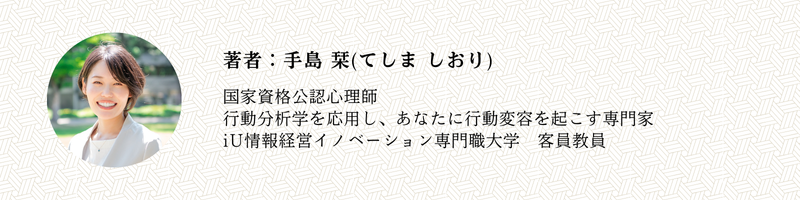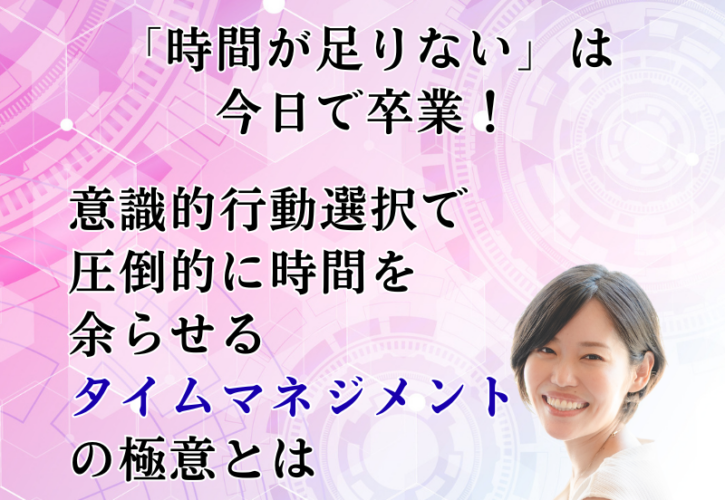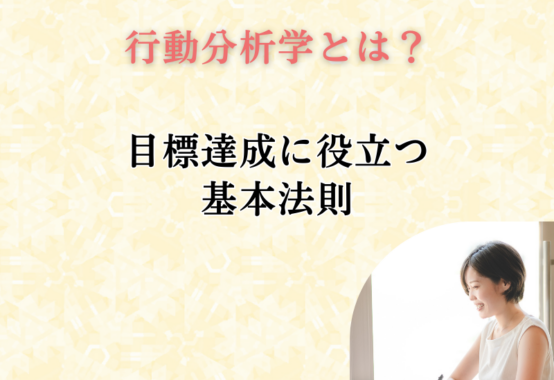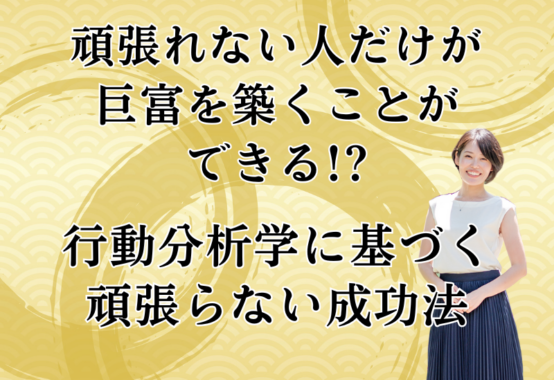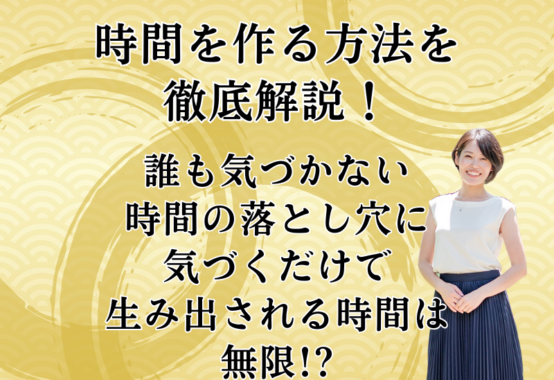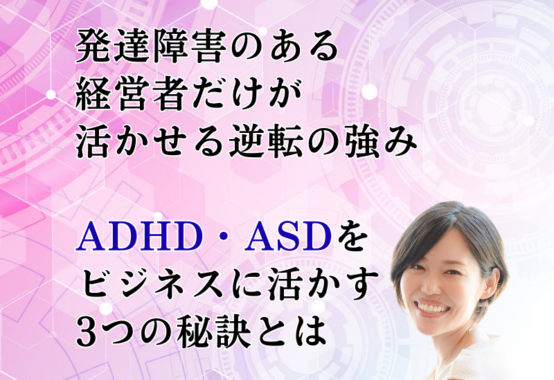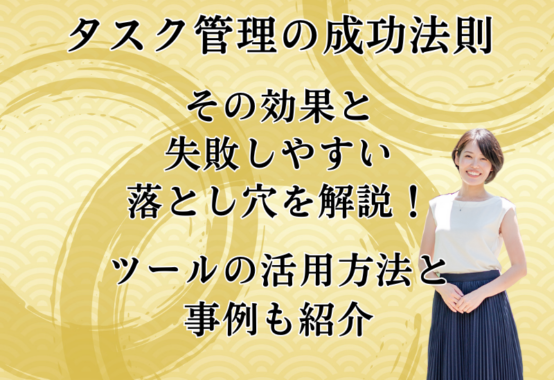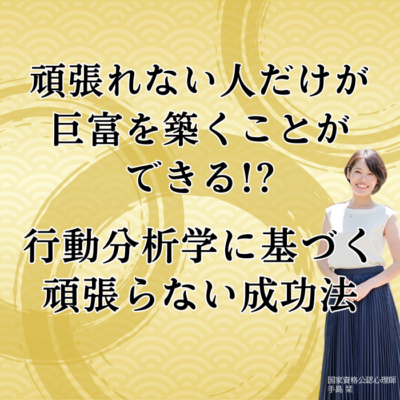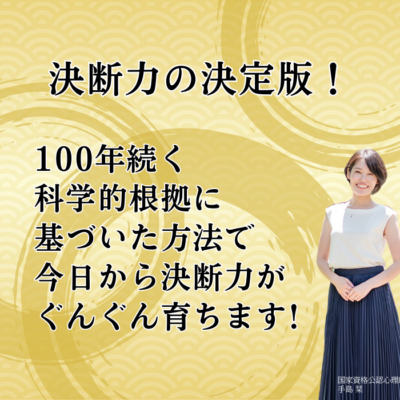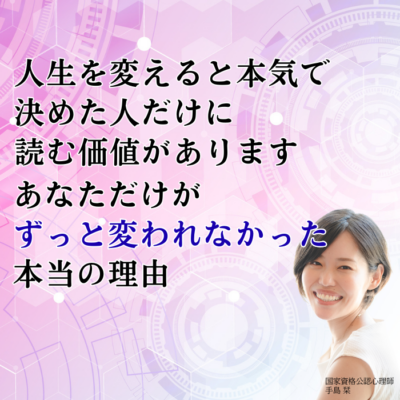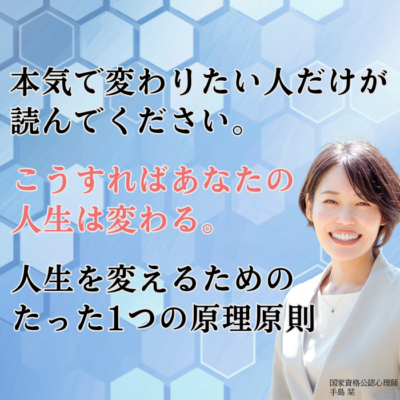こんにちは。行動分析学の専門家、手島栞です。目標を立てて行動をしても、いつも途中で挫折してしまう…。そんなお悩みを抱えている方に向けて、行動しやすくなるためのヒントをお伝えしています。
「時間が足りない」
もっと効率的に動きたい。
もっと余裕を持って過ごしたい。
そして何より、自分の能力や行動、人生そのものを「意図的に」選び取れる自分でありたい。
…そう願っているのに、現実は思い通りにいかない。
気づけば予定に追われ、やるべきことに振り回され、
「また今日も、望んでいた時間の使い方ができなかった」と自分を責めてしまう。
そんな日々に、そろそろ終止符を打ちませんか?
この記事では、「時間の使い方そのもの」を意識的に選び取るための具体的なアプローチを、行動分析学の視点からわかりやすく解説していきます。
時間の余白は、あなたの中に眠る可能性を引き出すスペース。
「時間に追われる人生」から、「時間を味方につける人生」へ。
その転換のきっかけを、ここから一緒に見つけていきましょう。
時間不足の本質を知ろう|“時間管理はスキル”という考え方

「時間が足りない」
「やることが多すぎて、もうパンクしそう」
そんなふうに感じたとき、多くの人がまず思うのは――
「自分の能力が足りないんじゃないか」
「もっと頑張らなきゃいけないのかも」
…という、自分への責めの気持ちです。
でも実は、時間に関する悩みの多くは、性格や意志の問題ではなく、知識やスキル不足の問題です。
時間管理は、生まれつき得意な人だけができる特殊な才能ではありません。
むしろ、やり方を知り、試行錯誤を重ねることで誰でも習得できる、後天的な「技術」なのです。
たとえば、いつも計画通りに動ける人や、時間にゆとりがあるように見える人。
彼らが最初からそうだったわけではありません。
自分の生活リズムや特性に合わせた“時間の扱い方”を見つけ、それを習慣として定着させているだけです。
時間の使い方には、「これが正解」という万能なやり方は存在しません。
生活環境、性格、仕事の仕方、家庭の状況…背景が違えば、合うやり方も変わって当然です。
朝が苦手な人に、朝活は向かないかもしれません。
予定が詰まりやすい人には、バッファ(予備時間)が欠かせません。
誰かの方法を真似してうまくいかなかったとしても、それは「あなたがダメ」なのではなく、「その方法があなたに合っていなかっただけ」なのです。
だからこそ、時間の悩みを解決する最初の一歩は、
「自分に合ったやり方は、きっと見つかる」という前提に立ち直すこと。
時間管理は、学び、慣れ、工夫していくことで確実に上達します。
焦る必要はありません。
ここから一緒に、あなたにフィットする時間の使い方を見つけていきましょう。
時間はお金と同じ?違う?|使っている意識の有無がカギ

「時間は大切にしなきゃ」
そう思っているのに、いつも足りないと感じてしまう…。
その背景にあるのは、時間の「使い方」に対する認識の違いかもしれません。
この章では、「お金」との違いをヒントに、時間の捉え方を見直してみましょう。
時間も「有限の資源」。でも、お金とは決定的に違う
「時間はお金と同じように大切な資源」
そんな言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
たしかに、時間もお金も有限であり、どう使うかによって成果に大きな差が出るという点ではよく似ています。
でも、決定的に違う点がひとつあります。
それは、お金は貯めたり増やしたりできるのに、時間は一方的に減っていくだけだということ。
しかも、一度失った時間は、どんなに努力しても取り戻すことができません。
「無自覚に使ってしまう時間」が、最大の落とし穴
この違いがあるにもかかわらず、私たちは時間を驚くほど無意識に使ってしまっています。
たとえば、なんとなくスマホを眺めていた30分。
この時間は、ただ過ぎただけではありません。
本来別のことに使えたかもしれない30分が、確実に失われたということです。
お金なら、レシートや口座明細で振り返ることができます。
でも、時間には明細がありません。
記録しない限り、何にどれだけ使ったのかを把握することができないのです。
まずは現状を把握する|“使い方の記録”で無駄を認識する

「時間が足りない」と感じているときほど、
実は自分が何に時間を使っているか、正確に把握できていないことが多いものです。
「なんだか忙しい」「気づいたら1日終わっていた」
そんな漠然とした感覚のままでは、改善の糸口は見えてきません。
まずは、今の時間の使い方を「見える化」することから始めてみましょう。
記録は“事実を知る”ための第一歩
時間の使い方を変えるには、最初にやるべきことがあります。
それは、現状を客観的に知ること。
私たちの頭の中の感覚は、意外とアテになりません。
たとえば…
- スマホを5分だけのつもりが、気づけば30分たっていた
- メールの返信に1時間以上かかっていた
- 「やることを整理するだけ」で、気づけば夕方になっていた
こうした感覚と現実のズレを埋めてくれるのが、時間の記録です。
主観ではなく、事実ベースで“使い方”を見直す。
そこから、時間管理の本当の改善が始まります。
続けられる方法でOK|おすすめの記録の取り方
「記録」と聞くと、面倒そう…と感じる方もいるかもしれません。
でも最初は、ざっくりでOK。大切なのは“続けられること”です。
以下のような方法があります
- 紙にメモ:ノートや付箋に、1時間ごとに「何をしていたか」をざっくり書く
- スマホのメモアプリやGoogleカレンダーに、予定と実績をざっくり残す
- タイムトラッキングツール(Toggl、Clockifyなど)で、作業時間を自動記録
- スクリーンタイム/RescueTimeなどのアプリで、スマホ・PCの利用時間を可視化
- 仕事風景を動画撮影して、自分の行動を客観的に記録
特に初めて取り組む方は、まず「何に使ったか」「どれくらいかかったか」をざっくり記録するだけでも、十分な気づきがあります。
24時間の行動を“可視化”する|意識的行動と無意識行動の2種類

行動を記録してみて、どう感じましたか?
「仕事はしていたはずなのに、思ったほど進んでいない気がする」
「気づいたら時間が経っていた…そんな空白が意外と多かったかも」
そんな感覚がある方にこそ、この章の内容が役に立ちます。
ここでは、記録した内容を「意識的な行動」と「無意識の行動」に分けて整理し、時間がどこで「抜けていた」のかを明らかにしていきましょう。
意識的な行動|目的が明確で、選択された時間
まずは「意識的行動」から。
これは、自分の意思で「何をするか」を選び、明確な目的を持って過ごしていた時間です。
たとえば…
- 会議、商談、資料作成、返信などの業務
- 食事、家事、運動などの生活習慣
- 子どもとの時間、勉強、読書などの自己投資
これらは「何をしていたか」が説明しやすく、記録にも残りやすいパートです。
ですが、この見える時間だけを整えても、時間不足の根本解決にはなりません。
無意識の行動|時間を使っているのに、やった感が残らない時間
見落とされがちなのが「無意識行動」です。
一言でいえば、「何をしていたか説明できないのに、時間が過ぎていた」時間のこと。
たとえば…
- タスクとタスクの合間に、なんとなくSNSをチェック
- 判断に迷って、数分〜数十分、手が止まる
- 集中が切れて「とりあえずメール」を開いたら、30分経過していた
- 会議後、疲れて動けず、しばらくぼーっとしてしまう
こうした時間は、一見「休憩」のように見えて、心身の回復にも作業の前進にもなっていない“空白”です。
しかも、1日あたりは数分でも、積み重なると週・月単位で大きなロスになります。
“すきま時間”は「余白」ではなく、「設計し直せる資源」
この可視化によって初めて見えてくるのが、意識せずに流れていた時間の存在です。
でも、これを「無駄だった」と切り捨てる必要はありません。
むしろ次章で紹介するように、これらの時間は“行動の設計ミス”や“環境のゆがみ”によって生まれていることがほとんどです。
そしてここからが、時間設計の醍醐味です。
可視化された“すきま”を活かせば、新たな余白や回復の時間を生み出すこともできます。
たとえば…
- 電車移動中にアイデアをメモする
- 15分だけ仮眠や軽い運動で集中力をリセット
- あえてタスクから離れて、思考の整理タイムにする
こうした工夫によって、“消えていた時間”が“使える時間”に変わっていきます。
時間は奪われるものではなく、意図的に取り戻せるもの。
経営者や多忙なビジネスパーソンにこそ必要なのは、この「使い直す視点」です。
“無自覚な行動”が時間を奪う|原因と対処法

無自覚な行動は、
この章では、その中でも「無意識に時間を奪われてしまう行動パターン」に焦点を当て、
なぜそれが起きるのか?そして、どうすれば繰り返さずに済むのか?を最低限の工夫で整えていきます。
なぜ“無自覚な行動”が起きるのか?
“空白”が生まれる背景には、共通するいくつかの要因があります
- やりたくない感情への回避(タスクの難しさ、不確実性、失敗への不安)
- やり方が曖昧なまま着手しようとしてフリーズ(判断ができない)
- 「これくらいで終わるだろう」という甘い見積もり(現実とのギャップ)
- 脳や身体の消耗による自然な逃避(本能的なエネルギー節約)
つまりこれは「サボっている」のではなく、
思考と行動が「設計されていない」ことによる構造的エラーなんです。
対処の第一歩は、自分の“避けがちなパターン”を知ること
全部を一気に変える必要はありません。
まずは、自分にとってよくある“回避パターン”を見つけ、
起きたときに自動で対応できる仕組みを1つずつ整えていきましょう。
| よくある無自覚行動 | 対処の工夫 |
| やりたくないタスクに着手できない | タスクの手順を細かくし、はじめの行動だけ取り組んでみる 「5分だけやる」と決め、タイマーをかけて取り組む |
| 会議後に手が止まる | 「会議後にやることリスト」を事前に用意しておく |
| 気づけばSNSに逃げていた | スマホを別室に置く or アプリに時間制限をかける |
ポイントは、意志で我慢するのではなく、「起きないように環境を設計する」ことです。
人は誘惑に弱い生き物。ならば、誘惑から遠ざかる仕組みを用意するほうが、ずっと賢い選択です。
計画と実行のすり合わせ|“未来の自分”をリアルに想定するテクニック

時間の見積もりが得意な人は、過去の経験をもとに現実的な予測ができる人です。
逆に、苦手な人は毎回タスクの所要時間を甘く見積もり、ズレに気づかないまま予定倒れを繰り返します。
このズレを放置すると、自己効力感の低下や慢性的な疲労感につながっていきます。
原因は「理想の自分」を前提にした計画
時間の見積もりが、現実と大きくズレてしまう原因として、「理想の自分」を前提に計画を立てていることが挙げられます。
- 「明日は集中できるはず」
- 「あれとこれも、午前中にやれるはず」
- 「邪魔は入らないはず」と考えてしまいます。
でも現実には、予期せぬ対応、集中の波、疲労の蓄積など、思い通りにいかない要素が毎日のように発生します。
それらを無視して立てた予定は、崩れるのが当然なのです。
ズレを防ぐための3つの視点
① 「体感」ではなく「データ」で見積もる
見積もり精度を上げるには、実績ベースで判断するのが一番です。
- 書類作成は、毎回90分かかっている
- 朝イチは雑務が多く、集中タスクに向いていない
- 会議後は、切り替えに30分かかる傾向がある
こうした傾向を記録しておけば、計画が現実に近づきます。
② 理想の自分ではなく、「今日の自分」で計画する
未来の自分に過度な期待をするのではなく、現実の自分を前提に計画しましょう。
- 金曜の午後は集中しにくい
- 会議が連続する日は思考業務を避ける
- 睡眠不足の日はタスク量を抑える
「こうありたい自分」ではなく、「いまの自分」に合わせて組み直すことで、無理のない一日になります。
③ バッファ(余白)を“戦略的に”設ける
ズレは、完全には防げません。
だからこそ、あらかじめ「崩れること」を前提に、余白をつくっておくことが有効です。
- タスクごとに10〜30%の予備時間を上乗せ
- 午後の1時間を「空白ゾーン」に設定
- 金曜の午後を「未消化タスクの立て直し枠」にする
この戦略的バッファがあるだけで、予定が崩れても慌てずリカバリーできるようになります。
見積もりは“気合”ではなく、“スキル”で整えられる
うまくいかない計画は、あなたの能力の問題のせいだけではありません。
構造としてズレやすくなっている可能性も大いにあります。
だからこそ必要なのは、「がんばり」ではなく、
- 自分の傾向を観察すること
- 実績をもとに組み立て直すこと
- 現実に合わせた予備と緩衝の設計をすること
こうしたスキルの積み重ねこそが、再現性のある時間管理をつくっていきます。
今すぐできる“時間を増やす”3ステップ
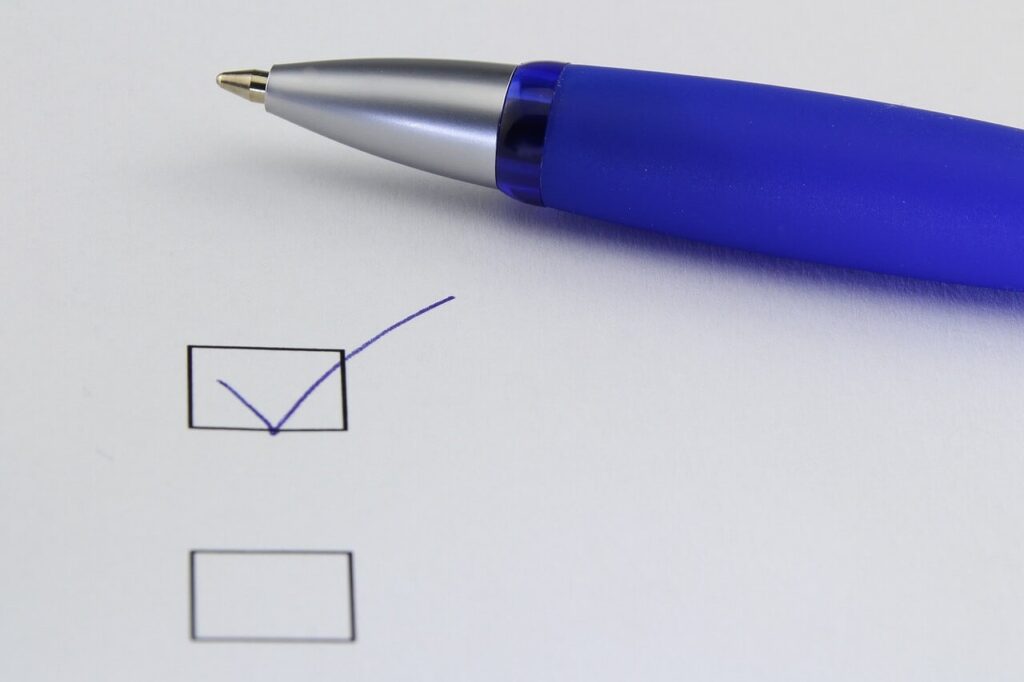
「結局、自分は何から始めればいいのか?」
ここまで読み進めてきたあなたに向けて、
この章では、今日から無理なく始められる「時間の再設計」3ステップをご紹介します。
ポイントは、生活そのものを大きく変えるのではなく、
小さな工夫を積み重ねていくこと。それが、時間の使い方を根本から変えていく近道です。
Step 1|「すき間時間」と「無意識の行動」に目を向ける
時間を見直す最初のステップは、「どこで時間が消えているか」を把握すること。
そして注目すべきは、長時間の仕事や会議よりも…
- 会議と会議の合間についSNSを開く
- 重たいタスクの前に、なぜかメールに逃げてしまう
- 作業のあとはしばらくぼーっとしてしまう
…そんな「小さな無意識の時間」です。
このような数分の行動も、1日に何度も繰り返せば、1〜2時間に相当します。
まずは、次の2つをチェックしてみてください
✅ どんな場面で「切り替えに時間がかかっている」か?
✅ どんな行動の最中に「目的を見失っている」か?
これが、時間を取り戻すための第一歩になります。
Step 2|「やめるリスト」をつくる
時間を増やしたいとき、真っ先にやりがちなのが「もっと頑張って詰め込むこと」。
でも、最初にやるべきなのは、やめることを決めることです。
たとえば…
- 実はやらなくても問題ないルーティン
- 自分がやらなくてもいい仕事
- 惰性で続けている作業手順
- 何度も開いてしまう同じチャットや資料
これらは、時間だけでなく思考力・判断力・集中力といった「脳のリソース」を知らないうちに削っています。
おすすめの問いかけ
✅ 「これは、今ほんとうに必要?」
✅ 「これを今日やらなかったら、何か困る?」
✅ 「誰かに任せる、という選択肢はある?」
「やらないことを選ぶ」という勇気が、時間の余白を生み出してくれます。
Step 3|小さく変えて、日々アップデートする
時間の使い方を変えるには、「一気に理想を目指す」のではなく、
小さく試して、ちょっとずつ整えることが何よりも大切です。
たとえば…
- 月曜の午前だけ、予定を入れずに余白時間をつくってみる
- タスクの前に「何分で終わるか」を予想して、後で答え合わせ
- スマホを見る回数を1日1回だけ減らしてみる
たったこれだけでも、「自分に合う時間の使い方」が見えてきます。
完璧を目指さなくて大丈夫。
ちょっとやりやすくなる工夫を、毎日ひとつずつ。
その積み重ねが、あなたにとって自然で快適な時間設計を育てていきます。
まとめ|自覚的な行動で時間は生まれ変わる

「また今日も時間をうまく使えなかった」
そんな日々から抜け出す鍵は、“時間の使い方”に自覚を持つことです。
行動を見える化し、計画と実行のズレをバッファで整える。
それだけで、追われる毎日から、自分で選び取る毎日へと変わっていきます。
時間は、意志ではなく仕組みで整えるもの。
焦らなくても大丈夫です。少しずつ整えていけば、あなたの毎日はきっと変わります。
時間管理スキルをどう活かす?専門家に相談する選択肢も
ライフステージや環境が変わっても、記録と分析の習慣があれば、時間の悩みには柔軟に対処できます。
それでも一人で限界を感じたときは、プロの視点を取り入れるのが最短ルートです。
私のサービスでは、あなたの生活や働き方に合ったオーダーメイドの時間設計をサポートしています。無料相談実施中です。
「本気で変えたい」と思ったときは、ぜひこちらをご覧ください。