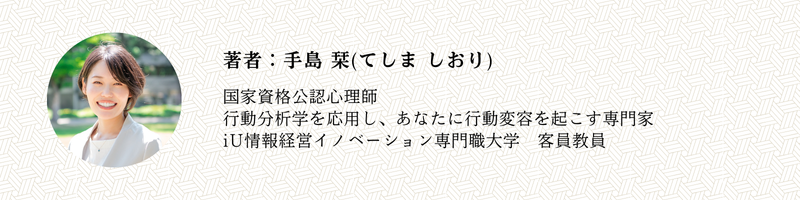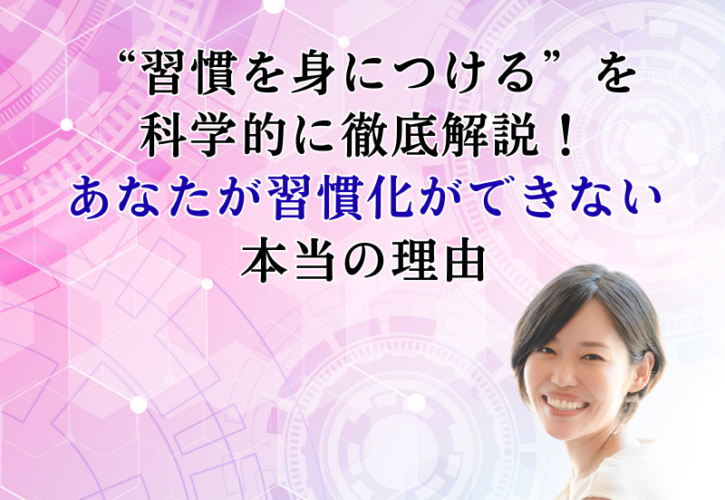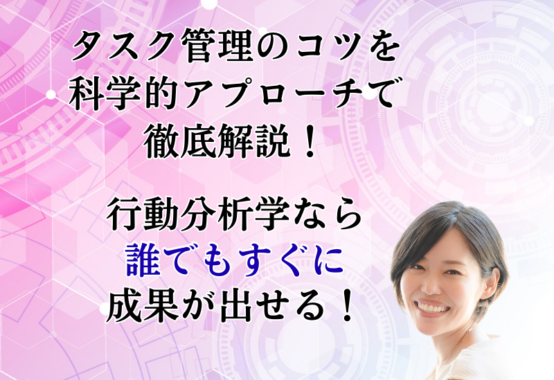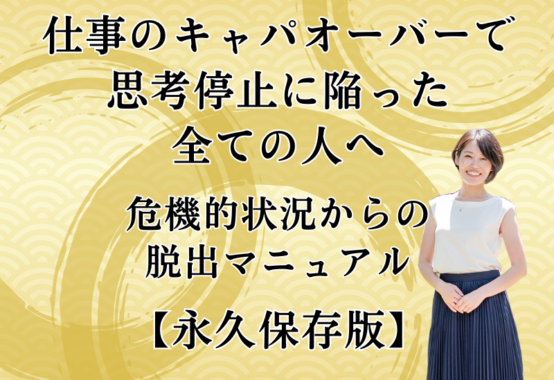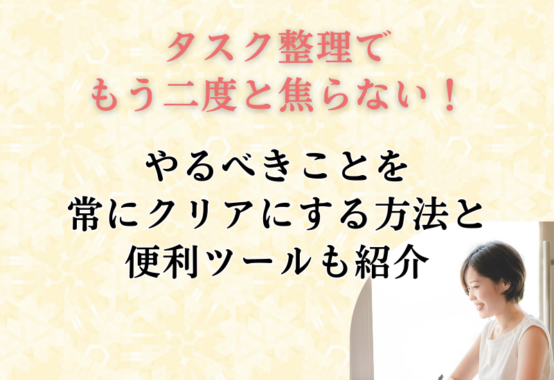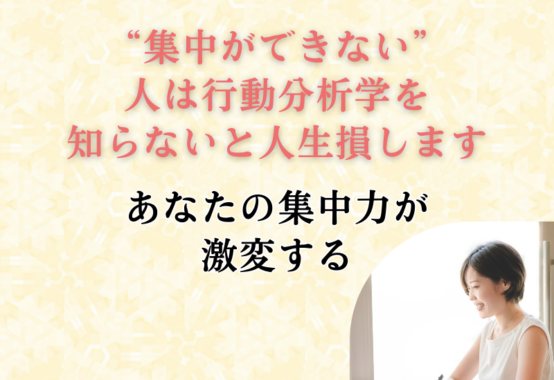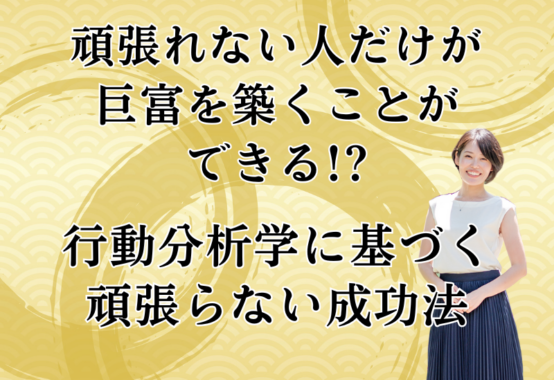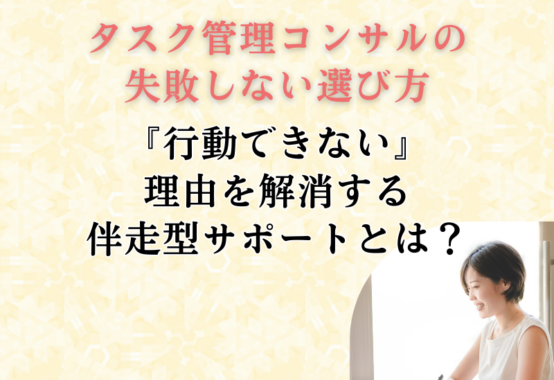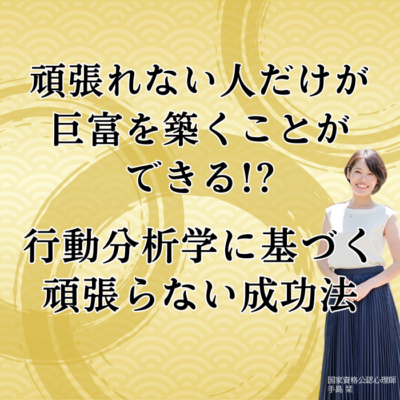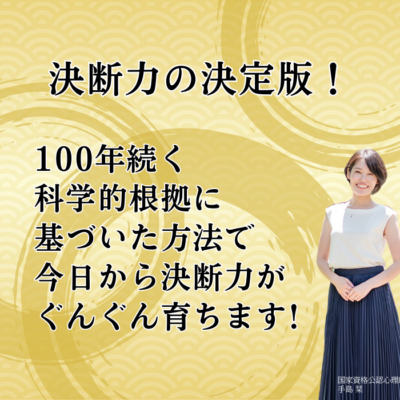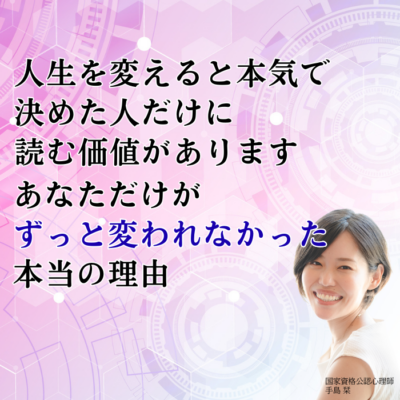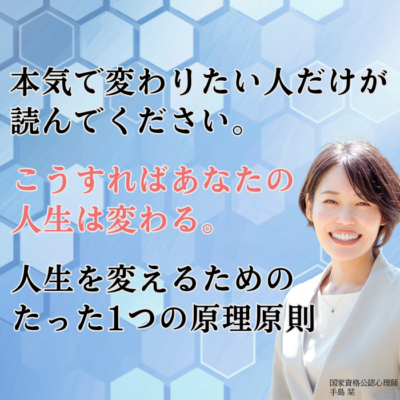こんにちは!行動分析学の専門家、手島栞です。 「どうしても、目標に向けた行動がとれない…」そんなお悩みをお持ちの方へ向けて、行動するためのヒントをお届けしています。
新しいビジネススキルを身につけよう!と意気込んでも、日々の業務に追われて、ついつい後回しにしてしまう…そんな経験ありませんか?
「継続は力なり」、頭では分かっていても、なかなか行動に移せない…なぜでしょうか?
実は、どんなに高い目標を掲げていても、自分の行動の仕組みをうまく活用できていないと、新しい習慣は思った以上に定着しないのです。そこで本記事では、行動の科学と呼ばれる行動分析学をもとに、「なぜ習慣が身につかないのか」という原因を徹底的に解説します。
習慣が身につかない理由を根本から理解すれば、どんな習慣も自由自在に身につけられるようになります。
「習慣を身につける」とは?3つのメリット
「今まで習慣を身につけられたことがない…」と感じている方は多いかもしれません。しかし、お話を伺うと、誰しも必ず何かしらの習慣を持っています。たとえば、箸の持ち方や着替えの順番、お風呂に入るときの手順など、子どもの頃から当たり前に身につけた行動は立派な“習慣”です。
習慣とは「考えなくても行動できる状態」
習慣とは、「何をするんだっけ?」「どうやってやるんだっけ?」「どの順番でやるんだっけ?」といった思考のプロセスがほぼ生まれない状態を指します。ビジネスの世界で成功を収めている方々は、まるで“自動運転”のように、迷いなく行動しているように見えませんか?実は、彼らの多くは、効果的な習慣を身につけているのです。この“自動運転”こそが、大きなメリットをもたらします。
- 1つ目のメリット:モチベーションに頼らなくていい
モチベーションには波があるのが普通ですが、習慣化された行動なら意志の力が弱いときでも「迷いなく」実行できます。童話の『うさぎと亀』になぞらえるなら、モチベーションのアップダウンに左右されず、亀のようにコツコツ続けられる仕組みこそが、長期的には有利なのです。 - 2つ目のメリット:エネルギーと時間を節約できる
私たちは日々、「何を食べる? 何を着る?」など多くの決断をしており、そのたびに思考を消耗しています。習慣として定着した行動は「やるかどうか」を悩まなくて済むため、経営や仕事での大事な意思決定に集中しやすくなるのです。 - 3つ目のメリット:日々の行動基盤ができると、目標達成しやすい
世の中の成功者は、やるべきことを「やり切った」共通点をもっています。成果が出るまで行動し続けるために、基盤となるのが習慣です。たとえば、「毎朝5分だけ学習する」「週に一度、新しいアイデアをまとめる時間を必ずつくる」といった小さな行動でも、地道に積み重ねれば大きな成果につながる可能性があります。
全てを習慣化すれば良いわけではない
習慣を身につけることで得られるメリットは大きなものですが、「全てを習慣化すれば良い」というわけではありません。
例えば、新規事業の立ち上げや、全く新しい商品開発など、前例のないことに挑戦する時は、過去のやり方にとらわれず、ゼロから発想する必要がありますよね。こうしたクリエイティブな作業は、毎回状況が異なるため、パターン化しづらく、無理にルーティン化すると、せっかくのアイデアが型にはまってしまうこともあります。
またあなたの仕事のなかで、突発的なトラブルや想定外の出来事に対応する場面が多い場合、すべてをルーティン化するのは難しいでしょう。そこで大切なのは、習慣化が適する行動と、そうでない行動を見極めることです。
たとえば、毎日積み重ねると効果が高い「生活習慣・学習・情報収集・定例のチェック」などは習慣化に向いています。一方、アイデアを練るときや特殊な問題解決が必要なときは、柔軟に考えを巡らせる必要があり、同じ手順を毎回繰り返すわけにはいきません。
このように、「習慣に向いている行動かどうか」をしっかり区別するだけで、習慣づくりの失敗を防ぎやすくなります。最終的には、本当に役立つ習慣を定着させるのがゴール。自分に必要な行動を選べば、モチベーションの波に振り回されず、スムーズに成果を出せるようになるでしょう。
世の中の「習慣神話」が抱える問題

習慣を身につけることに関して、一般的に信じられているものの、実際には科学的根拠が薄かったり、誤解に基づいている考え方があります。ここでは、いくつかの誤った習慣神話をご紹介します。
「21日間で習慣が身につく」:「21日間あれば、どんな習慣も身につく!」そんな言葉を耳にしたことがあるかもしれません。でも、これはちょっとした誤解です。実際に習慣が定着するまでの期間は、習慣の内容や、その人の個性によって大きく変わります。例えば、簡単な習慣(毎日水を飲むなど)なら比較的早く身につきますが、複雑な習慣(毎日新しいことを学ぶなど)は、もっと時間がかかることが多いのです。
「強い意志力があれば習慣は簡単に作れる」: 意志力は重要ですが、それだけに頼るのは非効率的です。あとでご説明しますが、意志力以外の戦略も組み合わせることで、より確実に習慣を身につけることができます。意志力は有限な資源であり、使いすぎると疲れてしまうため、環境や仕組みで補うことが大切です。
「習慣は毎日続けなければ意味がない」: 習慣は毎日行うものというイメージがありますが、必ずしもそうではありません。週に数回行う習慣や、特定の状況でのみ行う習慣も存在します。重要なのは、頻度ではなく、トリガーと行動の結びつきが確立されているかどうかです。こちらもあとでご説明します。
「マインドセットだけで習慣化はうまくいく」:マインドセットは習慣形成を支える土台になりますが、それだけで習慣が自動的に身につくわけではありません。習慣作りに役立つマインドを身につけながら、具体的な方法をとっていく必要があります。
行動分析学で解き明かす習慣の科学
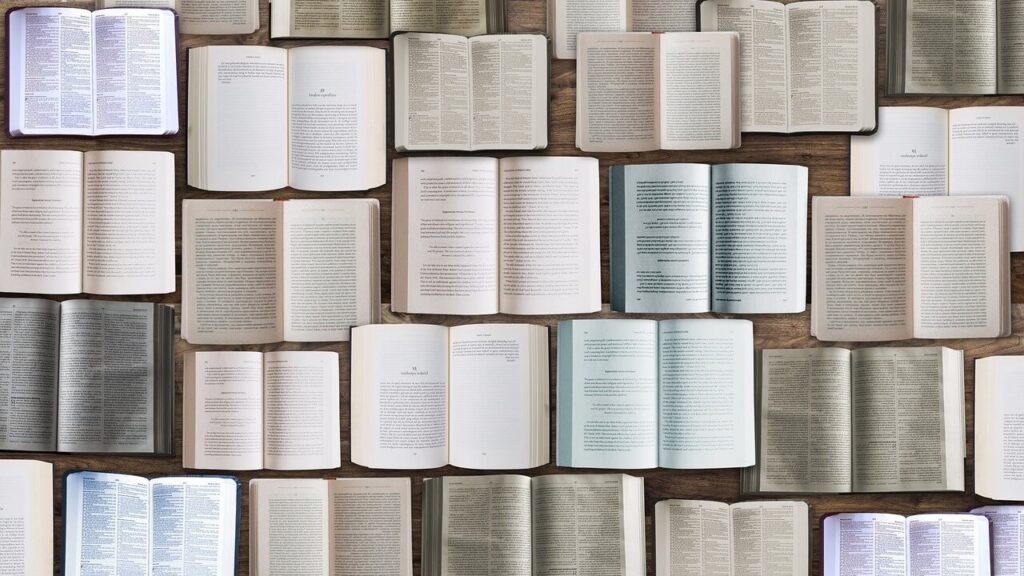
行動分析学という、人の行動を科学的に研究する学問があります。ここでは、行動分析学の視点から、習慣がどう定着し、どう続いていくのかをご説明します。
「トリガー」で行動が発動する
行動分析学でよく使われるフレームワークに、ABCモデルという考え方があります。
行動分析学では、人の行動は『ABCモデル』という3つの要素で説明できると考えられています。
Aは『きっかけ(トリガー)』、Bは『行動』、Cは『結果』です。
例えば、コップに水が入っている(A)、水を飲む(B)、のどが潤う(C)。このように、私たちの行動は、何かのきっかけがあって、それに対して行動し、その結果を受け取るという流れで成り立っているのです。
習慣を身につけるには、トリガーを固定化するのがポイントです。たとえば日記を書くという行動を習慣化させたい場合、「歯磨きをしたら日記を書く」など、既にある習慣をトリガーにすると、習慣化がしやすくなります。
また「電車に乗ったら本を開く」「タイマーが鳴ったら勉強する」「困ったらAさんに相談する」など、特定の行動や環境の変化、自分の内面の変化も、トリガーになります。
「強化」で行動が継続する
行動した後の「C:結果」によって、行動が継続・定着します。行動分析学ではこれを「強化」と言います。人は、ある行動の結果としてポジティブな成果を得たり、不快感を回避できたりすると、その行動を続ける傾向があるのです。
- 正の強化:行動後に得られるプラスの出来事(報酬・達成感・褒められるなど)
- 負の強化:行動後に不快な状況が減少・回避される(肩こりやストレスが軽減など)
「毎日続ける」だけが習慣ではない
「習慣=毎日やらなければいけない」と思うかもしれませんが、実はそうでもありません。行動分析学の視点からすると大切なのは「特定のトリガーが発動したときに、その行動を必ず取ること」です。
「週1回電車に乗ったら本を開く」といったペースでも、きちんと「そのときだけは必ずやる」形ができていれば、それも立派な習慣です。
行動の仕組みは人それぞれ違う
どのようなトリガーでどのような行動が発動されるのか。どういう結果を得たら、その行動が持続しやすいのかは、人それぞれ異なります。
この行動の仕組みの傾向は、子どもの頃から変わっていない部分も大いにあるので、自分自身の傾向を知ることで、意図的に習慣を作りやすくなります。
あなたの習慣が身につかない本当の理由

行動分析学の視点から見ると、習慣が身につかない原因は「トリガー」と「強化」の設計がうまくいっていないことにあります。
トリガーが曖昧、または存在しない
身につけたい習慣があっても、それを引き起こすトリガーが曖昧だと、行動に移しにくくなります。「時間があるときにやろう」「気が向いたらやろう」といった曖昧なトリガーでは、結局何もせずに終わってしまうことが多いです。
例えば、「毎日読書をする」という目標を立てても、「時間があるとき」というトリガーでは、他の用事や誘惑に負けてしまい、なかなか読書を始められないでしょう。しかし、「夕食後に食器を片付けたら、5分だけ読書をする」というように、具体的な行動をトリガーに設定すれば、読書を始めるきっかけが明確になり、習慣化しやすくなります。
以下のポイントを意識すると、習慣化の成功率が格段に上がります。
- 具体的なトリガーを設定する: 「時間があるとき」ではなく、「〇〇をした後」「〇〇の場所で」など、具体的で明確なトリガーを設定する。
- 既存の習慣をトリガーにする: 既に行っている習慣(歯磨き、朝食など)をトリガーにする。
- 環境をトリガーにする: 特定の場所や環境をトリガーにする。例えば、「書斎に入ったら仕事をする」「カフェに行ったら勉強をする」など。人も環境の一部なので「この人と会ったらこれをする」という方法もアリ。
強化(結果)が弱すぎる、または遅すぎる
新しい習慣の場合、すぐに目に見える結果が得られるとは限りません。例えば、運動習慣を身につけようとしても、すぐに体重が減ったり、体力がついたりするわけではありません。このように、本当に得たい結果が遅れてやってくる場合、行動を続けるのが難しくなります。
また「強化」の効力が弱すぎる場合も、行動は定着しにくいです。例えば、読書を習慣にしようとしても、読書自体にあまり楽しさを感じていない場合、途中で挫折してしまう可能性が高くなります。
強化を効果的に活用するためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 即時的な強化を用意する: 行動後すぐに得られる小さな報酬を用意します。例えば、読書中に好きな飲み物を飲む、運動中の写真をSNSに投稿し反応をもらうなどです。
- ポジティブな感情を強化にする: 行動後に達成感や満足感を感じられるように工夫します。例えば、読書後に学んだことをノートにまとめたり、運動後に体の変化を記録したりすることで、達成感や満足感を見える化できます。
- 内発的な動機づけを高める: 行動の仕方を工夫し、行動自体に楽しさや意義を見出すことができれば続けやすくなります。例えば、読書であれば、習慣ができるまでは自分の興味のある分野の本を選むことで内発的な動機と行動を連動させることができます。
身につけたい習慣と逆の行動が強化されている
「ダイエットのために甘いものを控える」という習慣を身につけようとしている人が、ストレスを感じたときに甘いものを食べてしまうと、ストレス解消という結果が得られます。この場合、「甘いものを食べる」という行動が強化され、「甘いものを控える」という習慣が定着しにくくなります。
このような状況を避けるためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 習慣と逆の行動を減らす: 身につけたい習慣と競合する行動をできるだけ減らすように環境を整えます。例えば、甘いものを家に置かない、ストレスを感じたときの代替行動(散歩、音楽を聴くなど)を用意するなどが有効です。
- 自己観察を行う: 自分がどのような状況で習慣を破ってしまうのかを記録し、分析することで、対策を立てやすくなります。
これらのポイントを意識することで、行動分析学に基づき、効果的に習慣を身につけられるようになります。
習慣を身につけるためのヒント

ここまでは、習慣が身につかない原因について、行動分析学の視点から解説してきました。では、実際に習慣を身につけるためには、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?
習慣化の方法は多岐に渡りますが、基本となるのは、以下の5つの要素を意識することです。
- 目的を明確にする
- 実行可能な小さな行動レベルに分解する
- トリガーや強化を自分に合うものに設計する
- 進捗を記録し振り返る
- 小さな成功を積み重ねる
これらの要素を具体的にどのように実践していくかについては、別の記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
「強化」の落とし穴
習慣を身につけるには、目標達成までの道のりが長いため、すぐに明確な報酬が得られるとは限りません。そのため「強化」だけで習慣を完全にコントロールしようとするのは、実は難しい場合があります。
強化だけに頼らない習慣形成のデザイン
習慣形成において、行動後の「強化」は重要な要素です。しかし、強化が得られるまでの期間が長い場合、即時的な強化となりにくく、モチベーションを維持するのが難しくなります。例えば、「新規事業の企画書を完成させる」という目標を立て、毎日少しずつ作業を進めようとしても、実際に企画が承認され、事業が動き出すという報酬(強化)が得られるのは、数ヶ月後、あるいはそれ以上先かもしれません。このように、強化までの期間が長い場合、途中で他の業務に気を取られたり、モチベーションが低下したりして、作業を続けるのが難しくなります。
そのため、強化だけに頼るのではなく、以下の2つの要素を重視した習慣化のデザインがおすすめです。
- 環境調整: 行動を促す環境を整えることで、行動へのハードルを下げます。例えば、企画書作成に集中したいなら、静かな書斎やカフェなど、集中できる場所を確保し、スマホの通知をオフにするなどが有効です。また、必要な資料やツールをすぐに使えるように整理しておくことも重要です。
- 行動トリガーの設計: 既存の習慣や日常動作をトリガーに設定することで、新しい行動を自然に組み込むことができます。例えば、「朝一番のメールチェックが終わったら、15分だけ企画書作成に取り組む」「昼食後の休憩時間に、アイデア出しの時間を10分だけ確保する」などです。
これらの要素を組み合わせることで、強化に頼らなくても、行動が自然と起こりやすい状況を作り出すことができます。
内発的動機づけと習慣の定着
やっていることが楽しい、意義を感じるなど、内発的動機づけとリンクする行動は、行動していること自体が報酬となるため、習慣として定着しやすいです。多少遠回りであっても、習慣にしたい行動自体を自分が楽しめる形にするというのも、非常に効果的な工夫の一つとなります。
例えば、「運動」を習慣にしたい場合、単に「体を鍛える」という目標だけでなく、「好きな音楽を聴きながら運動する」「仲間と一緒に運動する」「景色の良い場所で運動する」など、運動自体が楽しくなるような要素を取り入れることで、内発的動機づけを高め、習慣化を促進することができます。
継続の価値づけと記録の活用
日々できたことを記録し、自分で自分の進捗を認めることは、継続すること自体に価値づけをし、継続できている感覚(達成感)を得られるようにする効果があります。これは、自己効力感を高め、モチベーションを維持する上で有効です。
ただし、記録自体も習慣化しなければならないため、記録すること自体が負担になり、逆効果になる場合もあります。記録の方法は、自分に合った方法を選ぶことが重要です。例えば、手帳に簡単に記録する、アプリを活用する、カレンダーにシールを貼るなど、無理なく続けられる方法を選びましょう。
ネガティブな自己評価は、行動の定着を妨げる
行動の後に何も起こらなかったり、ネガティブな結果が起こったりすると、その行動は起こりにくくなります。
スモールステップで小さな目標を設定し、確実に行動できているにもかかわらず、「自分は全然できていない」「ゴールまでは程遠い」と、行動後の結果として自分自身にダメ出しをしてしまうと、せっかくの行動を自分で消すようなフィードバックをかけてしまいます。このようなネガティブな自己評価は、行動の定着を妨げるため、注意が必要です。
また、初めからハードルが高い目標を設定し、行動しても日々目標達成できない状態が続くと、これも行動を無くすことにつながります。スモールステップで、確実に、日々狙った行動をとれる状態を作り出すことが、習慣形成の成功につながります
習慣が身につくことを妨げるその他の要因

私たちの周りの環境や心身の状態も、習慣を身につけるうえで大きく影響してきます。ここでは、習慣の定着を阻む、見過ごされがちな要因について見ていきましょう。
環境の変動性
私たちの周りの環境は常に変化しています。環境から影響を受けやすい人は、特に以下のような変化は、習慣の定着を難しくする要因となります。
- 生活環境の変化: 引っ越し、転職、結婚、出産など、生活環境が大きく変わると、それまで築き上げてきた習慣を維持するのが難しくなります。新しい環境に慣れるまでは、心身ともに不安定になりやすく、新しい習慣どころではなくなってしまうこともあります。
- 人間関係の変化: 付き合う人が頻繁に変わる場合も、習慣の定着を妨げます。周囲の人のライフスタイルや価値観が変わると、自分の行動パターンも影響を受けやすく、習慣を維持するのが難しくなります。特に、新しい人間関係を築く際には、相手に合わせようとする意識が働き、自分の習慣を後回しにしてしまうことがあります。
- 仕事内容の変化: 仕事内容や勤務時間、職場環境などが変わる場合も、習慣に影響が出ます。新しい仕事に慣れるまでは、時間やエネルギーをそちらに取られ、習慣を維持する余裕がなくなってしまうことがあります。また、仕事の変化によって生活リズムが変わり、トリガーとしていた行動ができなくなることもあります。
生活リズムの不安定性
規則正しい生活リズムは、習慣形成の土台となります。しかし、以下のような要因によって生活リズムが不安定になると、習慣の定着が難しくなります。
- 睡眠の不安定: 睡眠不足や不規則な睡眠時間は、心身のコンディションを崩します。その結果、習慣を維持する意欲が失われたり、トリガーを認識できなくなったりすることがあります。
- 日々の活動の変動: 一日の活動が固定化されていない場合、トリガーとなる行動を設定しにくく、習慣を組み込むのが難しくなります。毎日違う時間に起きたり、違う場所で過ごしたりする生活では、習慣を定着させるための土台が築きにくいと言えます。
心身の状態の変動性
私たちの心身の状態は常に一定ではありません。以下のような要因によって心身の状態が変動すると、習慣の維持が難しくなります。
- 体調の波: 体調に波がある場合、体調が良い日は習慣を実行できても、体調が悪い日は実行できなくなってしまいます。このような状態が続くと、習慣が定着しにくくなります。
- ストレスの影響: ストレスは、心身に様々な影響を与えます。ストレスを感じているときは、集中力や判断力が低下し、習慣を維持する余裕がなくなってしまうことがあります。また、ストレス解消のために、習慣化しようとしていた行動とは逆の行動(例えば、暴飲暴食、過度な娯楽など)をとってしまうこともあります。
習慣形成を成功させるためには、行動や動機づけだけでなく、環境や生活リズム、心身の状態など、様々な要因を考慮する必要があります。
特に、上に書いたような変動性の高い状況にある場合は、習慣化の難易度が高くなることを認識し、より柔軟なアプローチを取ることが重要です。
完璧じゃなくていい

ここまで「習慣とは何か」「なぜ身につかないのか」を行動分析学の視点で解説しました。習慣を効果的に育てるには、「トリガー(きっかけ)」と「強化(結果)」が重要です。日常に目標達成の行動を組み込み、ご褒美を工夫することで無理なく続けられます。
「最初の一歩が踏み出せない…」と感じるのは普通のこと。でも今のあなたは、人間の行動の仕組みを知っています。完璧な計画は不要です。まずは小さな一歩を始めてみましょう。行動の積み重ねが未来を変えます。
さあ、あなただけの「成功習慣」をデザインしてみませんか?
科学の力で、習慣化の壁を乗り越える。手島栞のパーソナルサポート
「原因は分かったけど、実際にどうすればいいのか、自分だけでは不安だ…」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。もし、あなたがそう感じているなら、私、手島栞がお手伝いできます。
私は行動分析学という「行動の仕組みを解き明かす科学」を使って、一人ひとりに合わせた「成功習慣」を作るお手伝いをしています。
例えば、
- 「朝早く起きて、新しいことを学ぶ習慣を身につけたいけど、なかなか起きられない…」
- 「運動不足を解消するために、毎日運動する習慣をつけたいけど、三日坊主で終わってしまう…」
- 「仕事の効率を上げるために、タスク管理の習慣を身につけたいけど、いつも後回しにしてしまう…」
といったお悩みをお持ちの方に対して、
- 科学的根拠に基づいた習慣づけ支援: 行動分析学に基づき、なぜ行動できないのか?という原因を分析し、具体的な解決策をご提案します。
- トリガー設計や環境構築の具体的なアドバイス: あなたの生活スタイルや目標に合わせて、効果的な「トリガー(きっかけ)」を設定したり、行動しやすい環境を整える方法をアドバイスします。
- 個々の生活に合わせたカスタマイズプラン: 画一的な方法ではなく、あなたの状況や目標に合わせた、あなただけの「成功習慣」プランを一緒に作ります。
- 習慣が定着するまでの継続的なサポート: 計画を作るだけでなく、習慣がしっかりと身につくまで、継続的にサポートします。まるで、専属のコーチのように、あなたの習慣づくりを応援します。
「自分一人ではなかなか習慣化できない…」「科学的な方法で確実に習慣を身につけたい…」そうお考えの皆様、ぜひ一度ご相談ください。無料相談実施中です。詳しくはこちらをご覧ください。