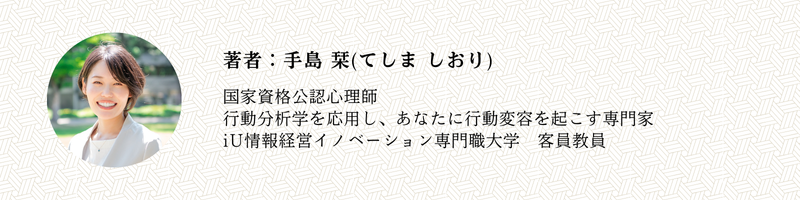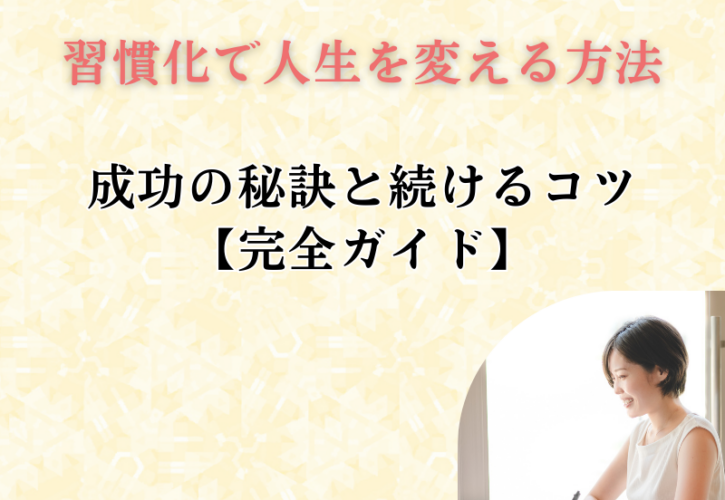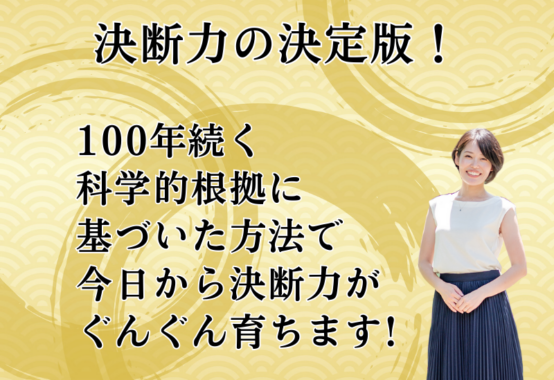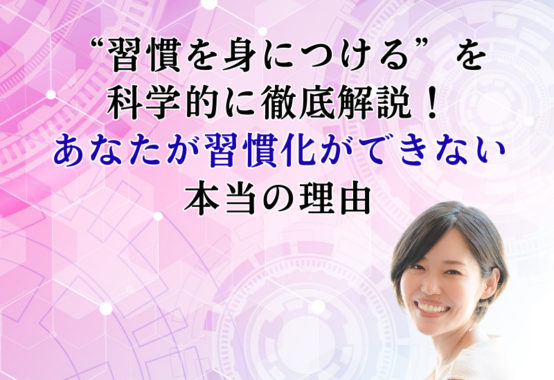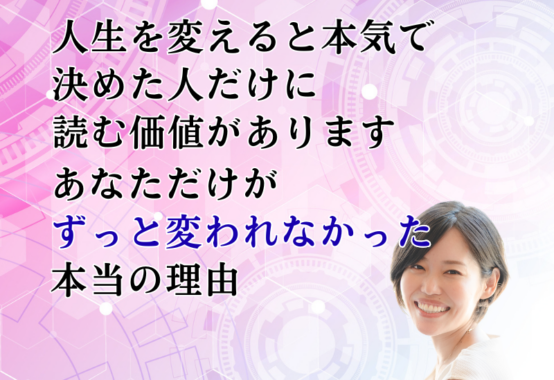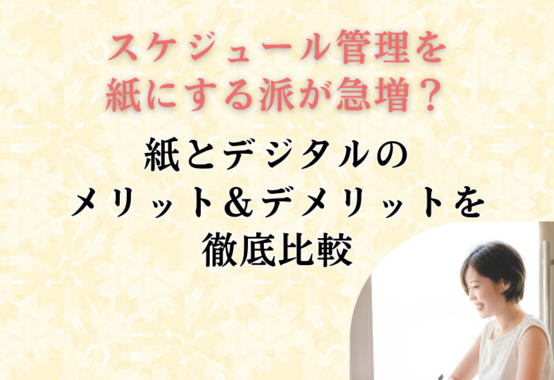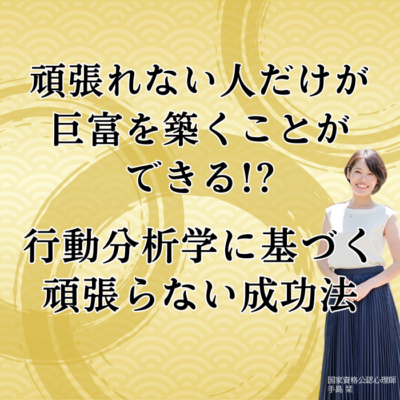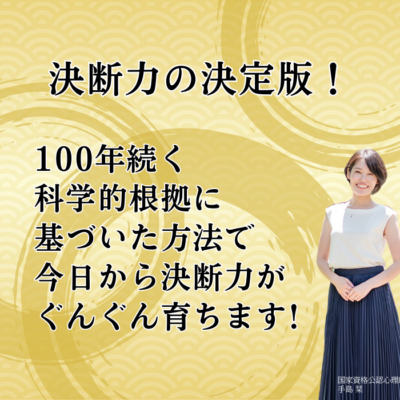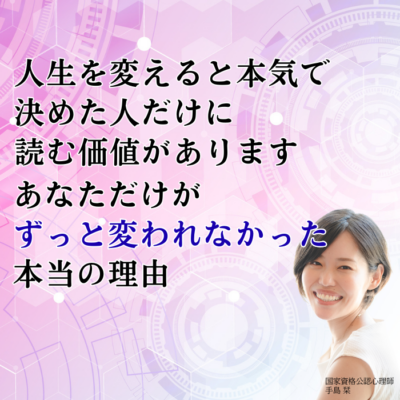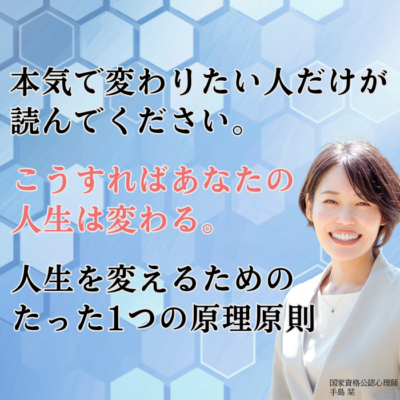こんにちは!行動分析学の専門家、手島栞です。「どうしても、目標に向けた行動がとれない…」そんなお悩みをお持ちの方へ向けて、行動するためのヒントをお届けしています。
ビジネスで成功したい、目標を達成したい。そう思ってはいるものの、『なかなか行動に移せない』『続かない』と悩んでいませんか?
頭では習慣化が大切だと分かっていても、日々の忙しさに追われ、つい先延ばしにしてしまう…。
私はこれまで多くの方とお会いする中で、習慣化の重要性を認識しながらも、実践に苦労されている姿を数多く目にしてきました。
習慣化は、目標達成のための強力な武器となります。この記事では、私がこれまで培ってきた知見と、数々の成功事例に基づき、『習慣化が難しい』と感じているあなたに向けて、成功の秘訣と続けるコツをお伝えします。
習慣を変えるための3つの条件:「知識」「意欲」「技術」
心理学や教育学の複数の理論によると、習慣を変えるためには以下の3つの条件が必要だといわれています。
①知識
②意欲
③技術
この3つの条件が揃うことで、初めて習慣を変えるための土台が整います。しかし、これらの条件は単独では機能せず、互いに補いながら作用します。それぞれを具体的に見ていきましょう。
①知識
「知識」とは、何をどうする必要があるのか、またその理由を理解することです。
たとえば、健康的な生活を送りたい場合、「運動が健康に良い」「適切な睡眠が必要」といった基本的な情報がなければ、適切な行動を選ぶことができません。
また、その行動の目的や背景(なぜ運動が健康に良いのか)を知ることで、行動の意味をより深く理解し、実行しやすくなります。
②意欲
「意欲」とは、行動を変えようとする気持ちや態度を指します。
どんなに正しい知識や高い技術を持っていても、実行しようという意志がなければ行動にはつながりません。意欲を高めるためには、自分の中で「なぜその行動をするのか」という内的な動機を明確にすることが重要です。
目標を具体的にイメージしたり、周囲からの支援を得たりすることも意欲の維持に役立ちます。
③技術
「技術」は、必要な行動を起こし、それを持続させるためのスキルや方法を指します。具体的には、新しい行動を身につけるための練習や、行動を維持するための仕組みづくりがこれに該当します。
2章からは、習慣化の「技術」を身につけるうえで、必要な知識や考え方をお伝えします。
習慣化とは何か?その本質と意味

習慣化の技術を身につけるためには、まず「習慣」とは何かを正しく捉えることが大切です。
習慣化された状態とは
習慣とは、何度もくり返して身についた“反応パターン”のことです。目に見える行動だけでなく、思考も習慣化します。
「反応」なので、やるかやらないかをその都度考えることなく、自然とそうしてしまうような行動になります。その行動をとらないことで「気持ち悪い」「落ち着かない」「怖い」という感覚になることも。
筋トレの習慣、読書の習慣など、毎日やることが習慣だと思われていますが、実はそうではありません。特定の環境で、いつも同じ行動をとるのであればそれは立派な習慣です。
たとえば、週末だけ車に乗るAさん。車に乗った時に、ドライバー席の背もたれを必ず調整します。毎日ではなくても、その環境になれば必ずとる行動は習慣化された行動であるといえます。
なぜ「習慣化」が人生や仕事を変えるのか?

習慣化の大きな魅力は、意思の力を使わなくても動けることです。
私たちのは「今日はどうしようかな」と迷い、「こうしよう!」と決めるたびに、時間とエネルギーを消耗します。しかし、習慣化された行動にはそうした迷いがありません。経営者の場合、重要な決断やアイデア出しなど、習慣化できない仕事が常に待っています。そこにエネルギーを集中するためにも、習慣化は心強い味方になります。
また、成果が出るまで時間がかかる行動ほど、習慣にしておくことが重要です。新しいビジネス企画や知識の習得は、一朝一夕では形になりません。そこで毎日5分だけでも新しい行動を続けることで、少しずつ確かな進歩を積み上げられます。そうやって積み重ねた結果は、後々「大きな成功」や「新しいチャンス」として返ってくるのです。
さらに、習慣化された行動は精神を安定させます。たとえばスポーツ選手が試合前に同じ動きをくり返すように、ルーティンには心を落ち着ける効果があります。ビジネスパーソンでも、仕事前に必ず机を整頓する、昼休みに短い散歩をする、などのルーティンを作れば、日々のストレスを減らし集中力を高める助けとなるでしょう。
習慣化とモチベーションの違い
モチベーションは、環境の変化やその日の気分、体調によって上下します。そのため、一瞬の意気込みだけでは継続が難しく、忙しい日々に流されがち。
だからこそ、忙しい経営者ほど、無意識レベルで行動できる習慣の力を活かすのがオススメです。長く続く行動こそが、ビジネスと人生を大きく前進させる鍵となります。習慣化を味方にすれば、気分が乗らない仕事でも、やる気に左右されずに進められるため、成果への道が自然とひらけます。
なぜ習慣化は難しいのか?

実は、誰もが知らず知らずのうちに何かしらの習慣を持っています。朝目覚まし時計を一度止めてから二度寝することも、仕事終わりにデスクを片付づけないことも、あなたが望んでいなくても立派な習慣です。
こういった習慣は、昨日今日身についたものではありません。また大抵の場合、なぜその習慣が身についているのか、自分でも自覚がありません。
新しい習慣をつくるには、この「すでにある習慣」を上書きする必要があります。新しい習慣をつくることだけでなく、すでにある習慣を無くすことの難易度が高いのです。
だからこそ、すでにある習慣を無くしながら、新しい習慣をつくる2方向からのアプローチが必要になります。
習慣化を科学する:行動分析学の視点

習慣化を助ける方法は、世の中にいろいろありますよね。そのなかで、科学的根拠にもとづいた習慣化の技術が「行動分析学」です。
行動分析学を活用すると、あなたの習慣がなぜ身についているのか(あるいは身につかないのか)原因に基づいて、具体的な解決策を導き出せるようになります。
私はこれまで、2歳の子どもから50代の経営者まで、幅広い世代の方々の習慣化を「行動分析学」を活用してサポートしてきました。
科学的根拠に基づく方法だからこそ、やる気や性格に左右されるのではなく、人を選ばず、習慣化を実現できるのです。
なぜ人は同じ行動をくり返すのか?
人が同じ行動をくり返すのは、今の行動がもたらすメリットと、“環境からのちょっとした合図”が大きく関係しているからです。たとえば、夜にスマホでSNSを見てしまう人は、その行動から手軽な楽しみやリラックスを得ています。もし「寝る前に読書をする習慣をつくろう」と思っても、スマホを触ることで得られていた気軽さがなくなるため、新しい行動に切り替えるのは簡単ではありません。
さらに、私たちの周りには、「ソファーの上に雑誌があれば、つい読んでしまう」「パソコンが開いていれば、なんとなくメールをチェックする」といった合図が潜んでいます。こうした環境からの刺激が“いつもの流れ”をつくり上げているため、これを断ち切るには、それまでの行動が得ていたメリットを補ったり、合図そのものを変えたりする工夫が必要です。
つまり、人は今の行動で得られている快適さや安心感を手放したくないうえに、無意識の合図に引きずられやすいという構造の中で暮らしています。この仕組みを理解すれば、ただ「がんばろう」「やる気を出そう」と言うだけではなく、環境や結果をうまくデザインすることで、新しい習慣へ移行できる可能性が大きく高まるのです。
行動分析学から見る習慣化の本質

4章では、行動分析学の理論的な土台を学びました。ここでは、その理論を踏まえて「習慣化の本質」を探り、“意志や性格だけに頼らずに行動を変える”ための考え方を整理してみましょう。
行動分析学が示す「環境」と「行動」と「結果」の密接な関係
習慣化を考えるうえで重要なのは、「行動は、環境の影響を受ける」ことです。4章でご説明したとおり、私たちは環境からの合図(トリガー)と行動後の結果(ごほうび、嫌なことの回避など)の組み合わせによって、自然と同じパターンを繰り返します。
スマホが目に入るだけで、集中が途切れる。お菓子が机の上にあると、つい手が伸びる。これは性格の問題ではなく、環境が行動を引き出している行動の仕組み上の問題です。
このとき、行動の“結果”が「楽しい」「気軽」「ストレス発散になる」といった小さなメリットをもたらすと、さらにその行動をくり返しやすくなります。こうした結果が無意識に行動を支えているため、なかなか別の行動に切り替えづらくなるわけです。
この視点をもつと、「自分は意志が弱いから続かないんだ」という自己否定よりも、「環境のつくりを少し変えれば、無理なく続けられるんだ」という建設的な見方ができるようになります。
こちらの記事では、この関係性についてより詳しく説明しています。
目標や「行動の仕組みの個別性」に合わせて“仕掛け”をデザインする
行動分析学では、個人的な目標や、すでに身についている習慣、人それぞれの行動のしやすい条件(あるいは、しにくい条件)を踏まえて、習慣をデザインします。
たとえば「夜型の人が朝の読書を習慣にしようとすると、そもそも起きられず失敗しやすい」というケースがあります。この場合、なぜ朝に読書を習慣化したいのか、なぜ夜型の生活になっているのか、起きられるときはあるか、それは再現性があるか…など、さまざまな個人的な要因を考えていきます。
〇本質的なポイント
- 自分の行動傾向を把握する
- 行動前の合図(環境)を整え、行動後に得られる小さなメリット(報酬)を意図的に作り出す
- 定期的に見直す(合わなければ微調整する)
これは、意志力に頼らずに行動を続ける仕組みを作る考え方です。いかに自分に合った設計をするかが習慣化の肝となります。
「行動の本質を知る」ことが挫折や惰性を防ぐ
「新しい習慣を始めても三日坊主で終わってしまう…」という悩みの背景には、「なぜその行動をやるのか」「なぜ同じ失敗を繰り返すのか」の核心が曖昧になっている場合があります。行動分析学の視点を取り入れると、それぞれの行動に「どんなメリットが隠れているか」「どんな環境が影響しているか」を冷静に分析できるようになります。
〇本質的なポイント:
- 「本当はどんな結果を望んでいるのか?」を言語化する(=行動の目的をはっきりさせる)
- 「続けられない原因」を報酬や環境面から見直す(=“意志不足”だけの問題にしない)
このように“行動の本質”を知ることで、自分の習慣を客観的に捉えられます。あいまいな根性論や一時的なモチベーション任せではなく、科学的な仕組みを活用すれば、挫折しにくい道を切り開けるのです。
成功する習慣化のための基本原則

習慣化を成功させるうえで、いくつかの基本的な手順や考え方があります。ここでは、そのポイントを簡単にまとめてご紹介します。
目的・ゴールの状態を明確にする
はじめに、「なぜその行動を習慣にしたいのか?」をハッキリさせることが大切です。目的があいまいだと、途中で「これ、本当にやる意味あるのかな…」と挫折しやすくなります。たとえば、
- 運動を習慣にする→「健康な体を保ち、疲れにくい状態を目指す」
- 朝の読書を習慣にする→「ビジネス書から最新情報を学び、仕事のアイデアを膨らませる」
小さな一歩から始める、または質を求めず行動をなぞる
新しい習慣をつくるとき、いきなり大きな目標を掲げると負担が大きく、途中で挫折しやすくなります。
- 小さく始める: 読書の場合、「1日5分だけ」「1行だけ読む」「1駅だけウォーキングする」といった形にすれば続けやすい。
- 質を求めず、形をなぞる: 完成度にこだわらず、「とりあえずやる」を繰り返すうちに、自然と行動が身についていきます。
環境と結果の設計を自分に合うものに変える
どんなにやる気があっても、環境が整っていなければ行動を続けにくいですし、逆にやる気が低くても、行動後の結果(報酬)が魅力的であれば自然と行動をくり返すようになります。つまり、環境と結果(ごほうび)の二つをうまく設計することこそが、意志に左右されない習慣づくりの要です。
- 環境の設計
行動を始めるうえで「合図」となる環境を作り込みます。たとえば、机の上には必要な資料だけ置いて、余計なスマホ通知はオフにすると、集中しやすい流れが生まれやすくなります。運動を習慣にしたい人なら、ランニングシューズを玄関の目立つところに置く、運動着をあらかじめベッドサイドに準備しておくなど、小さな工夫が後押しとなってくれます。
- 結果(報酬)の設計
行動を始めるまではハードルを下げ、行動後(あるいは行動中)に小さなごほうびや達成感を味わえるようにします。たとえば、ランニングをするときにお気に入りのウェアやシューズを身につけるだけでも、「楽しい」「かっこいい」といった気持ちを得やすくなります。あるいは、作業が終わったあとにSNSで進捗を報告し、仲間の反応をもらうのも立派なごほうびになるでしょう。
進捗を記録し振り返り改善する
習慣化を続けていると、思った通りにいかない日もあります。そんなとき、行動を客観的に振り返る仕組みがあると修正がしやすいです。
- 記録のメリット: 「どんな環境で行動しやすかったか」「どのタイミングで失敗しやすいか」がわかる
- 振り返りと改善: 週に1度など、定期的に「うまくいっている点」と「うまくいっていない点」を振り返り、環境と結果を調整する
小さな成功を積み上げる
長続きする習慣ほど、「できた」という感覚を少しずつ得られる仕組みがあります。小さな行動でも成功体験を重ねることで、やる気の波に左右されず、行動が当たり前のものに変わっていくのです。
- たとえば、達成するたびに目に見える形で記録しておく(アプリのカレンダーや手帳に印をつける)と、自分が積み上げてきたものが実感しやすくなります。
今回の内容を、さらに詳しく手順や具体例を交えてまとめた記事があります。以下のリンクからぜひご覧ください。
→ 挫折ゼロ!習慣づけることが難しい原因と続くようになる5つのステップ
人生を変える習慣とは?
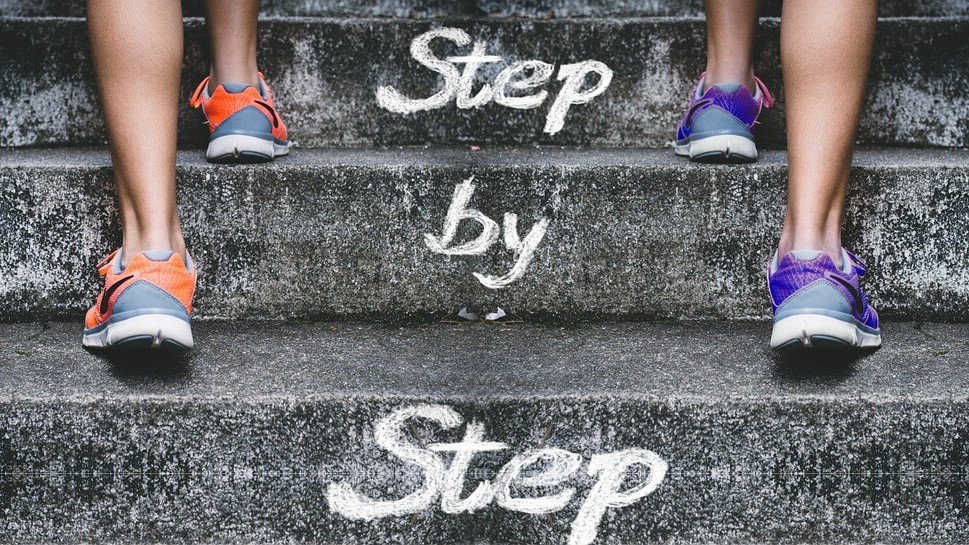
「人生を変える習慣」とは、一体どんなものでしょうか?
まず大切なのは、あなた自身がどんな人生を歩みたいのか、どんな目標を達成したいのかをはっきりさせることです。人によっては良いとされる習慣でも、あなたの人生プランには合わない場合もあります。だからこそ、習慣をつくるときは“自分の生き方”を起点に考えることが大切です。
それでも、多くの人にとって取り入れておいて損のない習慣はあります。たとえば、健康を維持する習慣です。大切なプロジェクトや目標があっても、体の健康を損ねてしまえば計画が崩れてしまうかもしれません。睡眠や食事、運動、定期的な健康診断などは、どんな人にとっても役立つ習慣だと言えます。
また、心の健康を守る習慣も欠かせません。趣味の時間を確保する、瞑想を取り入れる、環境をきれいに保つなど、リラックスとリフレッシュを得られる行動は、忙しい毎日の心の支えになります。
さらに、仕事を効率的に進める習慣もおすすめです。タスク管理や時間管理、集中力を高める工夫など、ほんの少しの日々の行動で、毎日の業務がスムーズに運ぶようになります。こうした習慣が積み重なることで、ビジネスや日常生活の質が大きく変わってくるでしょう。
習慣化が失敗したときのリカバリー方法
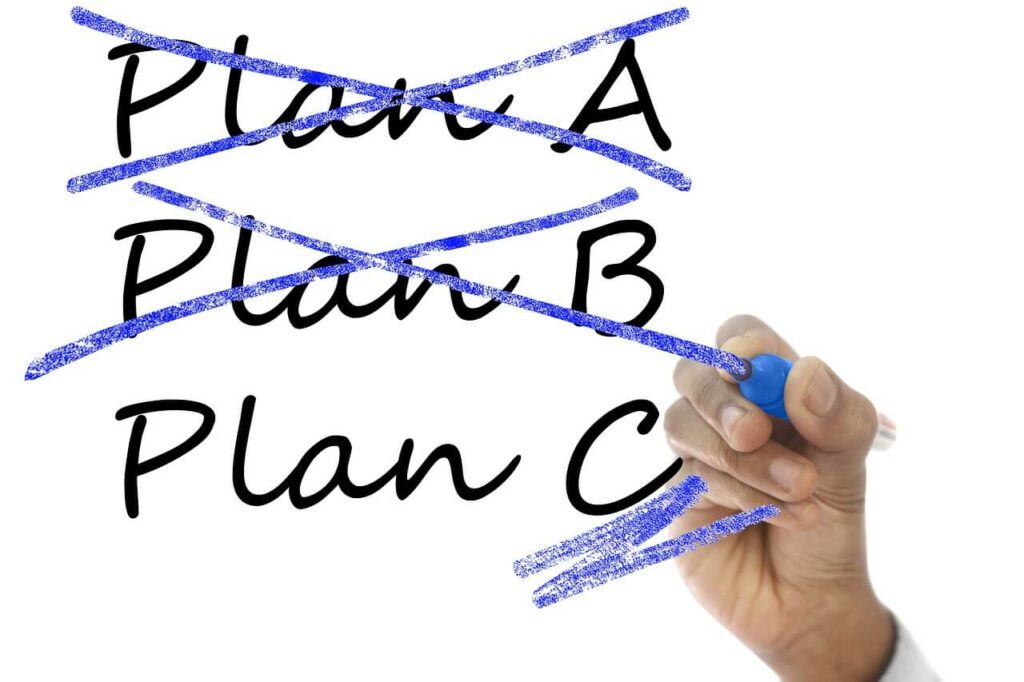
どんなに綿密に習慣化を進めても、最初のうちは必ずといっていいほど「挫折」や「失敗」に直面する場面がやってきます。大事なのは、失敗をただの終わりにせず、そこから学んで次に活かせるようにすることです。
8.1 失敗を振り返り、次に活かす方法
習慣化が途中で途切れてしまうと、「ああ、やっぱり続かないんだ…」とガッカリしがちです。でも、そこで終わりにせず、失敗をデータとして捉えて振り返ると、次につながる大きな学びが得られます。
- 環境はどうだった?
「朝起きづらい環境のまま、朝型の習慣を設定していなかったか」「スマホをすぐ触れる状態だったか」などをチェックしましょう。 - 結果(報酬)は見合っていた?
行動後に得られるごほうびや達成感が少ないと、行動が続きにくいかもしれません。小さな報酬を再設定してみるとよいでしょう。 - 開始レベルが高すぎなかった?
いきなり1時間の運動をするより、最初は5分だけウォーキングなど、小さく始めるほうが継続しやすくなります。
こうした振り返りをすると、自分の“習慣化を阻む要因”が具体的に見えてきます。あいまいな根性論ではなく、行動分析学の視点で環境と結果を見直すことで、次に活かせる対策が立てやすくなるのです。
たとえ失敗しても、自分のやり方を微調整すれば必ず再スタートできる――その理解こそが、習慣化を長続きさせるための最大の秘訣です。
まとめ:今日から始める習慣化の第一歩

本当に大切なのは今日、5分だけでも行動を始めてみることです。意志の強さに頼るだけでなく、環境を整え、行動後の小さなごほうびを用意すれば、自然と続きやすい仕組みができあがります。
三日坊主に終わった経験があっても、失敗はただのデータ。分析して再スタートを切れば必ず前進できます。
あなたが「今日」行動を起こせば、未来は必ず変わります。一緒に、習慣化による新しい毎日をスタートさせましょう。
行動分析学に基づいた習慣化サポートをご希望の方は、無料相談実施中です。
もし「一人でやるのが不安」「どこから手をつければいいかわからない」という方は、ぜひ専門家の力を借りてみてください。
行動分析学のアプローチで、あなたがうまくいかなかった原因をもとに、あなたの行動の仕組みや目標に合ったプランを立てて、一緒に走り続けます。サービスについての詳細は、こちらをご覧ください。