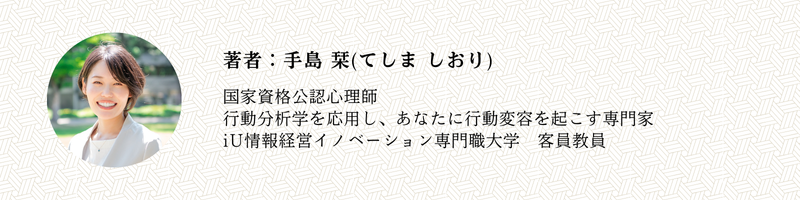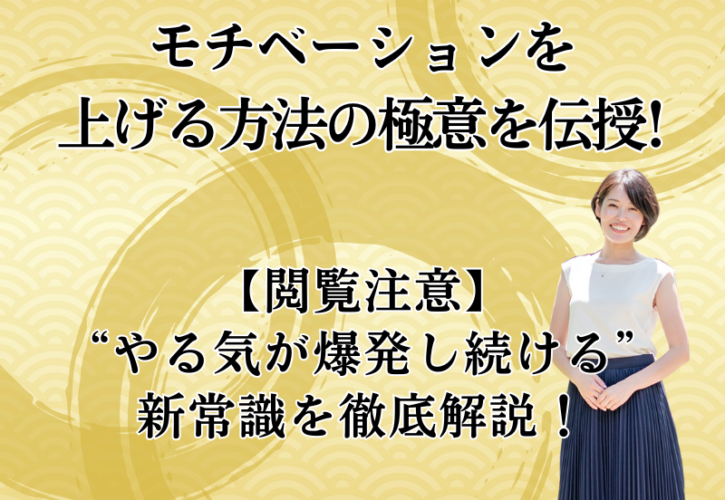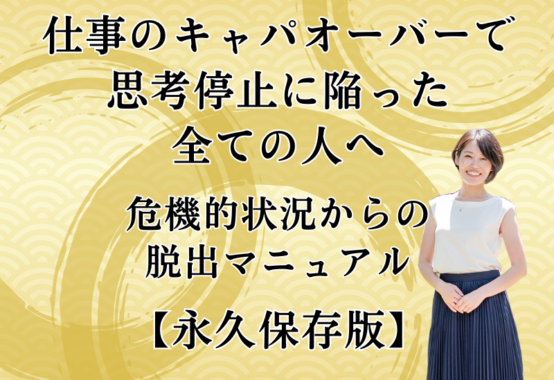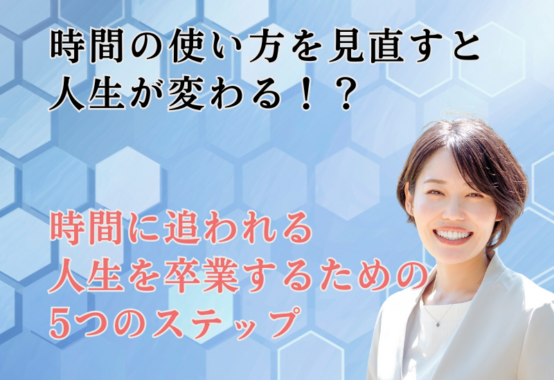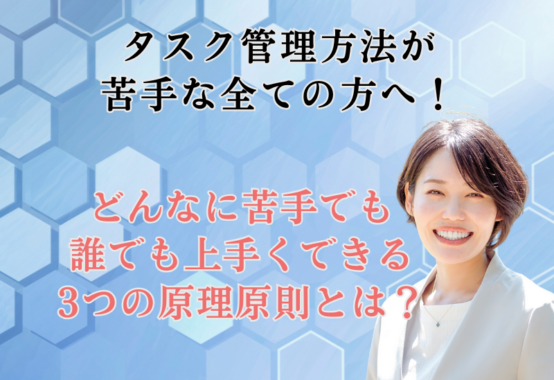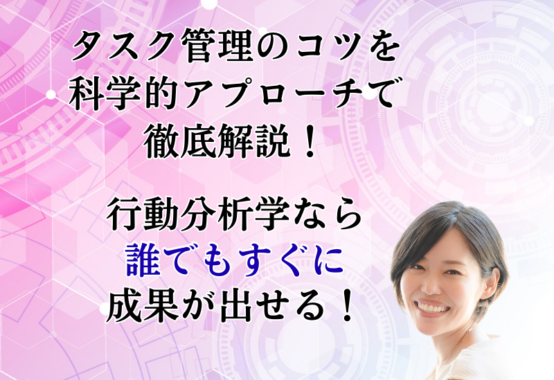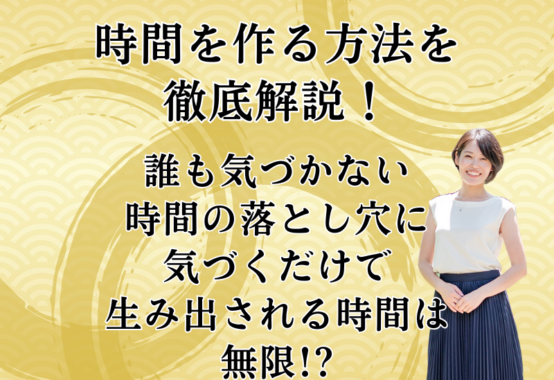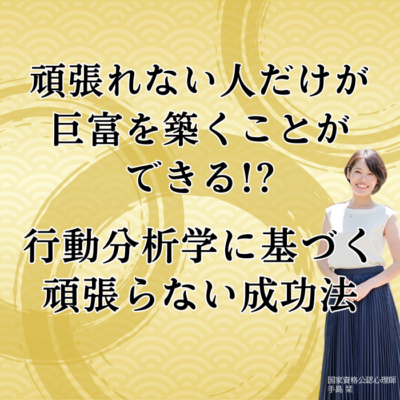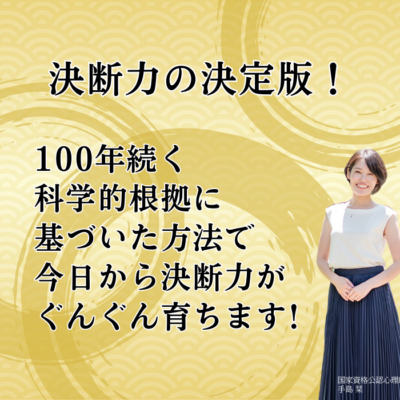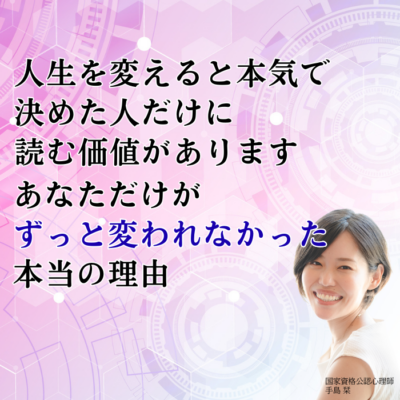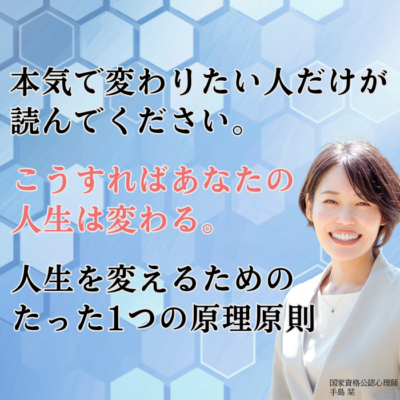こんにちは!行動分析学の専門家、手島栞です。「どうしても、目標に向けた行動がとれない…」そんなお悩みをお持ちの方へ向けて、行動するためのヒントをお届けしています。
多くの人が「やる気が出ない」「頑張れない」といった悩みを抱え、モチベーション(やる気)を何とかコントロールしたいと考えています。モチベーションが高いときはスムーズに行動できるのに、低いときはなかなか手が動かない…。こうした経験は誰にでもあるでしょう。
本記事では、そもそもモチベーションとは何なのか、そしてどうすれば上げられるのかについて、心理学の視点を交えてお話していきます。
モチベーションとは何か?
多くの人は「モチベーション」と聞くと、主観的な意欲や気持ちをイメージすると思います。実際、心理学の分野でも「モチベーション」をどう捉えるかについては、さまざまな理論が存在し、一口に「やる気」と言っても立場によって解釈が異なります。
「モチベーション」と聞いてイメージするのは、「やる気」「意欲」といった主観的で内面的な状態ではないでしょうか。
仕事や勉強、ダイエットなどで、「なんだかやる気が出ない…」と感じると、行動を起こすのが一気に難しくなってしまいます。これは、気分や感情が上下する人間の特性が大きく関係しています。
一般的なモチベーション論では、「気分や感情を高めるテクニック」を重視することが多いですが、これは一時的な効果にとどまりがちで、長期的な成果を保証するものではありません。
心理学におけるモチベーション:内的動機と外的動機
心理学の中でも、研究される分野によって「モチベーション」の定義はさまざまです。代表的な捉え方として、認知心理学における「動機付け」があります。
- 内発的動機づけ
行動そのものが楽しい、好奇心が湧くなど、自分の内面から自然に出てくるモチベーション。長続きしやすいと言われます。 - 外発的動機づけ
報酬や評価、罰など、外部の刺激をきっかけに生まれるモチベーション。すぐに行動に移しやすい反面、持続しにくい面が指摘されます。
実際には多くの人の行動は「内的か外的か」にスパッと分けられるわけではなく、両者が入り混じっているケースがほとんどです。
これが「自分のモチベーションがよくわからない」「意欲の波が激しい」という悩みを引き起こす原因にもなります。
行動分析学におけるモチベーション:行動を起こすための手段
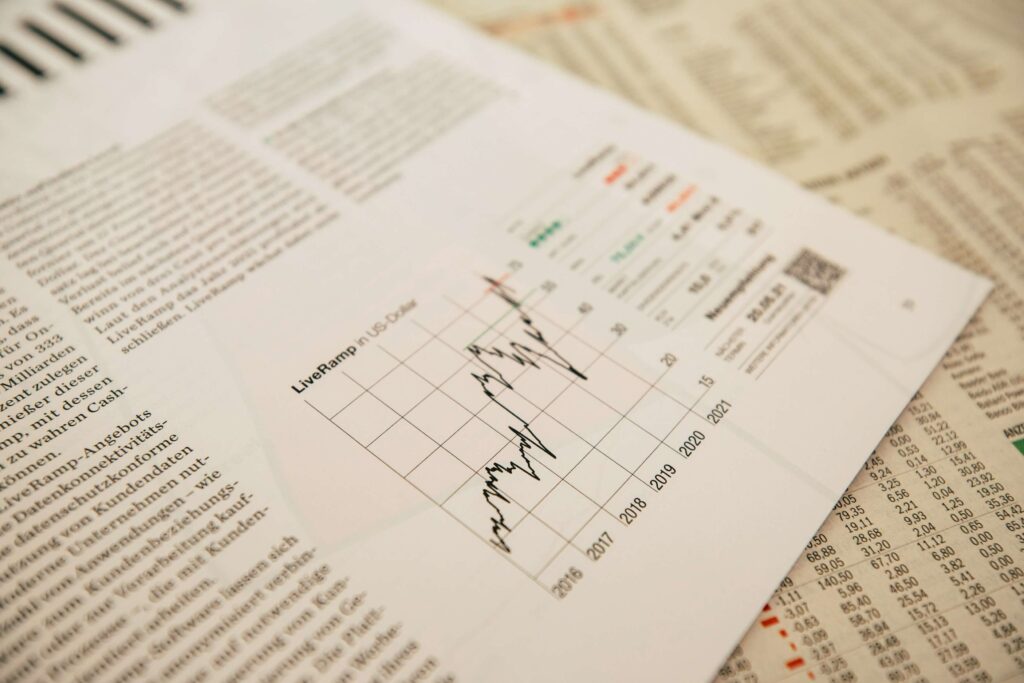
多くの方が「モチベーションを上げたい」と願うのは、究極的には「行動を起こしたいから」です。モチベーションが高まると、「目標に向けて手が動く」「やるべきことに集中できる」といったメリットが得られるため、その方法が知りたいと思うわけです。
一方で、一般的なモチベーション論や心理学では「やる気」や「意欲」といった内面的な状態に注目して「どうやって高めるか」を考えることが多いのに対し、行動分析学では「行動を取り巻く環境を整えることで、人の行動が変化する」と捉えます。
ここで大切なのは、そもそも私たちが「モチベーションを上げたい」と思う背景には、「実際に行動して、結果を得たい」という意図があるという点です。行動分析学は「内面を直接コントロールする」ことよりも、「行動が起こりやすくなる環境をデザインする」ことを重視します。これは、
「やる気」を高める=(結果として)行動を増やすこと
であれば、内面の気分に頼らずとも、行動を起こしやすい状況をつくってしまえば良いという考え方に基づいています。
なぜ行動分析学は「環境」に注目するのか?
行動分析学では、「人がある行動をとるかどうか」を大きく左右するのは、行動を取り巻く環境要因だと考えます。たとえば、
- 行動の合図(トリガー)
- 目に見えるところに道具を置いておくと、自然とやり始めるきっかけになる
- 行動しやすい仕組みの設計
- 邪魔なものを片付ける、必要なツールを使いやすくしておく
- 行動の結果として得られる報酬
- 「行動後にちょっとした楽しみや充実感が待っている」とわかると、取り掛かる抵抗が和らぐ
このように、やるべき行動自体が起こりやすい環境を整えることこそが、実質的に「モチベーション(やる気)」を高めることと同じ効果をもたらす、というのが行動分析学のアプローチです。
「やる気が出ない…」ときほど環境を見直す
多くの人は、「やる気がわかない」「どうしても手を動かせない」と悩んでいるときに、つい自分の内面を責めたり、やる気スイッチを探そうとしたりしがちです。しかし、行動分析学の視点に立つと、
「やる気が出ないときこそ、行動しやすい仕組みをつくるチャンス」
と捉えられます。たとえば、
- 机まわりを片づけて、作業の合図をわかりやすくする
- 時間を決めて“とりあえず○分だけやる”とハードルを下げる
- やり終えたあとに“小さなごほうび”を自分に与える
こうした“環境デザイン”によって、「モチベーション(=内面の感覚)」に頼らなくても、自然と行動を始められる状態をつくることができます。
なぜ行動分析学を活用することが大事なのか?

再現性が高い
行動分析学は、行動の前後にある環境や条件を整えていく科学的なアプローチを重視します。感情や根性論に頼らず、誰がやっても同じように成果が出やすい再現性を持っているのが強みです。
自己否定に陥らない
「モチベーションが湧かない=自分がダメだ」と思いがちですが、行動分析学的には「適切な環境が整っていないから行動につながらないだけ」と捉えます。内面を責めるより、環境や仕組みを調整すれば良いと考えられるため、自己否定から抜け出しやすいのです。
長期的な成果につながる
行動分析学で重視する「強化(報酬)」のしくみを使えば、小さな成功体験を積み重ねることで行動が徐々に定着していきます。一時的なやる気の爆発で終わるのではなく、継続的に成果を上げられる土台を作れるのが大きなメリットです。
行動分析学から考える「モチベーションを上げる方法」

前章まででお伝えしてきたとおり、行動分析学では「やる気を高める」こと自体をゴールにするのではなく、「行動を起こしやすくする」仕組みづくりに注目します。一方で、仕事やタスクの内容を見直し、自分にとって“楽しい・やりがいがある”状態(内発的動機)を育むことも、長期的なモチベーション維持には欠かせません。ここでは、環境を整えるアプローチをベースにしながら、自分の内発的動機づけを高める具体的な方法をご紹介します。
仕事そのものを「楽しい」「やりがいがある」と思えるように再設計する
「これをやるのが楽しみだ」「もっと続けたい」という感覚は、行動を起こし続ける“原動力”になります。仕事の設計段階から「楽しさ」「やりがい」を重視すれば、結果としてモチベーションが安定しやすくなるのです。
- 自分の好き・得意を活かす仕事に集中する
まずは、「どんな作業なら手をつけるのが億劫にならないか」を洗い出してみましょう。自分が得意で、やりがいを感じるタスクを優先的に増やすことで、自然と“行動を起こそう”という気持ちが高まりやすくなります。 - 苦手を人に任せる/思い切ってやめる
逆に、取り掛かりたくない・苦手意識が強い仕事は、外注やアシスタントの採用などで手放す選択肢も検討してみましょう。自分一人で抱え込まず、組織づくりやチームワークを活かすことで、ストレス要因を減らし、モチベーションを下げる要素をなくせます。
「やりたくない仕事」を、好きな環境にセットする
仕事やタスクそのものが楽しめなくても、取り巻く環境に“プラス要素”を与えることで取り掛かりをスムーズにします。
- 環境を変える/場所を変える
「普段のオフィスや自宅では気が乗らない仕事」を、あえてカフェやコワーキングスペース、あるいはワーケーション先で片付けるのも一つの方法です。場所が変わるだけで気分がリフレッシュし、取り掛かるハードルを下げる効果があります。 - 小さな楽しみと組み合わせる
「やりたくない仕事」に取り組むときほど、好きな音楽をかける、好きな飲み物やおやつを用意するなど、“作業中の楽しみ”をトッピングしてみましょう。「やりたくないタスク+好きなもの」がセットになると、行動への抵抗感が緩和されやすくなります。
環境 × 内発的動機の相乗効果を狙う
ここまで紹介したように、行動しやすい環境づくりと仕事自体を“やっていて楽しい”状態に変えていく工夫は、どちらか一方に偏るよりも、組み合わせることでより大きな効果を生みます。
- 基本は環境づくり
- 「目に見えるトリガーを置く」「短時間でも行動できる仕組みを用意する」「やったらすぐ報酬を得られるようにする」など
- 仕事の中身を“自分が楽しめる形”に再設計
- 得意な部分に集中し、苦手な部分は他者に任せる、環境を変えて気分を変えるなど
この2つを同時に進めると、「行動が起こりやすい」うえに「行動すること自体が楽しい」という状態になり、モチベーションの上がり下がりに左右されにくい安定したパフォーマンスにつながります。
長期的にモチベーションを保つためのポイント

モチベーションの波を前提にする
人間のやる気は、上がったり下がったりする波があるのが普通です。モチベーションの波が低いときは「自分はダメだ」と考えるのではなく、「こういう時期もある」と受け止めることが大切。波が上がってきたときにしっかりエンジンをかける、波が低いときはペースダウンして疲れを癒す、という長期的な視点を持ちましょう。
自分がモチベーションが上がるポイントを理解する
「他の人には効果的な方法でも、自分には当てはまらない」というケースはよくあります。自分が何にワクワクし、何に報酬を感じるのかをしっかり把握することは、長期的にモチベーションを維持するうえで非常に重要です。外部の評価や金銭的報酬が嬉しいタイプもいれば、自己成長や達成感に喜びを感じるタイプもいます。まずは自分を客観的に分析してみましょう。
小さな成功体験を積み重ねる仕組みを継続する
大きなゴールだけを見ていると挫折しやすくなります。短期的な目標を細かく設定し、小さな達成を繰り返すことで報酬を得られるチャンスを増やすのがコツです。
定期的に振り返りをする
モチベーションの波や行動の成果を、一定のサイクルで振り返ってみましょう。「どうして調子が良かったのか」「なぜ落ち込んでしまったのか」を客観的に分析することで、次の行動計画に活かせます。
モチベーションは「待つもの」ではなく「行動しながら高める」もの

「気持ちが上がらないと始められない」のではなく、始めてみるからモチベーションが高まるという逆の流れを意識しましょう。そのための“小さな一歩”を設定するのがカギです。
小さな一歩を踏み出すためには、モチベーションがなくても動ける仕組みづくりをする必要があります。どうしてもモチベーションが上がらないときこそ、「1分だけやる」「とにかく最初の一歩を踏み出す」など小さな行動をスタートするのがポイントです。モチベーションが低い状態でも動ける環境づくりをしておけば、波が低い時期に大きく後退するリスクを減らせます。
さらに詳しい方法はこちらの記事を見てみてください。
まとめ:環境をデザインし、行動からモチベーションを生み出そう
モチベーションは心の問題だけではなく、まわりの環境を整えることで生まれます。自分が楽しく働ける仕事を増やしたり、小さな目標を設定して達成感を味わう工夫こそが大切です。
「まず5分だけやってみる」「苦手な作業は好きなカフェで行う」など、シンプルな工夫を取り入れてみてください。行動を少しずつ積み重ねることで、モチベーションも自然と高まり、成果へとつながります。
経営者として、あなた自身とチームに合う環境を用意できれば、周りの人の力も引き出せるはずです。
一人でモチベーションを上げるのは難しいと感じたら…
行動の仕組みづくりや環境調整は、自分だけで考えると迷いやすく、途中で挫折することもあります。
そんなときは、専門家の力を借りるのも一つの手です。たとえば、行動分析の視点を取り入れたサポートでは、あなたの苦手を分析し、仕事や環境の工夫点を一緒に探せます。
「どうしてもモチベーションが保てない」「行動が続かない」と感じたら、こちらをぜひご覧ください。
一人ひとり異なる課題や状況に合わせて、より効果的な方法をご提案します。一緒に行動のサイクルをデザインし、目標達成に向けた行動を加速させましょう。