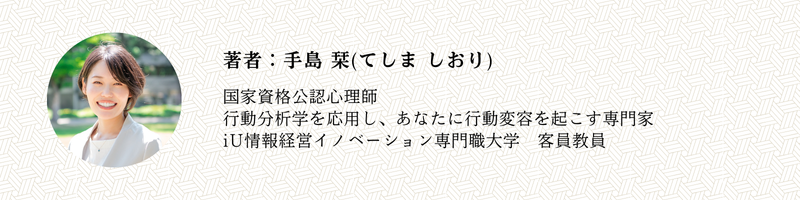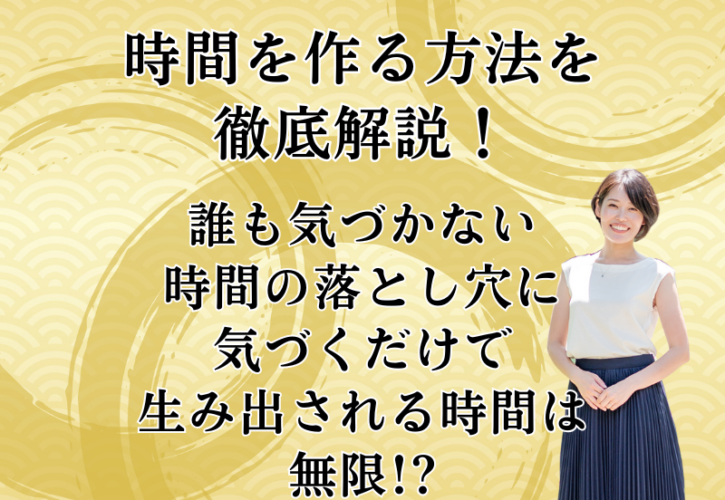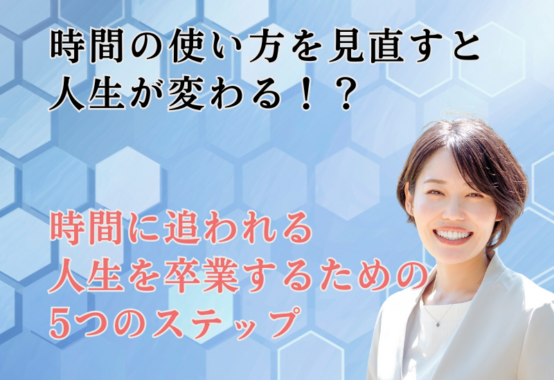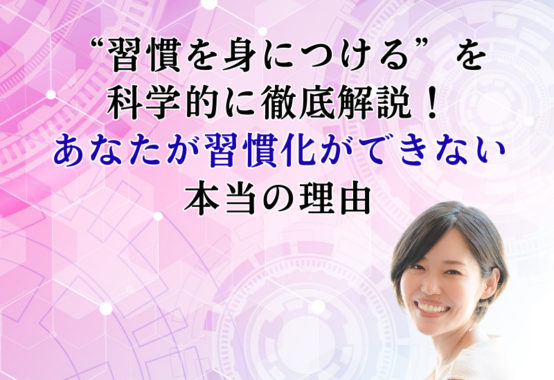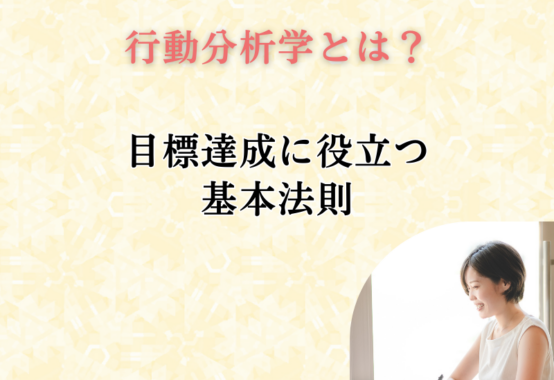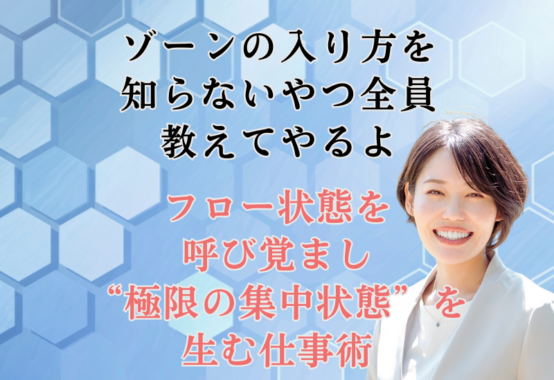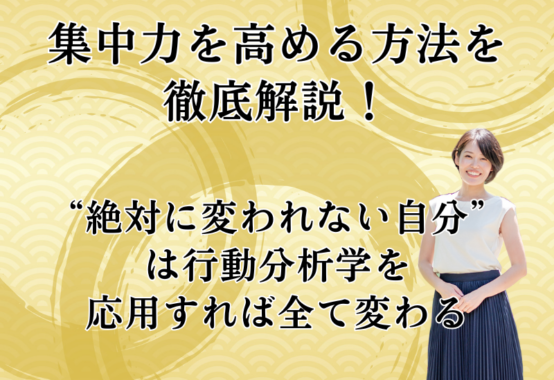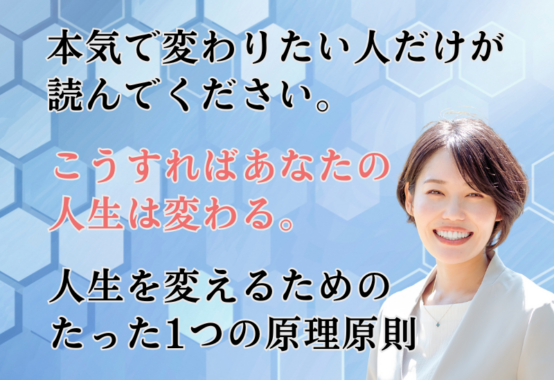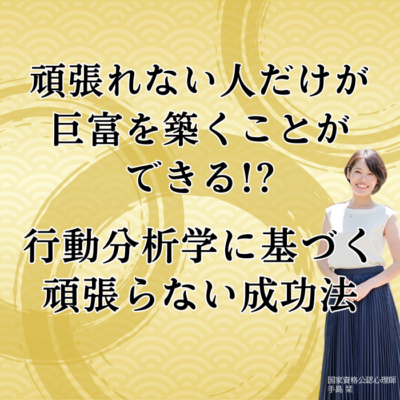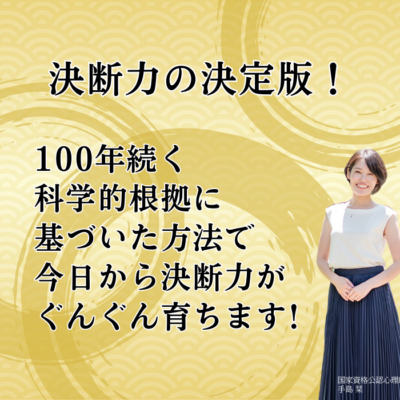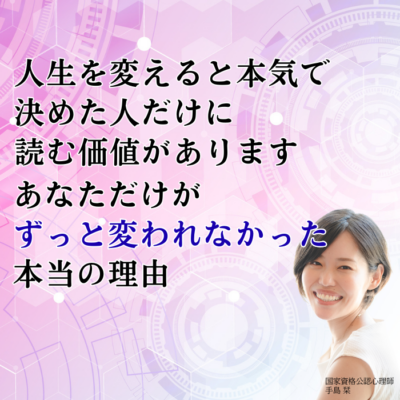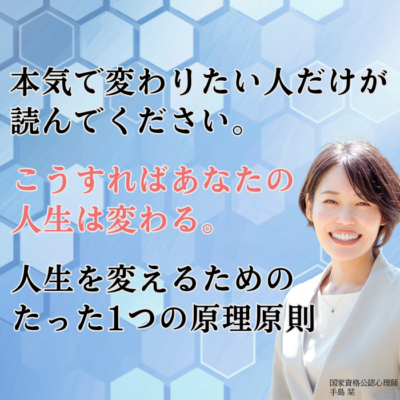こんにちは。行動分析学の専門家、手島栞です。目標を立てて行動をしても、いつも途中で挫折してしまう…。そんなお悩みを抱えている方に向けて、行動しやすくなるためのヒントをお伝えしています。
「このままじゃ、もう限界かもしれない」
頭ではそうわかっているのに、
気づけばまた、目の前の火消しに追われている。
本当は、未来のために時間を使いたい。
もっと仕組みを整えたいし、戦略に集中したい。
でも、「自分がやった方が早い」がまだ拭いきれず、
誰かの役に立っているという実感も、なかなか手放せない。
そんなふうに時間の構造に縛られたまま、
大事なことほど後回しになってしまう現状から、
そろそろ抜け出したいと思いませんか?
この記事では、「時間を作る方法」をただの効率化としてではなく、
時間が奪われている構造そのものをどう変えるかという視点から、
経営者だからこそ見落としがちな落とし穴と解決策を、徹底解説します。
読むことできっと、
「時間がない」の正体に気づき、
自分のために時間を生み出す行動へと、一歩を踏み出せるはずです。
時間を作ろうとしても、時間の問題は解決しない

「忙しいなら、まずは時間を作るべき」
そう考えて、タスクを整理し、会議を減らし、ルーティンを効率化する。
けれど、それでもまた気づけば時間が埋まり、余白は消えている…。
決してあなたのやり方が間違っているわけではありません。
むしろ多くの経営者が、同じ時間の落とし穴にハマっているのです。
空いたはずの時間が、なぜかすぐ埋まっていく理由
実は、「時間を作る」だけでは不十分なんです。
なぜなら、行動パターンや意思決定のクセ、人との関わり方がそのままなら、
空いたスペースには、また別の「つい手が伸びる仕事」や「反射的に優先順位を上げている仕事」が流れ込んでくるからです。
たとえば…
- 「この時間は集中しよう」と決めたのに、通知に反応してすぐ中断
- 誰かに頼めばいいのに、「あとで渡すのも面倒」で自分で処理
- 会議が1つキャンセルになった途端、その空きに別タスクを差し込んでしまう
時間を作ることに成功しても、行動構造が変わらなければ、結果は同じです。本当にやりたかったことに使える時間には、いつまで経っても届きません。
問題の本質は「時間不足」ではなく、「行動オーバー」
大事なのは、「どうやって時間を作るか?」ではなく、
「なぜ、いつも時間が埋まってしまうのか?」という問い直しです。
原因は、行動の多さそのものにあることがほとんど。
- 自分にしかできないと思い込み、任せられない
- 判断を保留したタスクをいつまでも抱え続ける
- 緊急性や相手の期待に過敏に反応してしまう
- 本当は不要な仕事を、習慣的に引き受けてしまう
こうした「無意識の行動」が積み重なることで、気づけばやることがオーバーフローしている状態…つまり、行動オーバーが起きているのです。
時間を奪っているのは「何をしているか気づいていない行動」
「時間がない」と感じているとき、その正体は多くの場合、
自覚のない行動に時間を取られていることにあります。
たとえば…
- 通知が鳴るたびに反射的にスマホを見る
- 頼まれたことを断れずにその場で引き受ける
- 少しのつもりが、SNSやメールチェックに15分
- 会議後、ぼんやりと切り替えられずに手が止まる
こうした行動は、「やっているつもり」も「休んでいるつもり」もなく、
ただ自然に起こっている。
でも、その積み重ねが、確実にあなたの貴重な時間を静かに削っているのです。
“時間がない”の正体:なぜ時間はいつの間にか消えていくのか?

「気づいたらもう夕方」「今日はあまり進まなかった」…そんなふうに、時間がいつの間にか消えていく感覚。
でも実は、時間は勝手に消えているわけではありません。すべて、あなた自身の「行動」として使われているのです。
私たちの24時間はすべて行動で埋まっている
あなたが「何もしていなかった」と感じていた時間。
思い返してみてください。
- 無意識に画面を眺めていた
- やるべきことを思い出して、頭の中で整理していた
- タスクの順番に迷って、手が止まっていた
こうした“小さな行動”の積み重ねが、気づかないうちにあなたの時間を埋めているのです。
ただ座っているように見えるときも、
ぼんやりしているように思える時間も、
実は、私たちはずっと「行動」し続けています。
ここで、ひとつポイントがあります。
行動分析学という学問では、たとえば「考える」「迷う」といった内側の動きも、
“私的な行動”としてしっかり扱われるんです。
私たちは、“行動していない時間”を持てない生き物である。
そう捉えてみると、「時間が足りない」と感じる理由も、少し見えてくるかもしれません。
時間はコントロールできない。でも、行動は変えられる
時間は増やせません。
1日は誰にとっても24時間──それは、どんなに優秀な経営者でも変えることができない事実です。
でも、希望はあります。
時間そのものは動かせなくても、
その時間を埋めているのは、自分の「行動」だからです。
つまり、時間を増やすことはできなくても、
自分の行動を変えることで時間を奪われないようにすることはできる。
行動を変えるのに役立つのが「行動分析学」です。行動分析学を活用することで、行動をコントロールできるようになります。
それだけで、未来の時間は取り戻せるのです。
“時間を作る”第一歩:やらないことを決める

「もっと時間がほしい」と思っても、時間を増やすことはできません。
だからこそ、時間を作るための第一歩はとてもシンプル。
やらないことを決めることです。
あなたの24時間を埋めている行動は?
やらないことを決めるために、
まずは、自分の1日がどんな行動でできているかを洗い出してみましょう。
ざっくりでも構いませんが、できるだけリアルに記録できると効果はぐっと高まります。
たとえばこんな方法があります。
- 朝に、今日の予定と実際にやったことをメモに残す
- 仕事の様子をスマホで撮影してあとから見返してみる
- タイムトラッキングアプリや、簡単な記録シートを使ってログを残す
少し面倒に感じるかもしれませんが、「自分がどんな行動で時間を使っているのか」を知ることが、行動改善の第一歩です。
すると、必ず気づきが生まれます。
「これ、本当に必要だったかな?」「もしかして、やらなくても困らないかも」…そんな小さな違和感が、次の行動につながっていきます。
やらない行動を決めて、余裕を生み出す
さて、記録を眺めてみてください。
そこに、こんな行動は紛れ込んでいないでしょうか?
- 他の人でもできたはずの作業を、自分でやっていた
- 頼まれて断れずに引き受けた、本当は必要のなかったお願い
- 無意識に繰り返すSNSチェックや情報収集
- 「考えなきゃ」と思っているけれど、実は止まっているだけの時間
こうした行動を見つけたら、そっと自分に問いかけてみてください。
「これは、本当に“今の自分”がやるべきこと?」
もし少しでも「いや、そうでもないかも」と感じたら、
その行動は、あなたの“やらないリスト”に加える候補です。
もちろん、すべてを一気にやめる必要はありません。
大切なのは、小さな「やめる」から始めること。
小さなやめるを積み重ねていくと、気づかぬうちにまとまった空き時間と、心のゆとりが生まれてきます。
そして、その浮いた時間はどうなるか?
戦略を練る時間に。
大切な意思決定に集中する時間に。
未来を形づくる、あなた自身のための時間に。
時間を「増やす」のではなく、「奪われないようにする」。
その起点となるのが、このやらないことを決めるという選択です。
時間の問題は“行動上の問題”:習慣を見直す必要性

「やらないことを決める」
これは、時間を取り戻すための第一歩として、とても効果的なアプローチです。
でも実際には、どうでしょうか?
「やめよう」と思ったのに、なぜか気づいたらまたやっている。そんな経験、ありませんか?
たとえば…
- 「SNSは昼と夜だけにしよう」と決めたのに、気づけば無意識に開いている
- 「これは他の人に任せよう」と思っていたのに、結局自分で処理してしまった
- 「次こそは断ろう」と思っていたのに、なぜかまた引き受けてしまった…
これらは、意志が弱いからでも、怠けているからでもありません。
実は、あなたのその行動がすでに“習慣”になっているからなのです。
「時間を作る」とは、行動習慣の再設計
時間を作るとは、単に予定の枠を空けることではありません。
本当に時間を取り戻すには、日々の「行動そのもの」を変えていく必要があります。
言い換えるなら…
- 今まで無意識に繰り返していた行動を、“意識してやめる”
- 新しく必要な行動を、“意識して取り入れる”
このように、行動を「削る・変える・強める」という調整が求められるのです。
そしてこれは、ただの“やる/やらない”の選別ではなく、習慣という仕組みそのものを見直すプロセスだと言えるでしょう。
習慣の力は強い。でも、設計すれば変えられる
習慣には、いくつかのやっかいな性質があります。
- 無意識でやっているため、自分では気づきにくい
- 「きっかけ(場所・時間・感情)」と「結果(安心感・達成感)」がセットになっている
- 一度繰り返されると、同じパターンに戻りやすい
つまり、やめたくても、気合いや根性だけではなかなか変えられないんです。
でも逆にいえば。
習慣の仕組みを理解できれば、
「なぜその行動をしてしまうのか?」→「どう設計すれば止められるか?」という視点で見直すことができます。
なぜやめられないのか?習慣が時間を奪い続けるメカニズム

「やらないと決めたのに、またやってしまった……」
「この行動はもう手放すって決めてたのに、気づいたら元通り」
これは、あなたの意志が弱いせいではありません。
その行動が、すでに“習慣”として、自動的に組み込まれているからです。
習慣とは「意識しなくても繰り返される行動」
習慣のすごいところは、わざわざ「やろう」と思わなくても、自然と体が動くこと。
そして同時に、それが厄介な点でもあります。
こんな特徴、心当たりはないでしょうか?
- 行動を始める「きっかけ」が固定されている(時間・場所・気分など)
- 考える前に、反射的に始まっている
- 報酬もやる気も関係なく、なぜか続いている
たとえば…
朝起きてスマホを開く。
集中が切れると、気づけばSNSを見ている。
会議前には、いつもコーヒーを飲む。
「断ろう」と思っていたのに、つい引き受けてしまう。
もはや選択しているというより、無意識のうちに動いてしまっている状態です。
習慣の一番の怖さは、「やっていることに気づきにくい」こと
これが時間を奪う最大の理由です。
行動しているという自覚がないまま、確実に時間が削られていく。
たとえば…
- スマホをちょっと見たつもりが、もう10分経っていた
- 「少し休憩」のつもりが、気づいたら次の行動に移れなくなっていた
- メールを確認しただけのつもりが、気がつけば30分も処理にかかっていた
どれも、「やる予定ですらなかった行動」が、知らないうちにあなたの時間を奪っていきます。
習慣を変えるなら、意志ではなく「仕組みごと見直す」
習慣は、気合や注意力だけで変えられるものではありません。
なぜなら、それは「意識の外側」で繰り返されている行動」だから。
本当に行動を変えたいなら、やるべきは次の2つです。
- 行動の始まりとなる“きっかけ”を断つ
- 自動的に繰り返されるパターンを分解し、再設計する
習慣とは、「気づいたときにはもう動いている」ような、自動プログラム。
だからこそ、そのプログラムを根本から書き換える必要があるのです。
時間が生み出せないときに試す“行動”の変え方

「行動を変えたい。でも、気づくと元に戻ってしまう」
そんなとき、頼りがちなのが“意志の力”。けれど、実はそれだけではなかなか変わらないのが人間の行動です。
ここでは、行動分析学の視点から、意志に頼らず行動を整える方法を2つの切り口でご紹介します。
行動分析学的アプローチ:環境調整
まず注目したいのは、「行動のきっかけ」になっている環境です。
意外かもしれませんが、私たちの行動の多くは、強い意志ではなく、環境によって自然に引き出されているんです。
たとえば…
- 通知音が鳴ると、ついスマホを手に取ってしまう
- SNSのタブが開きっぱなしだと、ついクリックしてしまう
- 頼まれごとの多い場所にいると、断れずに引き受けてしまう
こうした状況では、やる気や性格よりも、「環境」が行動を後押ししている状態です。
だからこそ、行動を変えるには、まず環境に手を入れることが効果的。
✅ たとえば、こんな工夫ができます:
- スマホの通知をオフにする/視界から遠ざける
→ 無意識に手が伸びるのを防ぐ - SNSやメールをチェックする時間・回数を決める
→ 「ついでに」の自動行動をルールで遮断 - 作業の一部を人に任せる/ツールで自動化する
→ 自分の手を離してもいい業務を見極める
「Slackは14時以降しか開かない」「メール確認は1日3回まで」と“時間で区切るルール”もおすすめです。
また、よくあるのが「これは自分がやらないと回らない」という思い込み。
本当にそうでしょうか?
少し視点を変えてみると、他の人の力やツールの活用で手放せる仕事も意外とあるものです。
結果を変えれば、行動に意識が戻る
もうひとつの視点は、「行動の結果」に注目すること。
人の行動は、そのあとに何が起きるか(結果)によって強化されたり、減ったりします。
たとえば、
SNSを見たら少し気がまぎれてラクになる。
タスクを後回しにしたら、とりあえずその場が落ち着いた。
こうした「小さなご褒美」が、無意識に行動を繰り返させています。
だからこそ、結果を意識的に「設計し直す」ことがカギになるんです。
✅ こんな仕組みが効果的です:
- SNSを見てしまったらペナルティ(小額課金、記録を共有など)
- 集中できたらご褒美タイム(好きなお菓子やYouTubeを解禁)
- 行動ログをチームや友人と共有し、「見られている仕組み」をつくる
こうした工夫は、「自動でやっていた行動にストッパーをかける」ための補助輪のようなもの。
報酬や罰という“結果”を調整することで、行動に対する意識が戻ってくるのです。
習慣は、「設計すれば変えられる」
行動というのは、「きっかけ(環境)」と「結果(報酬・ペナルティ)」の組み合わせによって強化されています。
だから、我慢したり頑張ったりするのではなく、
そもそも起きにくく、続きやすいように「仕組みで整える」ことが、最も現実的なアプローチです。
この考え方は、「習慣を変えたい」「いつものパターンをリセットしたい」ときにも、そっくりそのまま使えます。
「意志の問題」ではなく、「仕組みの問題」。
そう捉えるだけで、行動の変化は一気に現実味を帯びてきます。
習慣を変えるための具体的ステップについては、こちらの記事でさらに詳しくご紹介しています。
まとめ:時間を作る方法は、行動を変えることがすべてのカギ

行動が変われば、時間の流れも変わります。
そして、時間の使い方が変わることで、
仕事の成果も、チームの動きも、そしてあなた自身のあり方さえも変わっていきます。
このコラムは、「もっと頑張ろう」と自分を追い込むためのものではありません。
目指しているのは、“頑張らなくても自然と回る仕組み”をつくること。
そのための、静かで確かな一歩を、あなたと一緒に踏み出すことです。
大事なのは、自分を責めることではなく、
時間と行動の「設計者」になるという視点を持つこと。
それこそが、未来に集中できるあなたをつくる、ほんとうのスタートラインです。
専門家に相談することの重要性:行動分析学で時間を取り戻す
どれだけ工夫しても、「なぜか時間が足りない」が続いてしまう。
そんなときは、一人で抱え込まず、第三者の視点を取り入れることも大切です。
行動のクセや無意識の習慣は、自分ではなかなか気づけないもの。
だからこそ、行動分析学の専門家が伴走しながら、
あなたの行動と時間の使い方を棚卸しして、根本から“回る仕組み”を一緒に整えていきます。
「変えたいのに、変えられない」
そのもどかしさを、科学と仕組みで超えていきましょう。
▶ サービスの詳細はこちらから