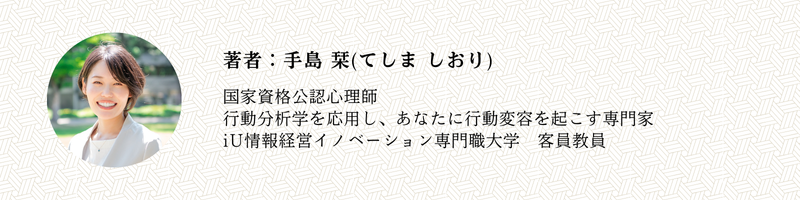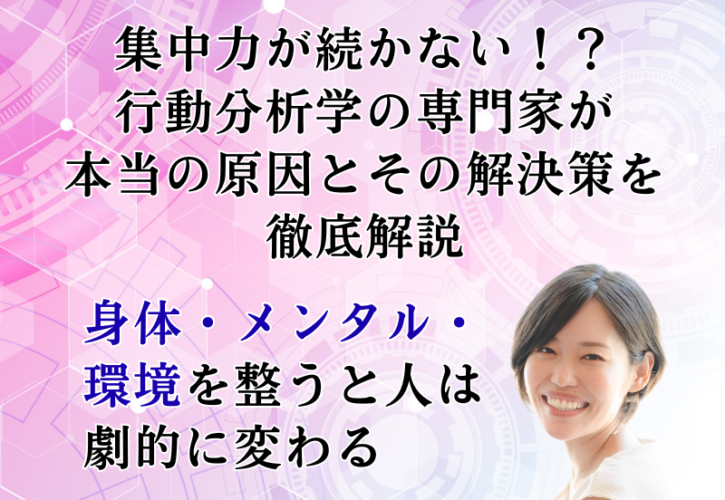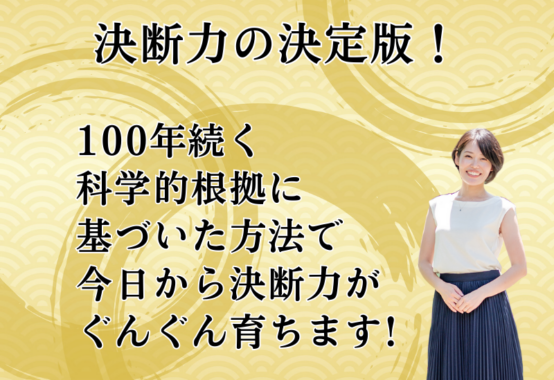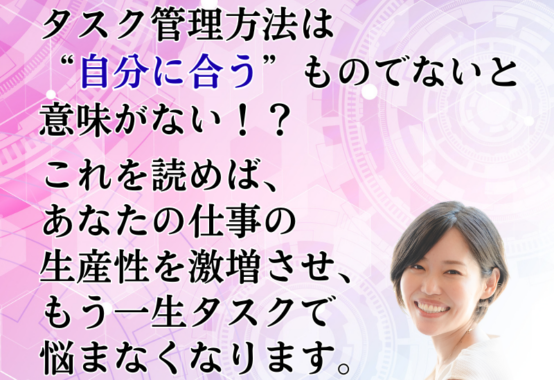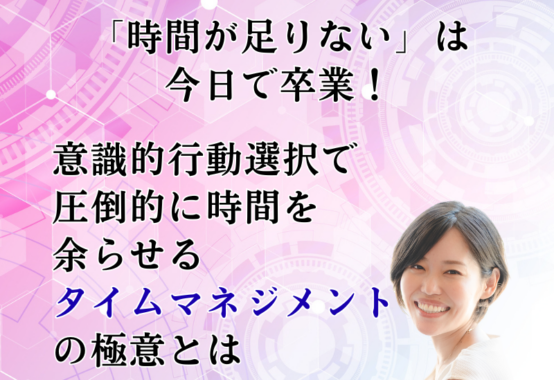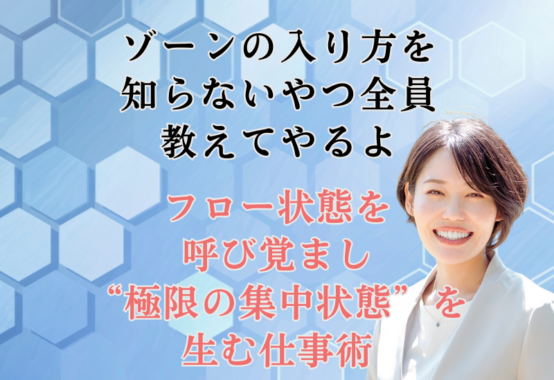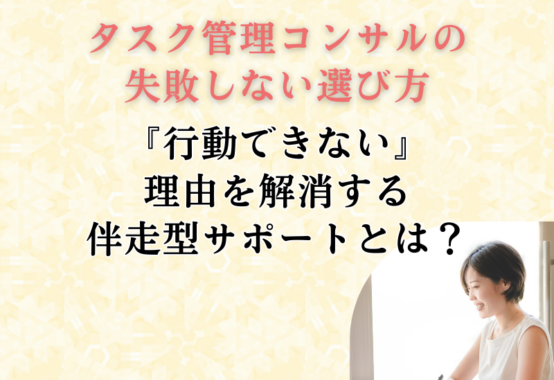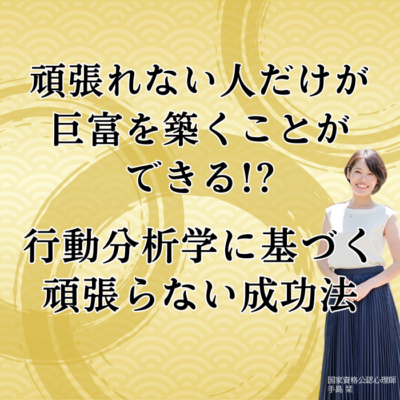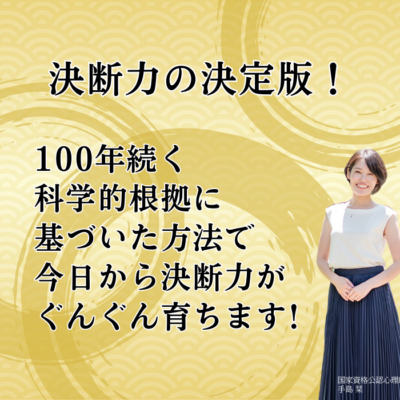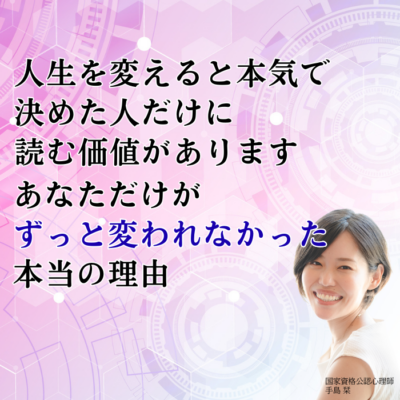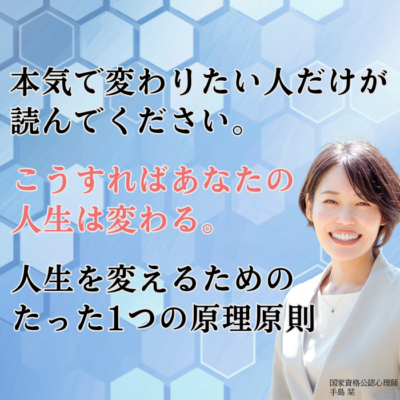こんにちは。行動分析学の専門家、手島栞です。目標を立てて行動をしても、いつも途中で挫折してしまう…。そんなお悩みを抱えている方に向けて、行動しやすくなるためのヒントをお伝えしています。
「集中しよう」と思っているのに、気がついたら別のことを考えていた。何も進まないまま一日が終わって、自己嫌悪…。
そんな日々に、少し疲れていませんか?
でも安心してください。
集中力が続かないのは、意志の弱さのせいではありません。
本当の原因は、もっと別のところにあります。
この記事では、行動分析学の視点から、
「なぜ集中できないのか」
「どうすれば集中を取り戻せるのか」
を、わかりやすくお伝えしていきます。
ポイントは、根性や気合ではなく、環境と行動を整えること。
それだけで、驚くほど集中力は変わっていきます。
「まとまった時間が取れないと集中できない」
「最近、自分の思考力に不安がある」
そんなふうに感じているあなたにこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
今こそ、「がんばらなくても集中できる自分」へと変われるタイミングかもしれません。
「集中力が続かない」人の特徴とよくある傾向
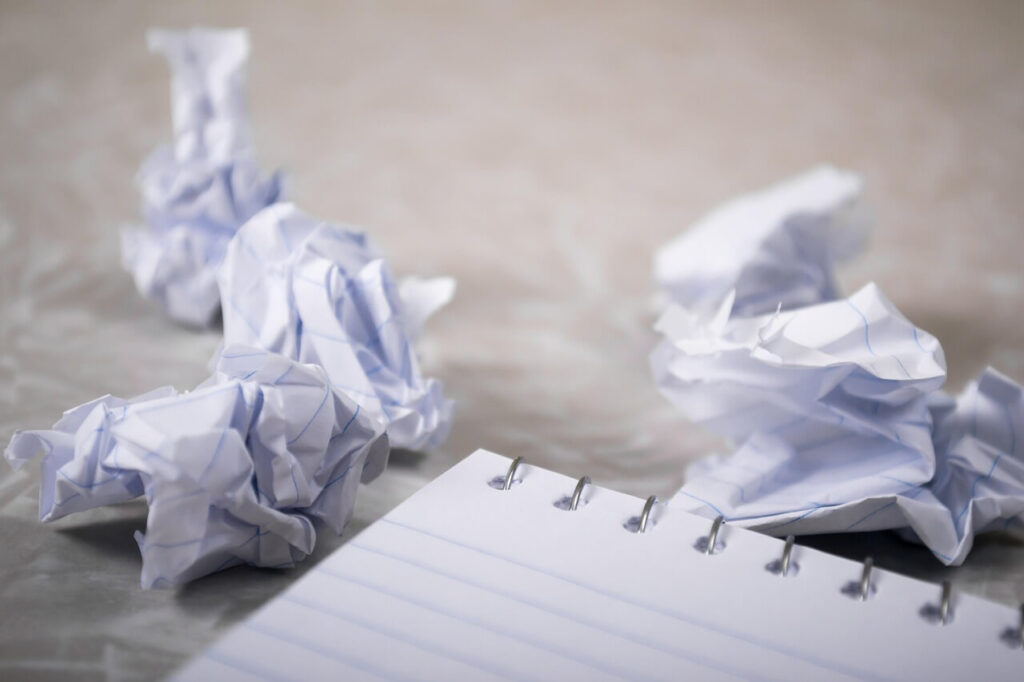
まずは、よくある「集中が続かない人のリアルな声」をご紹介します。心当たりはありませんか?
- 15分ごとにSlackやLINEが飛んできて、思考が切れる瞬間が一日中ある
- アイデア出しに取りかかりたいのに、細かい確認依頼や決済タスクで一日が埋まる
- 考え事をしていても、「他のことに切り替えなきゃ」という声が常に脳内で鳴っている
- 一つのタスクに集中していると、「他のことが遅れてる気がして不安になる」
- 誰かが困っていないかが常に気になり、集中より周囲の進捗確認を優先してしまう
- 「次の一手を考えたい」と思ってPCを開くが、いつの間にか違うことをしている
- タスクをこなすとやった感はあるのに、肝心の思考・意思決定業務が全く進んでいない
- 「今日は集中できるはず」と思っても、最初の5分で集中できなかったときの絶望感が大きすぎる
- 空白時間ができると、無意識にスマホを取り出してしまい、何を見たか覚えていない
こうした状態は、よくある「気のせい」や「甘え」ではありません。
脳の仕組み、置かれている環境、そしてタスク設計が影響し合って起きている、自然な反応です。
つまり、これにはちゃんとした「理由」があります。
そしてその原因さえ特定できれば、正しい対処で変えていくことができるのです。
主な原因を知ろう|身体・メンタル・環境・タスク別の要因

集中力が続かない原因は、一つではありません。
身体・環境・認知・行動。さまざまな要素が絡み合い、今の「集中できない状態」を生み出しています。
ここでは、集中力が続かない人に共通して見られやすい特徴や傾向を、4つの視点から整理してご紹介します。
1. 身体的な疲れやメンタルの問題を抱えている
まず最初に見直したいのが、「心と身体のコンディション」です。
疲労がたまっていたり、睡眠が不足していたりする状態では、当然ながら脳のパフォーマンスは低下します。
また、強いストレス、不安、あるいはうつの傾向がある場合には、意欲や集中力に直接的な影響が出てきます。
どれだけやる気があっても、身体やメンタルという土台が整っていなければ、集中を保つのは難しいのです。
2. 環境に左右されやすい
どこで、どんな環境で作業するか。これも集中力に大きく関わってきます。
たとえば、
・部屋が散らかっている
・スマホの通知が頻繁に入る
・音や匂いが気になる
といった物理的な刺激は、注意をあちこちに分散させてしまいます。
特にADHD傾向のある方は、外部刺激に過敏な傾向があり、注意がそれやすいのが特徴です。
また、「静かな場所で集中できる人」もいれば、「適度にざわざわした環境の方が落ち着く」という人もいます。
つまり、自分に合わない環境で無理に作業していることが、集中力を奪っている可能性があるのです。
3. 目的意識が薄い、やるべきことが不明瞭
「この作業、何のためにやってるんだっけ?」
そんなふうに目的があいまいなままだと、集中力はグッと下がります。
人間の脳は、「意味のあるもの」には自然と注意を向けます。逆に、意味を見いだせないものには集中しづらい構造になっているのです。
つまり、目標がぼんやりしていたり、「なぜやるのか」が自分の中で腑に落ちていないと、集中できないのは当然のこと。
集中の土台には、納得感や目的意識が欠かせません。
4. 仕事やタスクが多すぎる・難易度が合っていない
やることが山ほどあると、脳は常にフル回転状態に。
「あれもやらなきゃ、これもある」と焦る気持ちが強くなり、目の前の作業に集中しづらくなります。
また、
- 難しすぎるタスク →「自分には無理かも」と感じて脱線してしまう
- 簡単すぎるタスク →退屈して注意が散漫になってしまう
というように、タスクの難易度も集中力に大きく影響します。
集中し続けるには、ちょうどよい負荷と余白のある設計が大切です。
仕事のボリュームや内容のバランスが崩れていると、それだけで集中が妨げられてしまいます。
あなたの集中力が続かない原因を探る方法

「集中力を高めたい」と思ったとき、すぐに対策を講じるのも一つの方法ですが、
それ以上に大切なのは、まず「なぜ自分は集中できないのか?」を知ることです。
集中力が続かない理由は、前章でお伝えした通り、身体・メンタル・環境・タスク設計など、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。
だからこそ、いきなり「正解」を求めるのではなく、仮説を立てて検証するという柔軟な姿勢が、集中力を育てる第一歩になります。
①「どのシーンで集中が切れているのか」を振り返ってみる
まずやってみてほしいのは、集中が途切れたタイミングや場面を思い出してみましょう。
たとえば、こんなシーンがありませんか?
- 朝イチの時間帯に、なぜか頭が働かない
- 15時以降になると、どうしても眠気が出てくる
- 難しいタスクを始めたとたん、手が止まる
- 周囲のざわめきが気になって、意識がそちらへ行ってしまう
- 気がかりなメッセージを見た直後、急に集中できなくなった
こうした具体的なシーンを振り返ることで、集中が切れやすいパターンや傾向が、少しずつ見えてきます。
② チェックリストを使って、自分を観察してみる
振り返りを習慣化するためには、簡単なチェックリストを使うのもおすすめです。
たとえば、1日の終わりに以下のような項目をざっくりメモしてみましょう
- 今日、集中できた時間帯はいつだった?
- 疲れや眠気はあった? 睡眠時間は十分だった?
- 作業環境(音、気温、スマホ通知など)はどうだった?
- タスクの種類や難しさは?
- 気分やモチベーションの波は?
記録することで、頭の中だけでは気づけなかったことが可視化されます。
主観に頼らず、自分を客観的に見られるようになるのです。
無理にすべてを解明しようとしなくていいのです。
まずは、できる範囲で意識的に、自分を観察するところから始めてみましょう。
具体的な解決策①|身体・メンタル面の整え方

集中力が続かない原因を見直す中で、
「もしかして、自分は身体や心が整っていないのかも…」と感じた方もいるかもしれません。
集中力は、「意志の力」でなんとかするものではありません。
まずは、脳が本来の力を発揮できるコンディションを整えることが大切です。
この章では、身体・食事・メンタルの3つの観点から、集中を支える具体的な整え方をご紹介します。
疲労・睡眠不足対策
疲労や睡眠不足は、集中力の天敵です。
「まだ大丈夫」と思って無理を重ねるうちに、脳のパフォーマンスはどんどん低下していきます。
🔸睡眠時間や質にこだわる
必要な睡眠時間は人によって異なります。
まずは「翌日に疲れが残らない睡眠時間」を自分の基準として見つけて、できるだけ安定して確保することが第一歩です。
あわせて、睡眠の質にも注目を。スマートウォッチなどで睡眠の質を可視化できる時代です。質が低い場合、枕やマットレス、部屋の明るさ・室温などを見直すだけで、眠りの深さが変わることもあります。
「布団に入ってもなかなか眠れない」「夜中に何度も目が覚める」など違和感があるときは、睡眠障害の可能性も視野に入れて、医療機関に相談することをおすすめします。
🔸日中の眠気には仮眠を活用
午後になるとどうしても眠くなる、という方には、15〜20分程度の仮眠がおすすめです。
眠気対策には、シンプルに寝ることが一番効果的だと言われています。
「寝すぎてしまうのが不安…」という場合は、昼寝のあとにオンライン会議を予定するなど、起きる“きっかけ”を先に作っておく工夫も効果的です。
🔸こまめな休憩と軽いストレッチ
長時間座りっぱなしの状態は、体だけでなく脳にも負担がかかります。
1時間に一度は席を立ち、肩を回す・屈伸する・首を回すといった軽いストレッチを取り入れてみましょう。
画面をずっと見続けている方は、ふと窓の外を見て遠くに視線を移すだけでも効果的。
脳と目の疲労感がリセットされ、集中力が戻りやすくなります。
🔸軽い運動を日常に取り入れる
運動は、「脳のスイッチを入れる最強の方法」と言っても過言ではありません。
とはいえ、ランニングやジム通いなど、ハードなものを続ける必要はありません。
たとえば…
- 通勤時にひと駅手前で降りて歩く
- 朝にラジオ体操をする
- エスカレーターではなく階段を使う
- 買い物に歩いて行く
といった「生活に溶け込む運動」を意識すると、自然に続けやすくなります。
実際、継続的な軽運動が脳の血流を改善し、注意力や集中力の向上に寄与することは多くの研究でも報告されています。
栄養バランスと空腹・満腹対策
集中力は、何を食べるか・どれくらい食べるかにも大きく左右されます。
脳のエネルギー源はブドウ糖ですが、血糖値が急上昇・急降下すると、かえって集中が乱れる原因に。
また、空腹や満腹といった身体の感覚が不安定な状態も、脳のリソースを密かに奪っています。
🔸 食事の内容を見直す|「軽め・バランス重視」が集中を支える
脂っこい揚げ物や高脂質なメニューは、消化にエネルギーを使うため、食後に眠くなりやすいです。
一方で糖質が少なすぎると、脳の燃料が不足し、集中力が低下することも。
大切なのは、「適度な糖質」と「たんぱく質・野菜」のバランスの良い食事です。
例として、白米は少なめにして、鶏むね肉や野菜を中心にした定食などが◎。
🔸 空腹・満腹を避ける|“ちょうどよい満足感”が脳を守る
強い空腹感があると、頭の中は「早く食べたい」でいっぱいになります。
逆に満腹状態では、血流が消化に集中してしまい、眠気を引き起こす原因に。
「ちょっとお腹すいたな」くらいのタイミングで、ナッツ・チーズ・ヨーグルトなどをつまむのがおすすめ。
これらは血糖値の変動がゆるやかで、集中の維持にもつながります。
🔸 水分補給を忘れずに|脱水は“気づかぬ集中力低下”の原因に
軽度の脱水でも、注意力・記憶力・判断力が落ちることがわかっています。
のどが渇いていなくても、こまめな水分補給を意識しましょう。
特にコーヒーや緑茶をよく飲む方は要注意。
カフェインには利尿作用があるため、水や麦茶などでバランスを取ることが大切です。
メンタルのケア
集中力は、心の状態にも大きく影響されます。
イライラ、不安、焦りといった感情が渦巻いていると、思考は浅くなり、集中力はすぐに奪われてしまいます。
実は「集中できない」のは、「気が散っている」からではなく、
「気が晴れていない」からなのかもしれません。
🔸 まずは“今の自分”に気づくことから
集中が続かないとき、頭の片隅でこんなことが引っかかっていませんか?
- 人間関係のモヤモヤ
- 将来への漠然とした不安
- タスクが遅れていることへの自責感
これらの感情の渋滞が、知らないうちに脳の作業スペースを埋めてしまっています。
まずは、「自分はいま、何にとらわれているのか?」を言葉にしてみましょう。
それだけでも、脳内の負荷は少し軽くなります。
🔸 ストレスをリセットするためのリラックス習慣を持つ
集中力を取り戻すには、“切り替える時間”が必要です。
短時間でもOK。心と身体をゆるめるリセット習慣を持つようにしましょう。
おすすめは、
- 深呼吸や1分間のマインドフルネス
- アロマなど香りの力で五感を整える
- 軽い散歩、家事などの単純作業
- ぼーっとする、音楽を聴くなど「思考しない時間」
これらは交感神経から副交感神経へと切り替えるスイッチになり、脳の余白を取り戻してくれます。
🔸 言語化や相談も、脳内スペースをつくる手段
悩みや感情を頭の中だけで処理しようとすると、脳の作業メモリが圧迫されてしまいます。
まるで、タブを開きすぎたパソコンが重くなるような状態です。
そんなときは…
- ノートに書き出す
- 誰かに話す
といった「外に出す」行動がとても有効です。
もし感情が重すぎると感じたら、心理の専門家などに相談することも前向きな選択肢です。
具体的な解決策②|環境要因の改善

集中力が続かないとき、
「意志が足りないのかな」「気合が必要なんだ」と考えてしまいがちですが、
実は意外な盲点があるのをご存じでしょうか?
それは、「環境」からの影響です。
集中は、心の状態だけでは成り立ちません。
視界に映るもの、周囲の音、部屋の温度や匂いなど、五感を通じた外部刺激が、知らず知らずのうちに集中を妨げているのです。
この章では、環境を整えることで集中を高めるための具体的な工夫をご紹介します。
🔸 作業スペースの整理整頓
視界に入る情報が多いと、脳は無意識に刺激を受け、注意が分散してしまいます。
机の上は、「今使うものだけ」を手元に置き、それ以外は引き出しなどに収納しましょう。
また、「必要なときに道具が見つからない」状態も、集中力を断ち切る原因に。
よく使う資料は手が届く位置に、滅多に使わないものは動線の外へ。
さらに、PC内の作業環境も忘れずに。
デスクトップが散らかっていたり、ファイルが見つからなかったりするだけで、集中力は大きく落ちてしまいます。
物理空間とデジタル空間、両方の“整え”が、思考の流れを守る鍵です。
🔸 スマホ・通知の管理
スマホの通知音、バナー、バイブレーション…。
たとえ見なくても、それだけで脳は分断されてしまいます。
実際、「スマホが机の上にあるだけで集中が切れる」という研究結果もあるほどです。
- 視界に入らない場所へ
- 「おやすみモード」や「機内モード」で通知を遮断
- 通知設定を「本当に必要なものだけ」に厳選
- チャットやメールは「○時にまとめて見る」と決めておく
これは意志で我慢するのではなく、環境の力で気が散る要因を遠ざける工夫です。
🔸 音・匂い・室温などの調整
「無音すぎて落ち着かない」
「ちょっと寒くてそわそわする」
そんな微妙な違和感も、積もれば集中力を奪う大きな要因に。
人によって好みはありますが、集中を助けるための共通ポイントは次のようなものです。
- 無音が苦手な人は、ホワイトノイズ・自然音・BGM(歌詞なし)を流す
- 空気がこもっているときは、換気やサーキュレーターで循環させる
- 気分を切り替えたいときは、お気に入りの香り(アロマなど)を使う
- 室温は22〜25℃が、脳のパフォーマンスを最も高めるとされています
「自然と集中できる」環境は、つくることができます。
🔸 周囲の人とのコミュニケーション
「今ちょうど集中してたのに…」
話しかけられて思考が途切れると、イライラしたり、戻るのに時間がかかったり。とくにオフィスや在宅ワークでは、周囲との関わりも無視できない要素です。
- あらかじめ「話しかけOK/NGタイム」を周囲と共有する
- ノイズキャンセリングイヤホンやアイコンタクトで“集中中”をさりげなく伝える
- 集中タイムが確保できないときは、カフェ・図書館・個室ブースを一時的に活用するのも◎
「話しかけられる=悪」ではありません。
集中のための「境界」を上手につくることがポイントです。
具体的な解決策③|タスクへの向き合い方を変える

集中力が続かないとき、
その背景にあるのは「タスクそのものへの向き合い方」かもしれません。
やることが曖昧だったり、重たすぎたり、逆に退屈だったり…。
そんなとき、脳は別の刺激に注意を向けてしまい、集中を保てなくなるのです。
ここでは、タスクの設計と取り組み方を見直すことで集中力を高める方法をご紹介します。
🔸 タスクを細分化する
集中できないタスクの多くは、全体が大きすぎて最初の一歩が見えないことが原因です。
たとえば、「資料をつくる」という曖昧なタスクは、
「構成をつくる → 過去データを集める → 骨子をつくる…」など、行動レベルに分解してみましょう。
小さなステップにすればするほど、「これならできそう」と感じられ、行動のハードルが下がります。
逆に、簡単すぎるタスクに集中できない場合は、あえてゲーム化などの工夫を加えるのも有効です。
- タイマーを使って早く終わらせる「タイムアタック化」
- 仕上がりにひと手間加えて、完成度への満足感を高める
こうした適度な負荷や意味づけが、集中の持続に繋がります。
🔸 ゴール設定を明確にする
目的がぼんやりしたままでは、集中できなくなってしまいます。
私たちは「意味のあること」には自然と注意を向けますが、「意味が曖昧なもの」には注意を保ちづらい性質があるからです。
- 「この作業は何のため?誰の役に立つ?どこに繋がる?」を言語化しておく
- 「自分はこのタスクにどう向き合いたいか」も併せて考える
目的が明確になるだけで、作業への納得感が生まれます。
その納得感が、自然な集中とモチベーションを引き出すスイッチになるのです。
🔸 優先順位とスケジュール管理
集中できないとき、多くの人の頭の中では“やることリスト”が同時に回っています。
あれもこれも思い浮かんで、どれにも集中できない──そんな経験、ありませんか?
だからこそ必要なのが、「今、やること」と「今はやらないこと」を明確に分ける」工夫です。
- タスクを緊急度・重要度で分類し、優先順位をつける(例:アイゼンハワーマトリクス)
- あえて「今日はやらないことリスト」をつくる
- 予定が詰まりそうな日は、バッファ(予備時間)をあらかじめスケジュールに入れておく
やることが明確で、時間にも余白がある…。
それだけで、脳は今に集中しやすくなり、思考のキレが戻ってきます。
短期的な対策ではなく“長期的に機能する集中力”を手に入れるには
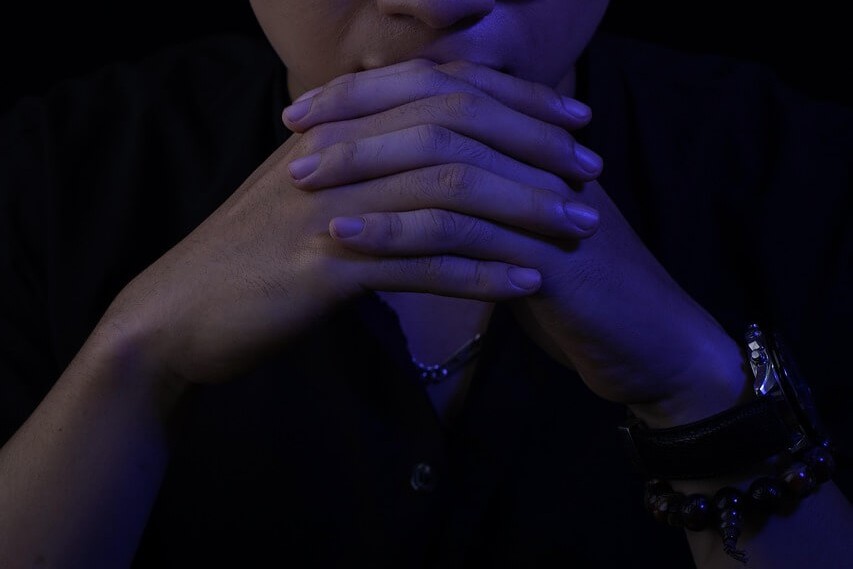
「集中力が欲しい」と思ったとき、
つい頼りたくなるのは、即効性のある対策かもしれません。
栄養ドリンクやカフェインを使って一気に進める方法も、たしかに有効です。
ただ、それらはあくまで短期的なブーストにすぎません。
その場しのぎの工夫だけでは、集中を再現したり、継続したりするのは難しいのです。
集中力は「習慣」とセットで育てるもの
集中力は、意志の力だけでどうにかなるものではありません。
本当に必要なのは、集中しやすい状態を「当たり前」にしておく仕組みを持つことです。
これまでご紹介してきた、身体・メンタル・環境・タスク設計の工夫も、
一度だけ試して終わりではなく、日常の中で使いこなしていくことが大切です。
たとえば…
- 寝不足の日は、昼寝で脳をリセットする
- 集中できないときは、環境を切り替えるクセをつける
- タスクが重たければ、無意識に分解できるパターンを持っておく
- 1日の中で“思考の時間”をあらかじめ確保しておく
こうした行動が習慣として根づいてくると、集中力は“特別なもの”ではなく、
自然と戻ってくるものへと変わっていきます。
とはいえ、習慣化にはちょっとした工夫とコツも必要です。
習慣づくりの詳しい方法については、こちらの記事でご紹介しています。
“自分だけの集中スタイル”を見つけよう
集中の型は、人によってまったく違います。
大切なのは、「誰かがやっている方法」ではなく、「自分の特性に合う方法」を見つけること。
- 朝のほうが思考タスクに向いている人もいれば、夕方に集中しやすい人もいます
- 無音が落ち着く人もいれば、ホワイトノイズやBGMがあった方が集中しやすい人もいます
- 一人で没頭できる人もいれば、誰かと“見られながら”の方が集中できる人もいます
だからこそ、「自分はどうすれば集中できるのか?」を日々観察してみること。
その積み重ねが、自分だけの“集中の型”を形づくっていきます。
そして、整う行動を日常に組み込むことができれば、
集中力はもう「気合で絞り出すもの」ではなくなります。
“一度で正解を見つける”必要はない
自分に合う集中スタイルを見つけるには、トライ&エラーが欠かせません。
そこで役立つのが、小さなPDCAサイクルです。
- Plan(計画):「こうすれば集中できるかも」と仮説を立てる
- Do(実行):実際にやってみる
- Check(振り返り):何がうまくいった?何が合わなかった?
- Act(改善):よかったことは続け、合わない部分は調整する
このサイクルを日常の中に組み込むだけで、
集中力は“気分に左右されないスキル”として、少しずつ育っていきます。
まとめ|原因別の解決策を探りながら“自分に合った集中スタイル”を見つけよう

あなたが集中できないのには、必ず理由があります。
そしてその理由に合う解決策を実践すれば、再現性のある方法で集中力を発揮できるようになります。
まずは、身体・メンタル・環境・タスクの4つの視点から、
今の自分に何が起きているのかを見直してみましょう。
そして、短期的なテクニックに頼るだけでなく、
長期的に機能する習慣や仕組みを整えていくことも忘れずに。
集中は気合いで乗り切るものではありません。
整え方と向き合い方で変えていける力です。
もちろん、自分にぴったりのやり方は、一度で見つかるとは限りません。
だからこそ、小さなPDCAを回しながら、試して、振り返って、少しずつ調整していく。
その積み重ねが、やがて
「自然と集中できている」日常へとつながっていきます。
がんばらなくても集中できる状態は、誰でも手に入れられます。
その第一歩として、今日できそうなことを、ひとつだけ選んでみてください。
そこから、すべてが始まります。
行き詰まったら専門家のサポートも検討しよう
もし「集中できない状態」が長く続いているなら、
無理にがんばり続けるのではなく、必要に応じて専門家に相談することも、
自分を守るための大切な選択肢です。
集中力を高めたいのに、どうにも行き詰まってしまう…
そんなときは、ぜひ一度ご相談ください。
あなたに合った集中のしくみを、一緒に整えていきましょう。▶ サービスの詳細はこちら