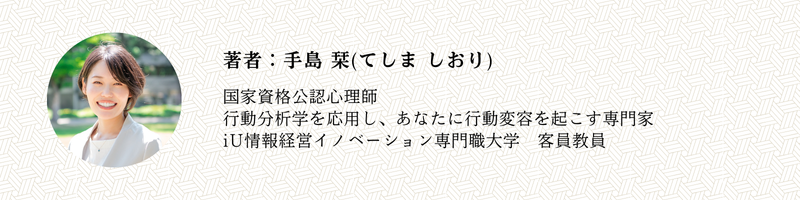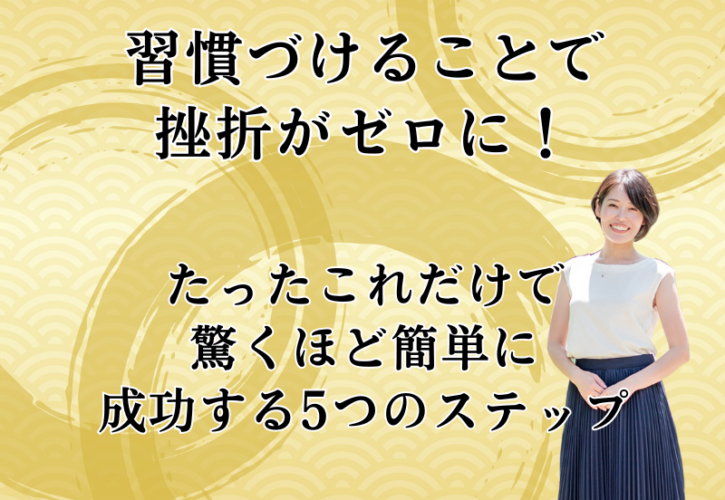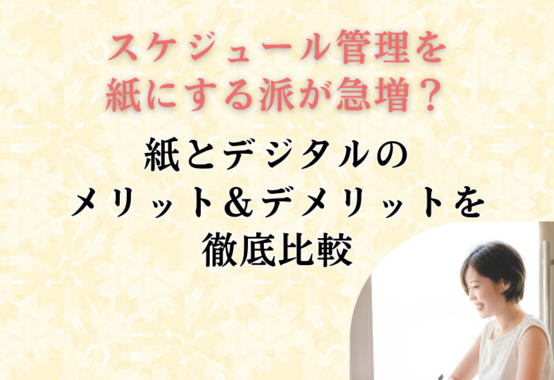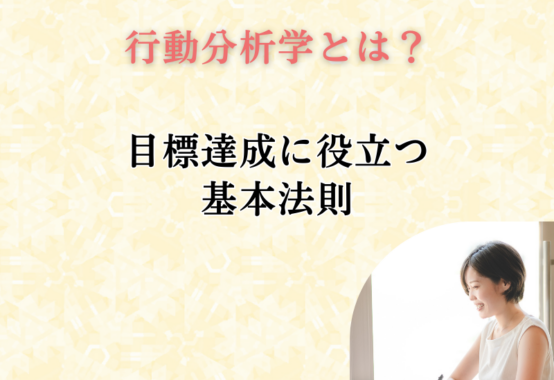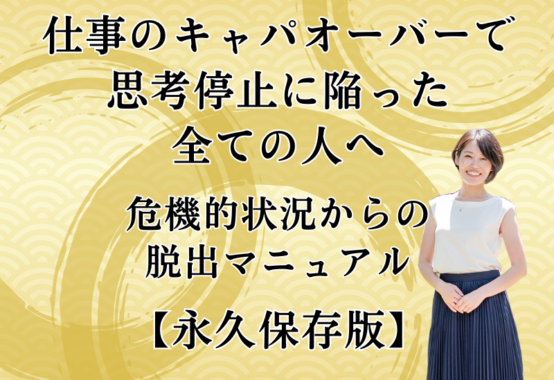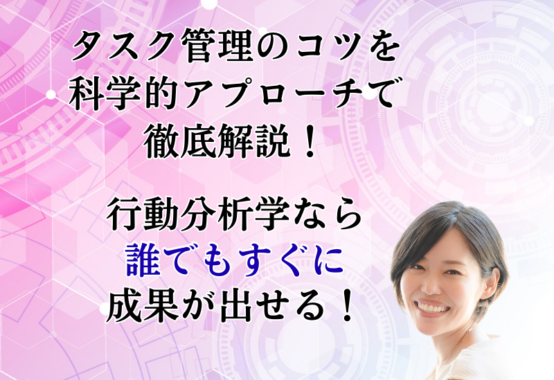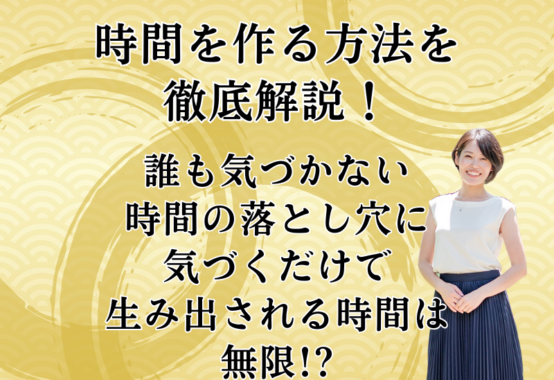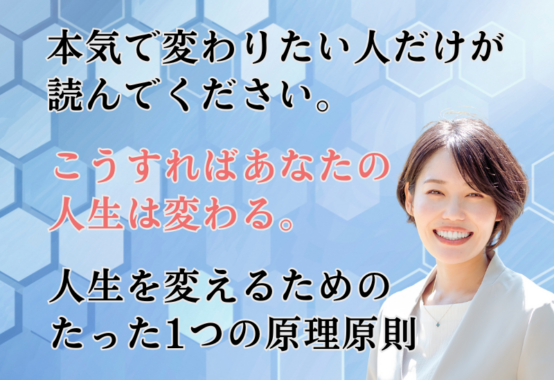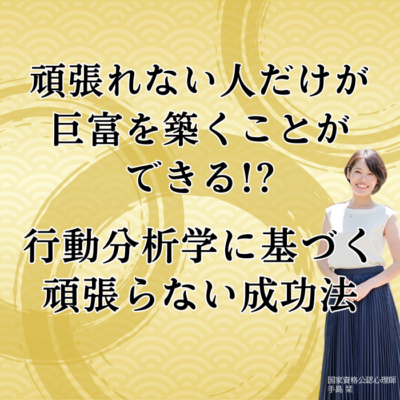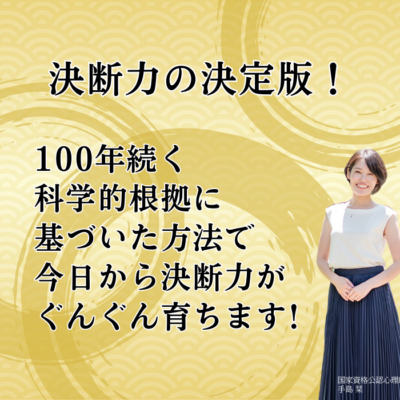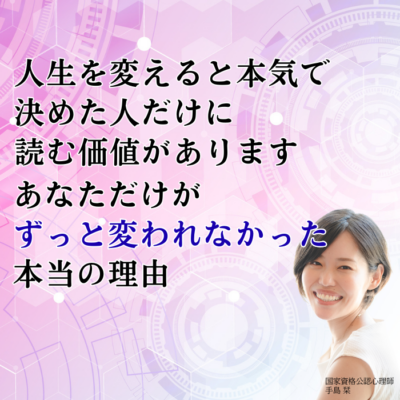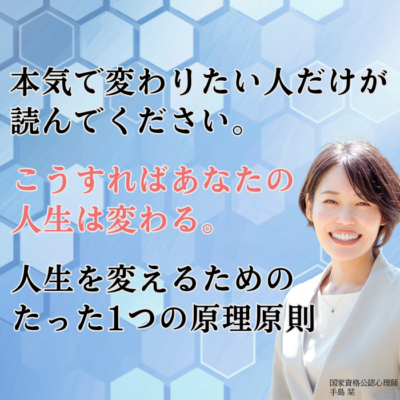こんにちは!行動分析学の専門家、手島栞です。
「どうしても、目標に向けた行動がとれない…」そんなお悩みをお持ちの方へ向けて、行動するためのヒントをお届けしています。
「目標に向かって行動を続けたいのに、いつの間にかやめてしまう…」と困っていませんか? あるいは、「新しい習慣を始めても、うまくいかない」と感じたことはありませんか?
経営者の方は、日々たくさんの仕事を抱えていますよね。大事な決断をしたり、新しいプロジェクトを進めたり…。こうした場面で、「習慣の力」がどれほど大切か、すでにお気づきの方も多いでしょう。どんなに小さな行動でも、それが続けば大きな変化を生み出します。
一方で、「習慣づける」ことは思った以上に難しく感じるもの。そこで、この記事では「なぜ習慣を続けるのがむずかしいのか?」をわかりやすくひも解きながら、確実に続けるためのポイントをまとめてみました。ぜひ最後まで読んでいただき、明日からの行動に役立ててみてくださいね。
「習慣づける」とは?その意味と重要性
「習慣づける」と聞くと、「毎日欠かさずやること」を思い浮かべるかもしれません。
たとえば、駅から自宅まで無意識に帰れたり、シャワーのあとのリンスが当たり前になったり…。
こういった“意識しなくても当たり前にできる行動”が増えるほど、余分なエネルギーを使わずにすむので、他の大事なことに頭を使えるようになります。
習慣化のメリット
- エネルギーと時間を節約できる
「やるかどうか迷う」時間が減って、頭を悩ませなくてすみます。 - 自信(自己効力感)が高まり、メンタルが安定しやすい
「自分はやればできる」と思えると、気持ちが落ち着いて行動しやすくなります。 - 小さな積み重ねが大きな成果につながる
たとえば毎朝5分のニュースチェックを続けるだけでも、ビジネスチャンスを逃しにくくなる…そんな「続ける力」こそ習慣の魅力です。
こちらの記事では、習慣づけられている行動が増えることが、人生にどのような影響を与えるのか、事例を挙げながらお話しています。
なぜ「習慣づける」ことが難しいのか?
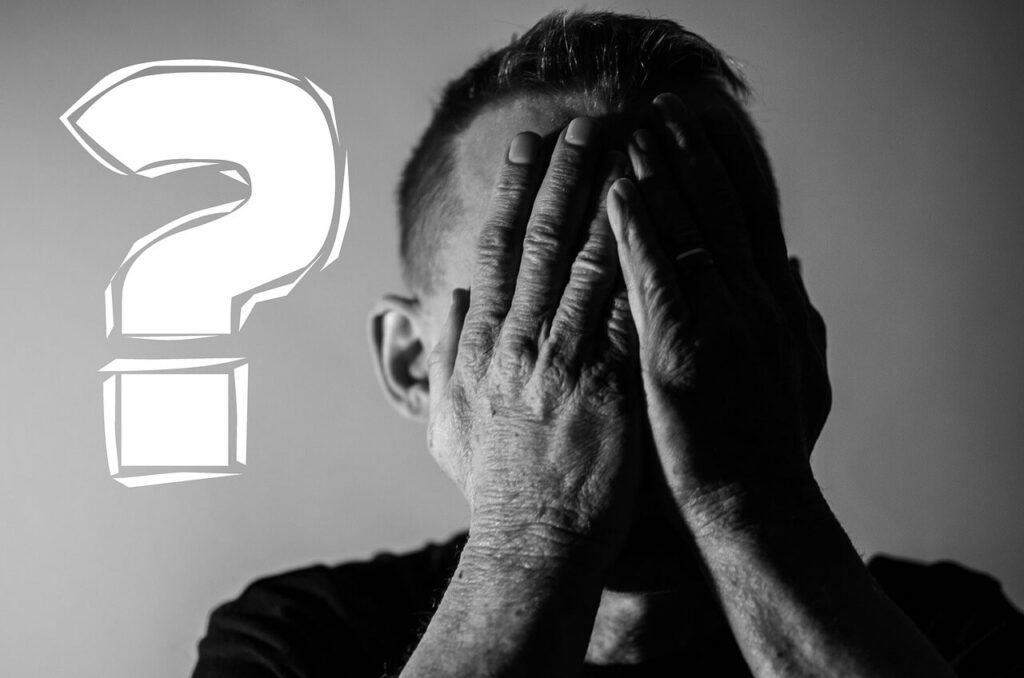
ここからは「行動分析学」の視点で、新しい習慣が続かない原因を説明します。
すぐに報酬(いいこと)を得られない
人は「行動したあとにいいことがある」と、その行動を繰り返しやすくなります(これを「強化」といいます)。
でも、読書や運動など、新しく始めることは、すぐに成果を感じにくいですよね。そのため、ついスマホでリフレッシュするなど「手軽に快感が得られる行動」に流れがち。
結果として、本来やりたかったことが続かなくなります。
長年染み付いた“無意識の習慣”を変える難しさ
私たちは、何年もかけて自然に身についた行動パターンをたくさん持っています。そこに新しい習慣を上書きするには、どうしても最初はエネルギーが必要です。
朝運動する習慣を始めてみたら、朝食の時間が足りなくなってバタバタ…と、思わぬ変化も起こりやすいのです。
だからこそ「本当に必要な習慣は何か?」「どのくらいの頻度なら続けやすいか?」をじっくり考える必要があります。
行動分析学から見る「習慣づける」の本質

ここでは「習慣づける」仕組みを、行動分析学の視点で簡単に解説します。
より詳しい心理的メカニズムや原因を知りたい方は、こちらの記事もあわせて読んでみてくださいね。
「行動が変わる仕組み」は「トリガー」づくりがカギ
「歯磨きのあとは日記を書く」「朝コーヒーをいれたら勉強を始める」など、すでに毎日やっている行動にくっつけると、新しい習慣を思い出しやすくなります。
「週1回でも、そのタイミングだけは必ずやる」と決めるのも立派な習慣づけです。
「トリガー」づくりが習慣化を後押し
行動分析学では、行動が続くためには「行動のあとに良いことがある」ことが重要だと考えます。
すぐに良さを実感できない行動でも「小さなごほうび」を設計しておくと、続けやすくなります。
自分の行動の仕組みに合わせてカスタマイズ
自分に合った“トリガー”や“小さなごほうび”を見つけることが大事。「自分がどうすればやる気が出るか」「何があると動きやすいか」といった“行動のパターン”を観察し、カスタマイズしていきましょう。
成功するための「習慣づけ」の5つのステップ

新しい習慣を身につけるには、単に「やる」と決めるだけでは不十分です。ここでは、行動分析学に基づいた5つのステップをご紹介します。これらを実践することで、無理なく確実に習慣を定着させることができます。
①目的・ゴールの状態を明確にする
はじめに「なぜその習慣を身につけたいのか?」という理由と必要性をはっきりさせます。また、最終的にどのような状態(ゴール)を目指すのかを具体的に定義することで、行動の意味を強く感じられるようになります。
具体的なステップ
- なぜその習慣を身につけたいのかを明確にする
- 自分がその習慣を始める理由を考えます。例えば、健康維持、スキル向上、ストレス解消など、目的を具体的に設定しましょう。
- 最終的にどのような状態を目指すのかを具体的に定義する
- 目指すゴールを明確にイメージします。ゴールが具体的であればあるほど、行動の方向性が定まりやすくなります。
ゴールの違いによる具体例(読書編)
読書習慣を身につけたい場合、ゴールによってアプローチが変わります。以下に3つの具体例を示します。
- 本に書かれた内容を単純にインプットする(ざっくり理解したい)
- 目標:とにかくページをめくり、内容を一通り読む。
- 習慣化する行動例:1日1章を読む、休日に一気に読むなど。
- 内容をしっかり理解して整理する
- 目標:本の内容を理解し、自分なりにまとめられるようになる。
- 習慣化する行動例:読んだ内容をメモやSNSに投稿してアウトプットする。
- 理解したうえで、自分の生活に落とし込むところまで狙う
- 目標:読書から得た知識・アイデアを日常や仕事に応用する。
- 習慣化する行動例:読んだ内容を、自分の生活にどう生かせるか思考する時間をつくる。ノートにまとめて具体的なアクションプランを立て、数日ごとに「実際に生活に取り入れてみてどう感じたか」を振り返る。
②小さな一歩から始める、または質を求めず行動をなぞる
行動を無理なく始められるように計画を立てます。大きな目標をそのまま実行しようとすると負担が大きくなり、挫折しやすくなります。始め方は以下の2つのアプローチがあります。始めやすいアプローチを活用して、習慣化をスムーズに進めましょう。
小さな一歩から始める
まずは、目標となる行動を「無理なく実行できる小さなステップ」に分解します。これにより、行動のハードルを下げ、継続しやすくなります。
(具体例)
読書習慣を身につけたい場合
- 本を手に取る: 本棚から本を出して机に置く、または電子書籍ならタブレットやスマホを開くだけでOK。
- 本を開く: 「カバーをめくり、読みたいページを開く」といった具体的な行動に分解。
- 一文だけ読む: たった一文でも読むことで、読書を始めたことになります。
- 一段落読む → 一ページ読む → 一章読む: 徐々にステップアップしていく。
時間で段階をつくる方法
- 最初は短時間設定: 例えば「5分だけ読む」といった短い時間を設定。
- 徐々に時間を増やす: 慣れてきたら「10分」「30分」と段階的に時間を延ばしていく。
質を求めず、行動をなぞる形から始める
行動の「完成度」や「質」にこだわらず、まずは形だけでも行動を繰り返すことが習慣化の鍵です。これにより、行動自体を始めるハードルが下がり、自然と習慣が定着しやすくなります。
(具体例)
運動習慣を身につけたい場合
- 運動着に着替える: まずは運動着に着替えるだけでOK。
- 軽いストレッチを1分行う: ストレッチを1分だけ行うことで、運動を始める。
- ウォーキングを5分する: 無理なく5分間だけ歩くことで、運動を継続する習慣を作る。
読書習慣を身につけたい場合
- 本を開いて眺めるだけ: 内容を読むことにこだわらず、本を開いてページを眺めるだけでもOK。
- 一文だけ声に出して読む: 読んだ一文を声に出して読むことで、行動を確実に実行する。
③トリガー・強化の設計を自分に合うものに変える
行動を始める「きっかけ(トリガー)」と、続けるための「ごほうび(強化)」を上手にデザインします。自分の生活や行動の仕組みに合ったトリガーと強化を設定することで、習慣化が格段にしやすくなります。
トリガーを既存の習慣に結びつける
既に日常的に行っている習慣や行動に新しい習慣を結びつけることで、新しい行動を開始するハードルが下がります。
(具体例)
- 朝食を終えたらストレッチを始める
- 歯磨きをした後に日記を書く
- コーヒーを飲みながら読書をする
外部トリガーを活用する
外部からの刺激を利用して、行動のきっかけを作る方法です。内部トリガー(思考や感覚の変化)に頼ると自分で把握しづらいため、外部トリガーを積極的に取り入れることをおすすめします。
(具体例)
- スマホのアラームを使って、毎日決まった時間に読書を始めるようリマインドする。
- 運動用具をリビングに常備しておくことで、運動を始めやすくする。
強化(ごほうび)を活用する
行動中や行動後に、自分が嬉しく感じるごほうびを設定することが効果的です。これにより、行動を繰り返しやすくなります。
(具体例)
- 達成感を感じるアクティビティを取り入れる
例: サウナ好きの方の場合、サウナ併設のジムに通い、運動後の楽しみを設けておく。
- 視覚的な成果を確認する
例: 毎日読書をしたらカレンダーに印をつける。視覚的に達成感を感じやすくする。
- 社会的な承認を活用する
例: 習慣化したい行動に取り組んだら、SNSに投稿し、反応をもらう。
- 特別なご褒美を設定する
例: 1週間連続で運動を続けたら、自分へのご褒美として好きなデザートを食べる。
- 学びや成長を感じる活動を組み込む
例: 習慣を通じて得た知識を活かしてワークショップを開催し、自分の成長を他人と共有する。
④進捗を記録し振り返る
進捗を記録し、定期的に振り返ります。これにより、自分がどれだけ目標に近づいているかを客観的に確認し、必要な調整を行うことができます。
記録ツールを選ぶ
まずは、習慣の進捗を記録するために自分に合ったツールを選びましょう。後ほど、5章で詳しくご説明します。
定期的に振り返りの時間を設ける
記録をつけるだけでなく、定期的に振り返る時間を確保しましょう。これにより、自分の進捗を分析し、改善点を見つけることができます。
- 週1回の振り返り
週末にその週の進捗を確認し、「どのくらい習慣が続いたか」「何がうまくいかなかったか」を分析します。
- 月末のレビュー
月ごとに詳細なレビューを行い、長期的な進捗や達成度を評価します。必要に応じて目標や方法を修正します。
- フィードバックを活用する
専門家に進捗を共有し、フィードバックをもらうことで、客観的な視点を取り入れます。
課題点を分析し、計画を修正する
振り返りの結果を基に、課題点を分析し、計画を修正することで、より効果的な習慣化を目指します。
- 課題の特定
振り返りで見つかった問題点を明確にします。例えば、特定の時間帯に行動が続かなかった原因を探ります。
- 改善策の立案
課題を解決するための具体的な改善策を考えます。例えば、時間管理を見直す、環境を整えるなど。
- 計画の調整
目標や行動計画を必要に応じて調整します。無理な設定を避け、現実的な目標に修正します。
⑤小さな成功を積み上げる
小さな成功を意識的に捉えて積み重ねていきます。小さな目標を達成するたびに、その成功を認識し、喜びや達成感を味わうことで、次の行動への意欲が高まります。
小さな達成でOK
大きな目標を一度に達成しようとするのではなく、小さな目標を設定して達成感を積み重ねることが大切です。
(具体例)
- 3日連続でできたら「3日連続で運動できた!」と自分を褒める。
- 1週間連続で続けられたら「1週間続けられた!」と自分へのごほうびを設定する。
喜びや達成感をしっかり味わう
達成した際には、その喜びや達成感をしっかり感じることが重要です。これにより、自己効力感が高まり、習慣を続ける意欲が増します。
(具体例)
- 運動を終えたら「今日も運動できた!よく頑張った!」と自分を褒める。
周りの人にも報告する
周りの人に進捗を報告することで、外部からの承認を得られ、継続するモチベーションが高まります。あなたの挑戦を応援し、適切に評価してくれる人に限定して報告しましょう。
(具体例)
- オンラインコミュニティで共有する
- 同じ目標を持つ仲間と進捗を共有し、励まし合う。
習慣づけを助けるツールとアプリ
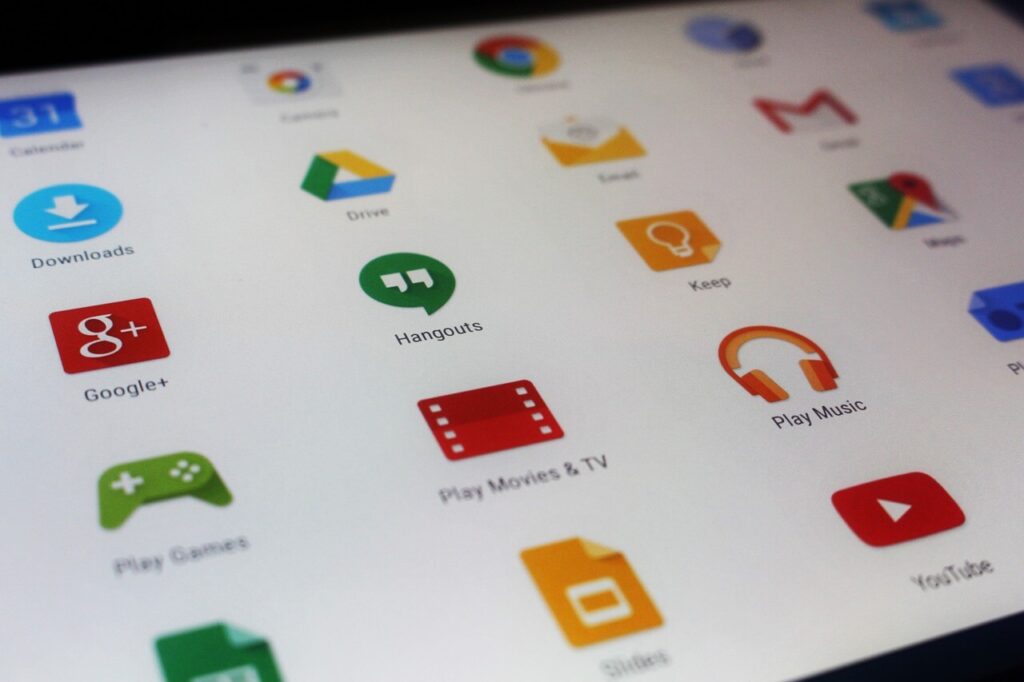
習慣化を継続するうえで助けになるツールやアプリ、仕組みをご紹介します。デジタルが得意な人も、アナログがしっくりくる人も、専門家の力を借りたい人も…それぞれの環境や行動傾向に合ったサポート方法が見つかれば、ぐっと続けやすくなります。
習慣づけに役立つ!おすすめアプリ3選
Habitify
- こんな人におすすめ:記録を取ること自体が面倒になりやすい方
- 特長:ウィジェット機能で簡単に記録でき、習慣の種類や時間帯も細かく設定しやすい。
- ダウンロードは、こちらから。
みんチャレ
- こんな人におすすめ:一人でコツコツ頑張るより、仲間と励まし合いながら続けたい方
- 特長:同じ目標を持つチームでやるので、報告やスタンプで楽しみながら継続。孤独感が減ります。
- ダウンロードは、こちらから。
継続する技術
- こんな人におすすめ:まずは1つに集中し、習慣の達成感を得たい方
- 特長:1つの小さな習慣を30日続ける仕組みで、いきなりたくさんのことをやらずに済むので成功体験を積みやすい。
- ダウンロードは、こちらから。
物理的なツール(手帳、チェックリスト、カレンダー)の効果的な使い方
「スマホを開くのが手間」と感じるなら、アナログツールを使うのも手です。
デジタル機器をタップするよりも、手書きしたほうが「やった感」を味わいやすい人がいます。また、カレンダーを部屋の壁に貼っておいたり、いつも使う手帳にチェック欄を設けたりすることで、わざわざアプリを立ち上げなくてもサッと記録ができる状態を作れます。
視界に入る場所に記録ツールがあるおかげで「今日やることを思い出しやすい」「終わったらすぐに書き込める」という利点があり、結果的に習慣の継続につながりやすくなります。
行動を見守るサービス:手島栞が提供する「行動監視型サポートサービス」のご紹介
もし「最初のスタートダッシュをどうにかしたい」という方は、行動を見守ってくれるサポートを検討してみてください。
手島栞がオンラインで提供する「先延ばしタスク片付け部屋」は、ビデオ通話であなたの行動を監視し、先延ばしタスクの片付けを手助けをするサービスですが、習慣の立ち上げ時期の10日間など、短期集中で利用する人も増えています。
- 行動を監視してもらうメリット
自分一人だけで「やらなきゃ」と思っていても、なかなか腰が上がらないことがあります。しかし、「この時間に○○をやる」と手島と事前に約束することで、約束を守るためのモチベーションが高まり、実行率がグッと上がります。
「自分との約束は守れないけど、人との約束は守る」という方にうってつけの仕組みです。 - ビデオ通話での監視がもたらす安心感
作業している間、オンラインでつながっているだけでも「誰かが見てくれている」と思えるため、サボりたくなる気持ちを抑えやすくなります。特に、習慣を立ち上げる最初の10日間は、ちょっとした油断がそのまま挫折につながりやすい時期。ここを乗り切るための“外部からの力”として、有効なサポートとなり得ます。
「自分は厳しくされないとやらないタイプかも…」と少しでも思うなら、こうした外部の力を借りるのも立派な戦略。最初の壁を突破するだけで、習慣づけがスムーズになる場合も多いですよ。
『先延ばしタスク片付け部屋』の詳細はこちらをご覧ください。
習慣づけが失敗したときの回復方法

習慣化がうまくいかなかったと感じたとき、それは失敗ではなく、自分に合った方法を見つけるための貴重なデータが得られたと捉えましょう。
まずは、なぜその習慣が続かなかったのかを冷静に分析します。例えば、時間帯が合わなかったり、トリガーが効果的でなかったりする場合があります。この情報を基に、次回は異なるアプローチを試すことができます。例えば、習慣を行う時間を変更したり、別のトリガーを設定したりすることで、より自分に適した方法を見つけることができます。
また、小さな調整を積み重ねることで、無理なく習慣を定着させる道筋が見えてきます。失敗ではなく、自己理解のチャンスと捉え、柔軟に対応していきましょう。
今日から始める「習慣づけ」の始まり
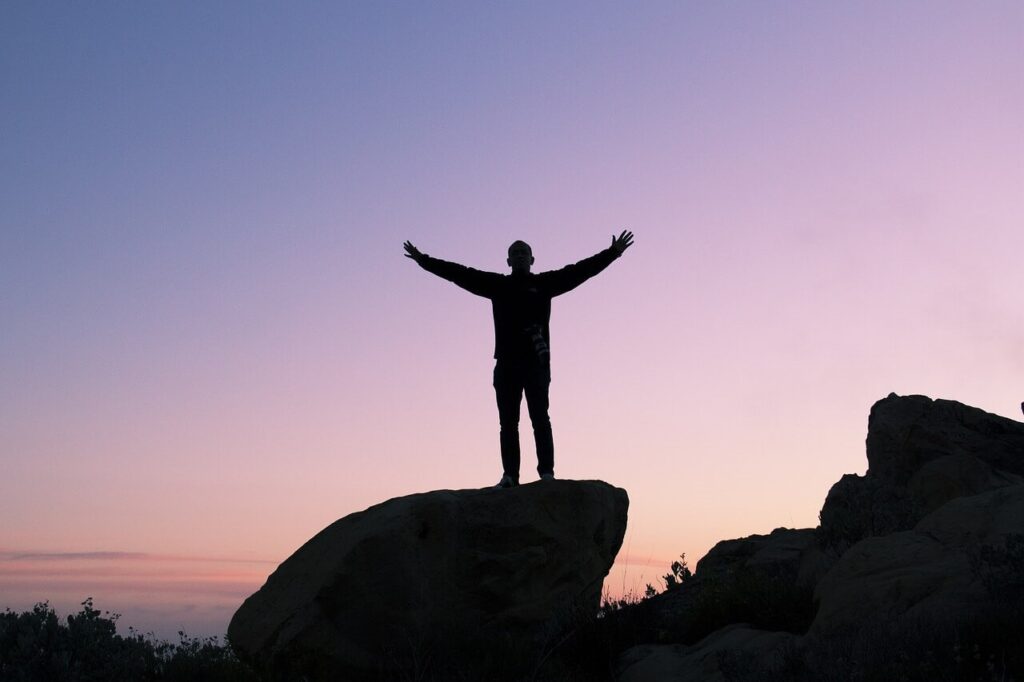
どんなに大きな成功でも、小さな一歩から始まります。会社の経営で忙しい方でも、“ほんの数分だけ”なら続けられるはず。
歯磨きのあとに日記を書く、昼休みに5分だけ英語を勉強するなど、小さな行動でもかまいません。まずは行動を始めることが大事です。
あなたの決断一つで未来は変わります。今日、ここで紹介したステップやツールを試してみませんか?一歩を踏み出せば、新しい習慣があなたの可能性を広げてくれます。すぐ始めれば、明日が変わります。
行動分析学に基づいて、あなたの習慣づけをサポートします
あなたの習慣化がうまくいかない理由を分析し、あなたに合う習慣化プランをご提案します。無料相談実施中。サポートをご希望の方はこちらをご覧ください。