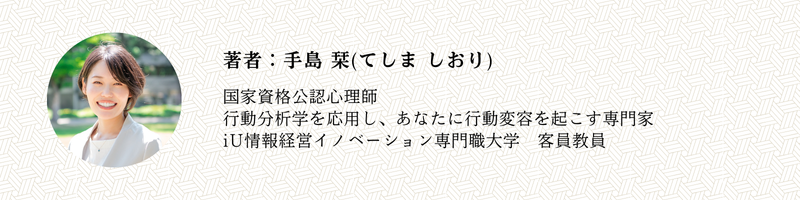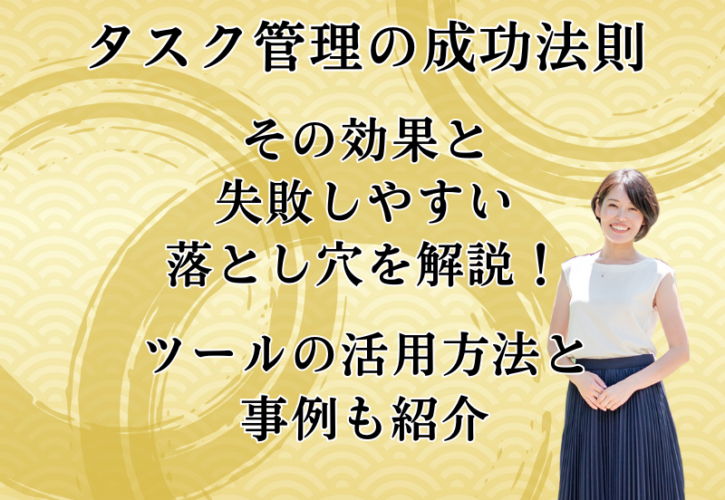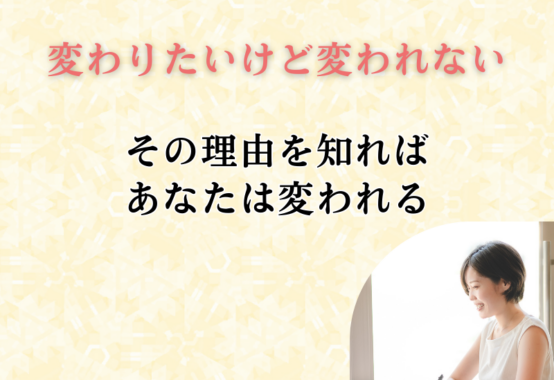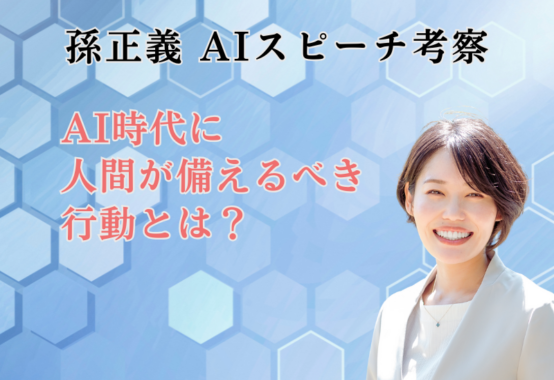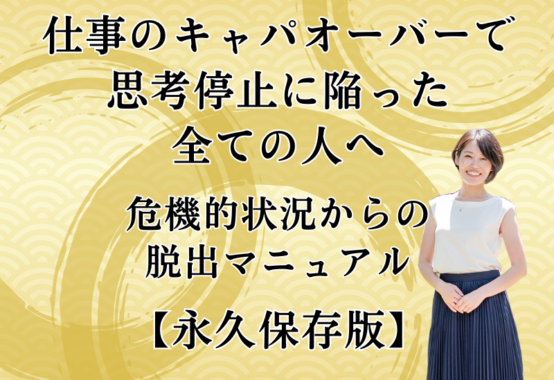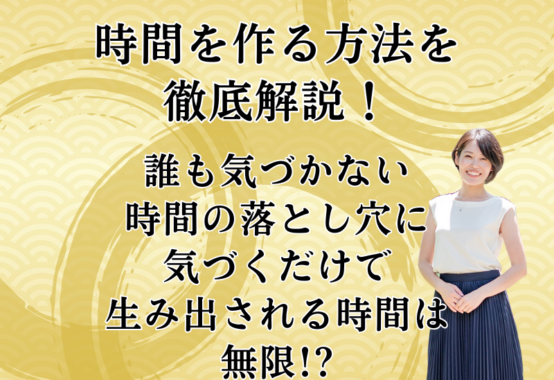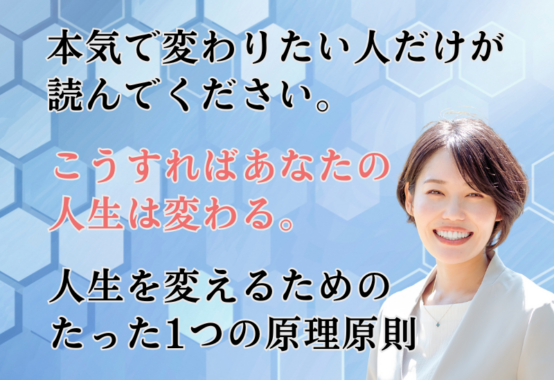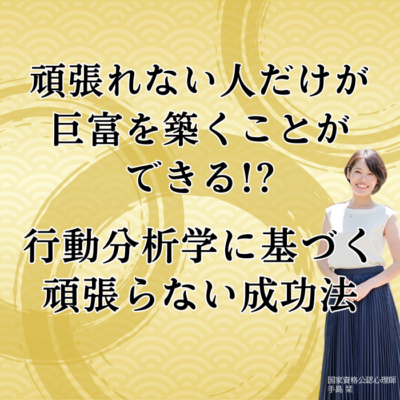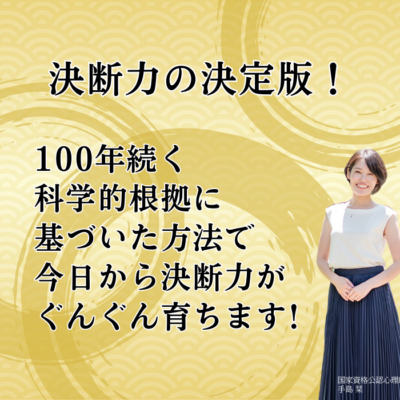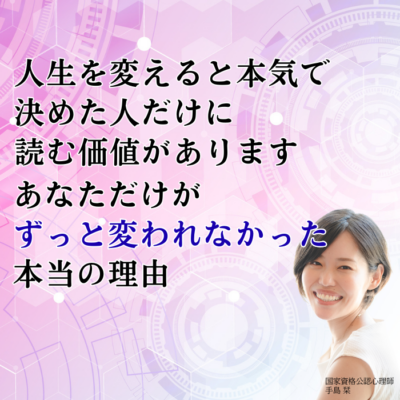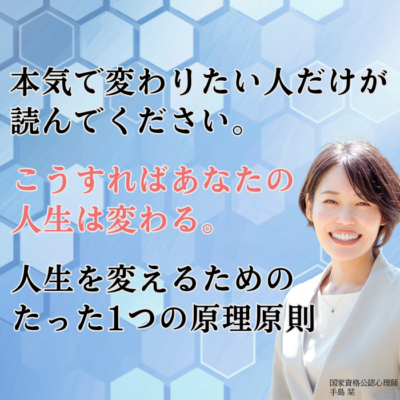こんにちは!行動分析学の専門家、手島栞です。
「何かが障壁になって、どうしても目標を達成できない」
そんなお悩みを抱える経営者やビジネスマン向けに、目標達成に役立つ情報を発信しています。
タスクが管理しきれない・・・いつまで頑張れば良いのだろう
- 「タスク管理しないといけないことはわかっているけれど、やるべきことが多すぎて、どこから手をつければ良いか分からない」
- 「抜け漏れがないかどうか不安で、夜もなかなか眠れない」
- 「やるべきタスクをついつい先延ばしして、気づけばいつも締め切り間近」
- 「タスク管理をどんなにしても、管理に時間がかかってタスク管理そのものが無駄に感じてしまう」
あれをしなければならない、これをしなければならないと、常にタスクのことが頭から離れず、タスクに振り回されて息つく暇もないという生活は息苦しく、いつまでこんな生活を送れば良いのかと疲弊してきます。
その状態が一時的なものであれば乗り切れるのかもしれません。でも、仕事している間ずっとタスクに振り回されてばかりいると、いつか必ず息切れをしてしまいます。
「仕事は長距離走」とよく言われますが、あなたに合った持続可能な方法を見つける必要があります。
今日はあなたの仕事を上手くいかせるための、「タスク管理」について徹底解説していきます。
私はあなたの行動と成果を科学的にベクトルに変化を与え、成果を激変させる専門家です。
これから読んでいただくことはあなたのビジネスや人生にとってとても重要なことなので、少し長いかもしれませんが、最後まで読んでいただくことをおすすめします。
もちろん、今タスク管理で全く困っていないよという方にとっては、無理に読んでいただく内容ではないので、スルーしていただいて大丈夫です。
タスク管理とは?その目的と効果
タスク管理の目的は、タスクを実行しやすい状態を得ることです。実行しやすい状態というのは、
「今できるという確信を得られている状態」
です。そのためには、どのタスクに手をつければ良いのか明確に分かる必要があります。
タスクを実行しやすい状態を得られるようになれば、タスクに着手することに迷いがなくなるので、すぐに行動を起こすことができます。
また、タスクに着手しやすくなるだけでなく、タスクを減らすことも可能になります。本当に自分にとって重要なタスクが分かり、それ以外のタスクをどうすれば良いのか判断がしやすくなります。
タスクを減らし、自分がやらなければならないタスクに、時間を無駄にせず着手できるようになると、時間の余裕が生まれます。
時間の余裕は心の余裕を生み出します。心に余裕のある状態になれば、カツカツで仕事をしていた自分では想像もできないくらい思考が柔軟になったり、よりアクティブに行動をとることができるでしょう。
経営者やフリーランスに最適なタスク管理法

人生の目的がはっきりしている経営者やフリーランスの方々が抱えているタスク量は膨大で、一人の人間が記憶できるタスクの量をオーバーしていることが多くあります。
タスクを記憶し、頭の中で優先順位付けをしていると、抜け漏れが発生してしまいます。
もしあなたが個人の能力を最大限に発揮したいと望むなら、脳を記憶ツールとして使ってはいけません。脳を記憶の手段として使うのではなく、あなたのビジネスを左右する大事な意思決定や、新しい発想に使うべきです。
脳を記憶に使う代わりに、信頼のおける外部記憶装置を使うことをオススメします。信頼のおける外部記憶装置というのは、タスクを管理するために有効で効果的なツールや仕組みのことです。
たとえば、タスク管理のためにITツールを使う人もいますし、手帳に手書きで書く人もいます。秘書などの人間を使う人もいますよね。ここでいうタスクを管理するための有効で効果的なツールや仕組みというのは、何か特定の方法を絶対に使わないといけないというわけではなく、あなたの目的達成のために、あなたのタスクが「今できるという確信を得られている状態」にできることであれば何でも良いわけです。
ここを見れば全てのタスクが入っている、この方法を使えばいつでもタスクが把握できるという安心感を持てるような「第二の脳」としてタスク管理ツールやタスク管理の仕組みを作って活用しましょう。
タスク管理するうえで必須となる力とは?
タスク管理のメリットを理解し、良さそうなタスク管理ツールと出会えても、タスク管理を断念する人が続出しています。
なぜでしょうか?
それは、「続ける」という視点が抜けているからです。タスク管理は習慣とセットで考えていかなければ、続けられずに一時的なもので終わってしまいます。
多くの人が一度はタスク管理系のノウハウ・スキル本を購入したことがあるかと思いますが、今まで読んできた本で実際に今も活用し続けられているタスク管理方法はいくつありますか?
きっとほとんどの方は今まで読んできた本の内容を活用できていないのではないかと思います。
タスク管理成功のための習慣づくりは地味
多くの方が陥る落とし穴は、素晴らしいツールを使えば、今の苦しいタスク地獄のような生活をすぐに改善してくれると幻想を抱いていることです。
しかし、タスク管理をするうえで、最も大事なことは「素晴らしいツールを使うこと」ではなく「いかにそのツールを使い続け、タスクが管理できている状態を維持するための習慣を作るか」という点なんです。
朝起きる習慣でも、筋トレでも、ランニングでも、習慣づくりというものはとても地味な作業です。
一発逆転のようなものではなく、毎日コツコツ。誰に褒められるわけでもないのに、続けなければなりません。
この地味な作業がタスク管理の成否を左右するということを理解しておかなければ、どんな素晴らしいツールを使ったとしても失敗に終わります。
でも安心してください。
このどんなに地味で維持し続けることが苦しいタスク管理作業だったとしても、その苦痛を取り除いていくことも可能です。
行動分析学とは?タスク管理にどう役立つのかを解説
行動分析学は、人や動物が「なぜそのように行動するのか?」行動の原因を解明し、行動に関する法則を見出す科学です。
実験室で見出されたいくつかの法則が活用され、今では行動分析学を応用して、社会の中の実践的な問題を解決しています。
行動分析学を活用すると、行動を制御したり、予測したりすることができるようになります。
「タスク管理」という行動を「続ける」ときに、行動分析学を活用することで、続けやすくすることができます。
また「タスク管理」そのものをどのような「仕組み」にすることが人間にとって成果が出やすく効果的で、かつ、継続していきやすいのか?についても行動分析学を応用することができます。
今まで、何かのツールを使えばタスク管理がしやすくなるとか、このメソッドを使えば効果的だとか、様々な「タスク管理」に関するスキル本があったり、動画やコラムがあったりしたと思います。
ただ、その「タスク管理」のスキル・ノウハウ本を読んで実際にやるのは人間です。
ここで一つ問題が出てきます。
人間は一人一人個性や特徴が異なり、それぞれ強みや弱みもバラバラです。実際に「タスク管理」のスキルやノウハウを試そうとしても、どうしてもその内容が合う、合わない、続けられる、続けられないという問題が生じます。
また、たとえその方法が合っていたとしても、例えばその人個人に、「タスク管理」を「続ける」ことに問題がある場合、せっかく最適な方法で「タスク管理」ができていたはずなのに、「続けられない」原因が本人にある場合、それも「タスク管理」が続けられない原因になってしまいます。
最初に立てた目的・目標が達成されていれば問題はないのですが、「タスク管理」が続けられない場合は、おそらくは目的・目標も予定通りには上手くいっていないことでしょう。
そのため、「タスク管理」を「続けて」目的・目標を達成するために必要なことは、先ほどもお伝えしたように「いかにそのツールを使い続け、タスクが管理できている状態を維持するための習慣を作るか」なんです。
そこで「行動分析学」がでてくるわけです。
活用すると、自分の意思の有り・無しに関係なく、劇的な効果が出せる、人間にとっては希望になるような学問なのです。
行動分析学に基づいた、タスク管理を続けるコツ
タスク管理をするという行動は、いくつかの小さな行動が一連の動作となって形成されています。
その行動を細かく分解し、はじめの段階を特定するとしたら「タスク管理ツールを開く」であると考えます。
タスク管理を続けるコツとしては、はじめの行動目標を「タスク管理ツールを開く」に設定し、その行動を毎日続けることを目標にします。
一番簡単な行動レベルで、習慣化を目標とするため、タスク管理の質や、時間の長さは問いません。時間は5分でも大丈夫です。5分で良いから触って機能を覚えるというのに注力してください。
武術の型を体にしみ込ませるように、行動の流れを体に覚えさせます。
一日の中で、決まった流れの中に組み込むと、より習慣化しやすいでしょう。
朝起きて、コーヒーを飲む日課がある方は「コーヒーを淹れたらタスク管理ツールを開く」など、既にある習慣にくっつけると習慣化しやすいのでオススメです。
一見すると、「なんだこんなことか」と思われたかもしれません。
ですが、今までダイエットや朝の運動、タスク管理ツールの使用、朝の習慣を継続できてこなかった全ての人は、このような簡単なことが習慣化されていなかった、もしくは習慣化される環境にいなかったために、挫折してきたのです。
5分触ることができるようになったら、質を上げていく
5分タスク管理ツールを触ることが習慣化してきたら、次にタスク管理の質を上げていきます。
タスク管理の質を上げるというのは、たとえば、目的を見直し、よりタスク管理による効果を得るために、具体的に必要な手順を考え、実行に移していくということです。
タスク管理の質を上げることに関しては、「タスク整理でもう二度と焦らない!やるべきことを常にクリアにする方法と便利ツールも紹介」でも解説しているので、こちらも併せてお読みください。
「どうなったら習慣化したことになりますか?」と、よくご質問いただきます。
「やらないと気持ち悪いレベルになったら」とか「別のことを考えながらでもタスク管理ツールを開けるようになったら」など、さまざまな指標がありますが、ピンとこない方は、10日続けることができたら質を上げてみると良いでしょう。
質を上げた時に、毎日続けられていた「タスク管理ツールを開く」という行動ができない日がでてきたら、質のハードルが高すぎたことになります。
行動分析学を応用すると、「タスク管理ツールを継続的に使用する」という行動も一つの人間の営みとして認識しますので、その人がどこにハードルがあるのかを理解して、より効果的に「タスク管理ツールを継続的に使用する」ということを実行できるように改善することも可能です。
使い続けられるタスク管理ツールを見つけるには?3つのポイント
タスク管理ツールは世の中にたくさんあります。どれも良さそうで、どれが良いのか分からないというお悩みを感じる方も多いです。
使い続けられるポイントを3つお伝えしますね。
1. 使ってみたいと思える
「なんかかっこいい」
「使えるようになりたい」
心の内側から湧き出るワクワク感を持てるのであれば、その気持ちは大事にしましょう。
実はこのワクワク感などの気持ち、とっても大事なんです。
心理学の世界では、この心の内側から湧き出る「やりたい」「そのツールを使ってみたい」という気持ちのことを、内発的動機と言います。
この内発的動機があれば多少の困難さも乗り越えられることがあります。だからタスク管理ツール一つ取ってみても、ワクワクすることや使ってみたいという気持ちというのはとても大事なことなんですね。
ツールの見た目がカッコいい、イケてると思えるなら、使ってみても良いかもしれません。
そのツールを使いこなしている自分を想像して、ワクワクするのであれば、是非一度使ってみてください。
ただし、ツールを使ってみた結果、ツールの使い勝手が悪いとか、あなた自身の目的達成に合わないものだと良くないので、そこは注意しながら使ってみましょうね。
2. 使い方をすぐ人に聞ける
私がサポートさせていただいている方々の多くは、さまざまなタスク管理ツールを使うのに挫折した経験をお持ちの方々が多かったです。
なぜ挫折してやめてしまうのかというと、多くの方が操作が複雑で理解できなかったからという理由を挙げています。
操作に慣れるまでは、どんなツールを選んだとしても、面倒くささを感じるでしょう。その面倒くささを解消するために「分からない時にすぐに詳しい人に聞ける」環境があるのは、使い続けられるポイントとして大きいです。
身近にそんな人はいないという方は、ツールの使い方について質問できる機能をもっている会社もあります。
人に聞くのは申し訳ないという方は、チャットボットが使えるところもあるので、ぜひ検討してみてください。
また、最近では比較的周知されているタスク管理ツールであれば、ChatGPTやperplexityなどの自動生成AIツールで、ウェブ検索で使い方を調べることで、すぐにわかりやすく使い方を自動生成AIが解説してくれたりします。
こういうことも、タスク管理ツールをより一層使いやすくする手助けになりますので、使い方がわからない時や、どうしたら効果的にタスク管理ツールが活用できるだろうと考えている時にはぜひ活用してみてください。
3. 複数のデバイスで利用できる
自宅にいる時にPCでタスクを確認したいときもあれば、出張先で、旅先で、気軽にタスクを確認したいという方もいるかもしれません。
電車に乗っている最中に、タスクを思いついて整理したいとき、PCでしか管理できないツールを使っていると不便です。
使えないタイミングがあると、それだけでツールから足が遠のきます。複数のデバイスでデータを連携できるというのは続けやすいポイントになります。
タスク管理ツールを選ぶ時には、PCで使った時と、スマホやその他のデバイスで使った時の使用感についても調べておくと良いでしょう。
タスク管理の成功事例と失敗事例
これまでご相談に乗ってきたエピソードの中で、失敗事例と成功事例についてお話します。参考にしていただければ幸いです。
事例①完璧主義であれこれ機能をつけすぎて使わなくなって挫折したケース
さまざまな機能をカスタマイズできるタスク管理ツールを導入したAさん。あれもこれもと機能を追加することで、日々タスクを整理する時間が膨大になってしまいました。その結果、「今日は時間が無いからタスク整理ができない」という意思決定をしやすくなり、タスク管理ツールから足が遠のきました。
失敗経験を踏まえ、何のためにタスク管理をするのか改めて目的を再確認。タスク管理のこだわりを最小限にし、必要十分な機能をカスタマイズしたタスク管理ツールを使い続けることができました。
事例②仲間と一緒に使うことでツールの使用の継続に成功したケース
必要最低限のシンプルな機能を備えたタスク管理アプリを使っては、三日坊主で続けられない経験を積んできたBさん。Bさんのこれまでの人生を振り返ったときに、仲間がいると続けられることが分かりました。
初めての人にとってはハードルが高そうなタスク管理ツールに切り替え、同じタスク管理ツールを使っている人で構成されたコミュニティに入会することで、難しい機能について仲間に聞きながら解決していくスタイルをとり、タスク管理を継続することができました。
事例③「やることが曖昧だった」ことで続けられなかったケース
Cさんは「夜に1日の振り返りをする」という習慣を作ろうとしましたが、「振り返り」の目的と内容が曖昧で、だんだん日記を書くことに目的がシフトしてしまい、徐々に面倒になってやめてしまいました。
タスク管理の目的を明確にし、「タスクの達成率・うまくいった点、難しかった点の考察・明日やること」の3項目をテンプレ化し、タスク管理の流れも具体的に決めることで、迷いなく着手できるようになり、習慣化に成功しました。
PDCAサイクルで最適なタスク管理にしていく

何かを続けるうえで「完璧主義」と括られる行動の癖は、多くの場合足枷になります。はじめから完璧を目指すのではなく、タスク管理の精度を少しずつ上げていくつもりで、PDCAサイクルで改善していきましょう。
改善のサイクルも習慣に落とし込むと、より楽に、タスク管理を極めていくことができるようになります。
日々の忙しさに追われてしまうと、タスクのことを考えることはできても、タスク管理の方法や仕組み自体を見直すことは、ついつい後回しになってしまいます。毎日でなくても、週1回や、月1回などに、定期的に振り返る時間を設けるだけでも、違ってきます。
タスク管理が続かないあなたへ:専門家に相談するメリットとは?

そうは言われてもやはり、それぞれのタスクについて考えることや、タスクの実行に時間を取られて、気づけば週1回、月1回の時間すらとれないという方も多いのではないでしょうか?
タスク管理そのものを習慣化させようと思うと、環境から整えていかなければならないので、思っているよりもタスク管理の継続ができていない人が多いように感じられます。
また、振り返る時間を作れても、どのように改善していけば自分にとって良いタスク管理方法に変えていけるかが分からないという方も多いと思います。
そういう時は、定期的にあなたが直面している課題について分析し、あなたに合うタスク管理方法について提案し、より良くなるまでサポートし続けてくれる専門家に頼ってみるというのも一つの手です。
行動分析学を活用すれば、あなたのタスクの実行をスムーズにする、あなたのためのタスク管理方法を見つけることができます。どんなサポートが可能なのか、こちらで詳しくご説明しています。
まとめ
タスク管理は特別な才能や努力が必要なものではありません。小さな一歩を積み重ねるだけで、あなたの生活や仕事は確実に変わります。
例えば、「タスク管理ツールを開く」たったこれだけでも立派な第一歩。無理なく始められるシンプルな方法で、自分のペースで続けてみませんか?
大切なのは、完璧を求めることではなく、続けること。行動分析学の視点からも、小さな習慣を積み重ねることで自然と流れができ、負担なくタスクを管理できるようになります。
「できるかもしれない」と思えた今が、変化のチャンスです。