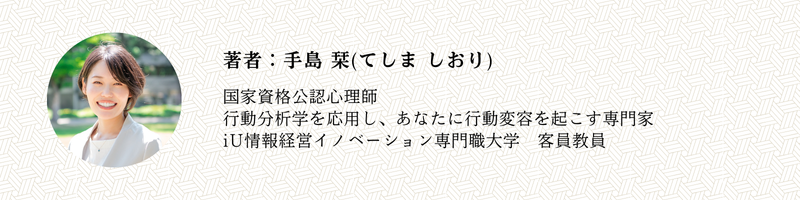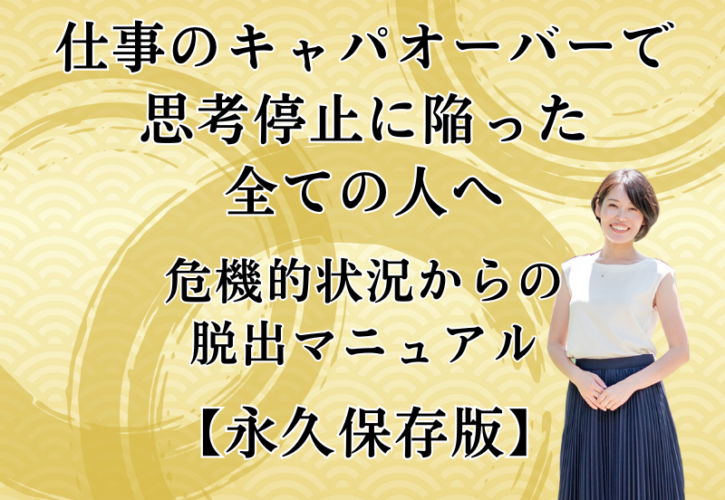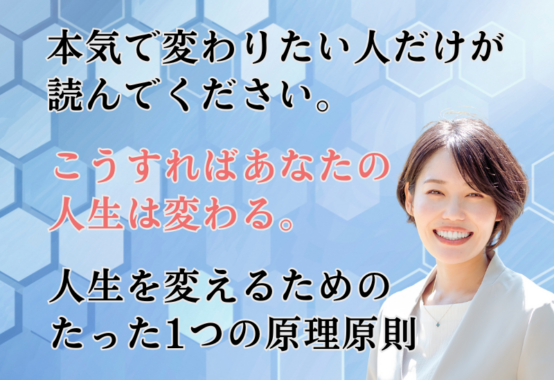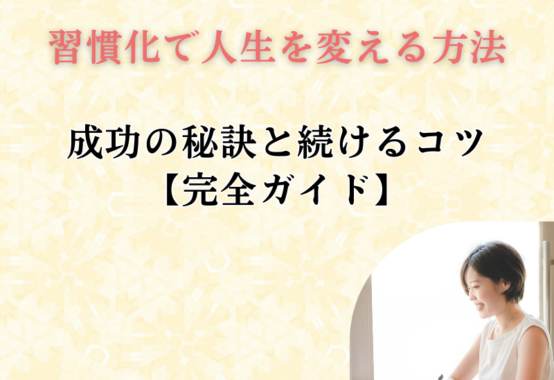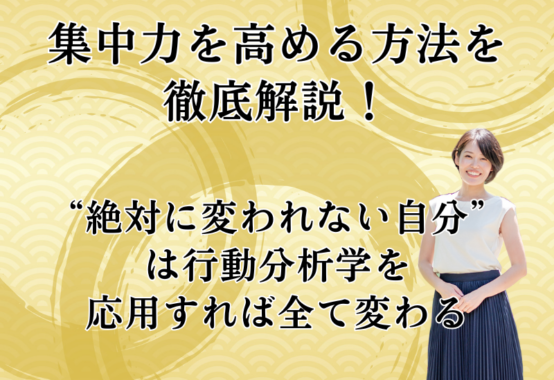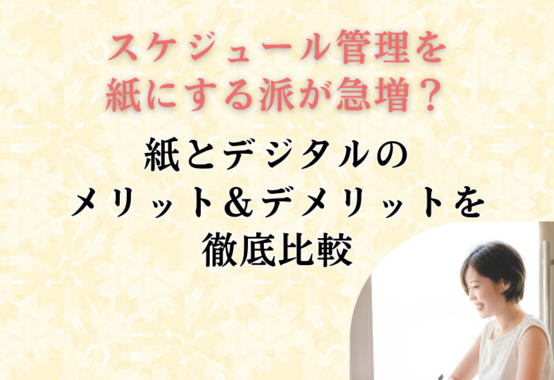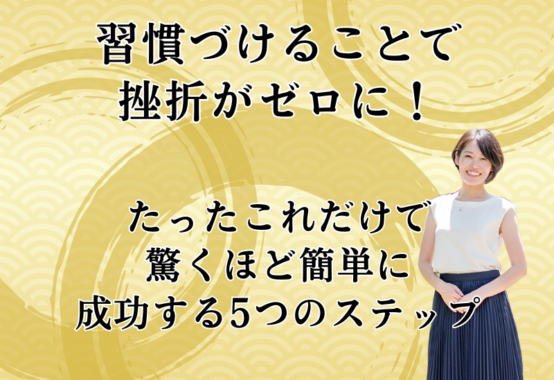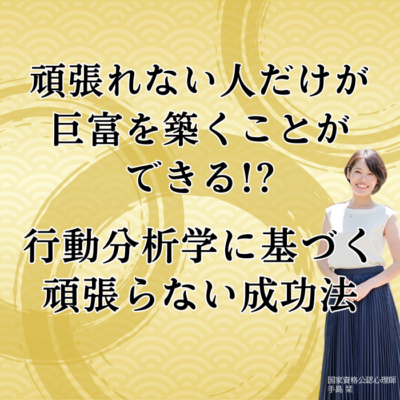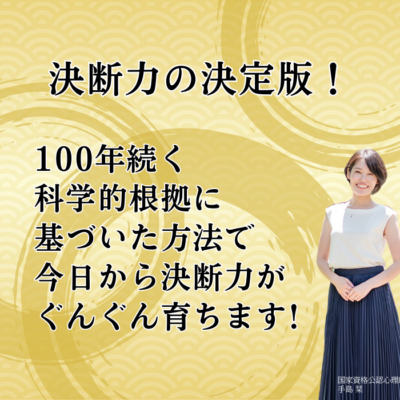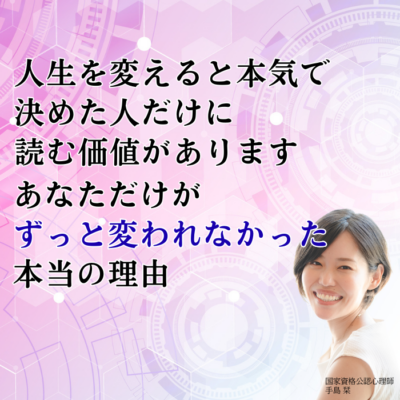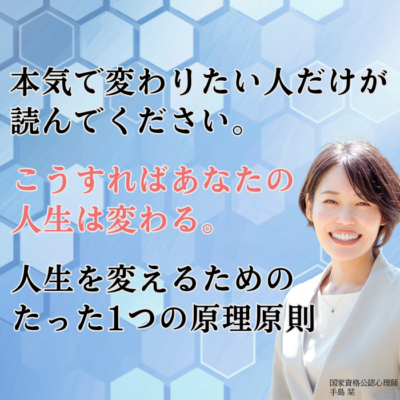こんにちは! 行動分析学の専門家、手島栞です。
私はこれまでクライアントの行動変容を73,050回以上起こし続けてきました。
これによって、多くのビジネスマンの行動が変わり、結果が変わり、自信につながっていくお手伝いをし続けてきました。
なかには、支援開始当初はお一人でタスクを大量に抱えて、キャパオーバーをしてしまっていたのが、たった1、2年で今では10名以上の部下を抱えるようになり、10倍以上も成果を出せるようになっている方もいらっしゃいます。
今日は仕事のキャパオーバーで思考停止に陥った方向けにメッセージをお送りします。
朝からずっと、やることは山ほどあるのに 何ひとつ終わらない。
PCの前に座っているだけで、タスクを見ても頭が動かず、気づけば無意識にスマホを触ってる。
やばい、進んでない、どうしよう。でも、何から手をつければいいかもわからない。考えることすら重たくて、動けない。
そんな状態が続いているなら、それは、あなたの意志が弱いからでも、甘えているからでもありません。
キャパオーバーによる思考停止は、脳が非常事態に陥ったときの正しい反応です。
そんな時、ほとんどは「もっとがんばればなんとかなる」とか、「ちょっと1週間くらい休めたら良いのにな」とか、頑張ったり休んだりして、もう一度頑張って解決しようとしますよね。
でも、仕事のキャパオーバーで思考停止に陥ってしまっている場合、休んでもさらにタスクが増えてしまうケースもあります。
さらには、休んでも、仕事が気になって心が全く休まらない可能性もあります。
そうすると、逆効果になってしまって、状況がさらに悪化している場合もあります。
だから本当は、この状態から抜け出す方法は、「がんばる」でも「休む」でもないんです。
あなたが今日この問題点の本質に気づくことができれば、今日から人生が変わり始めます。
だから、長いかもしれませんが、この文章を読む時間がないと感じてしまうかもしれませんが、なんとか全部読み切ってみてください。
必ず今のあなたのキャパオーバーで思考停止に陥っている状況には、本当に効果的な内容になっています。
今5分の時間を取って、一生使える方法を知るか、今その5分を惜しんで目の前のタスクに負われ続ける人生を送るか、よく考えてみてください。
必ずあなたの今の状況を変えるきっかけになると確信しています。
あなたに今すぐ必要な解決策というのは、実は思考を取り戻すための具体的な設計とステップなんです。
この記事では、あなたの混乱を整理し、正常な判断力を取り戻すための方法をお届けします。
「今の自分は、読む力すらない」
そう思ったあなたにこそ、届いてほしい内容です。
どうか一人で抱え込まないで。
これは危機ではなく、ここからの人生の「回復のはじまり」です。
ここからしっかりと詳しく解説していきますね。
なぜ“仕事でキャパオーバー”すると“思考停止”になるのか

皆さんは仕事でキャパオーバーになると、なぜ思考停止になるのか考えたことがありますか?
忙しい合間に新しいタスクが次から次へと舞い込むと、私たちの脳は「これ以上は無理だ」と感じてしまいますよね。
これは、精神的にいっぱいいっぱいになっているだけだと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこれには脳の仕組みが密接に関わっています。
脳にはワーキングメモリと呼ばれる情報処理の一時保存場所があり、その一時保存場所には限りがあり、どれだけの情報を同時に扱えるかは決まっています。
複数の指示が同時に頭をよぎると、脳はまるで重すぎるソフトを起ち上げたパソコンのように動かなくなってしまうのです。
さらに、無理を重ねた結果としてストレスがどんどん溜まります。
ストレスホルモンは脳内で情報を整理し判断する「前頭前野」の働きを鈍らせます。
こうなると、いつもなら素早く判断できる人でも、まるで交通整理が乱れた交差点のように、「考えが止まった!」と感じるような現象が起こってしまうのです。
これが思考停止の本当の正体なんです。
「お昼に何を食べようかな」という日々の些細な意思決定の積み重ねでも、実は大きな負担になっています。次々と決断を迫られる環境では、「決断疲れ」という現象が起こります。
その結果、脳の自己制御のエネルギーが枯渇し、効果的な判断ができなくなるのです。
以上のような背景から、仕事でキャパオーバーに陥ると、ただの肉体的な疲れだけではなく、認知資源の限界、ストレスによる脳機能の低下、そして連続する意思決定によるエネルギー消耗が重なり、最終的に「思考停止」状態へと導かれてしまいます。
これは決して怠けではなく、科学的な理論と実験により裏付けられた現実なのです。
だからこの「思考停止」の状態を生み出さないような仕組みを日々のタスク管理の設計に組み込んでしまえば、あなたはどんなにタスクが多くても、どんなに忙しくても、「思考停止」の状態にならないようにすることもできますし、それどころか、どんどんタスク処理がスムーズにできるようにしていくこともできるのです。
あなたがキャパオーバーで「思考停止」の状態に陥っているのは、実は脳の仕組上そうなっている
に過ぎないのです。
だから、どんな人にでも、キャパオーバーで「思考停止」の状態を解決することは必ずできるんです。
これからその方法についてはご説明していきますね。
私自身、とても大事なことを全力でこの記事に詰め込んでいます。この記事を読んで、思考停止に陥ることのないように、最後まで読んでくださいね。
仕事でキャパオーバーしてしまう原因を整理しよう

まずは、自分がなぜキャパオーバーに陥ってしまうのか、その原因を一つひとつ丁寧に洗い出してみましょう。
原因がはっきりすると、その後に打つべき対策も見えてきます。
ここでは洗い出しのヒントとなるポイントをお伝えしますね。
1. 仕事量・タスクの増加
頭の切り替えが必要な、種類の異なるタスクを一度に抱えすぎていませんか?
あるいは、一つひとつはシンプルな作業でも、その数が次々と増えてしまっている状況ではないでしょうか?
また、あなた自身が「タスク」と意識していなくても、無意識のうちにエネルギーを消耗していることもあります。
例えば、会社の中で「なんだか空気がピリピリしている」と感じる瞬間や、取引先との関係がうまくいっていないという直感。
これらはまだ大きな問題として表面化していなくても、その不安やストレスがじわじわと心を押しつぶし、あなたの脳のキャパシティを次第に圧迫していく可能性があります。
2. 時間管理・優先順位のあいまいさ
「この仕事、本当に意味あるのかな?」という違和感を感じていませんか?
「やっていることが、自分の目指す方向とズレている気がする…」そんな感覚があると、気づかぬうちに心にブレーキがかかってしまいます。
たとえば、ゴールがぼんやりしたまま走り続けるマラソンのようなもの。
どこを目指せばいいのか分からないまま走り続ければ、いずれ疲れ果ててしまいます。
それでも無理やり走り続けていると、少しずつ、でも確実に、心のゆとりが削られていきます。やる気や集中力が落ちてくるのも当然のことです。
つまり、優先順位のあいまいさや目的とのズレこそが、キャパオーバーを引き起こす大きな原因になることがあるのです。
3. プライベートとの両立の難しさ
キャパオーバーしているのは仕事中。
でも、その原因が「仕事」だけとは限りません。
たとえば、家庭での役割、育児や介護、体調管理、人間関係のストレスなど、プライベートの負担がじわじわと影響していることも少なくありません。
プライベートで心がざわついていると、仕事中も集中力が散漫になり、小さなミスが増えたり、判断に時間がかかったりします。
その結果、予定通りに進まないことでさらに焦り、キャパオーバー感を強めてしまうのです。
また、「どちらも頑張らなければ」と自分を追い込むことで、どこにも逃げ場がなくなってしまうこともあります。
仕事とプライベートは切り離して考えがちですが、実際には深くつながっていて、互いに影響し合っています。
だからこそ、キャパオーバーの原因を探るときには、「仕事」だけでなく、「今、自分の生活全体にどんな負担がかかっているのか?」にも目を向けてみることが大切です。
“思考停止”の正体を知る|行動分析学の視点から見る止まり方

思考停止状態に陥ると、何も手につかなくなり、自分を責めてしまう。
そんな悪循環に入りやすくなります。
行動分析学の視点から見ると、この「思考停止」にも解決の糸口があります。
行動分析学とは、「なぜその行動が起こるのか」「どうすれば望ましい行動が増えるのか」を、環境との関係の中で科学的に探っていく学問です。
行動分析学では「行動」は意図的にコントロールできるものであるとされています。
また行動分析学では、思考も立派な「行動」だと考えるので、行動分析学を活用すれば、思考停止状態を解決することもできます。
なぜ思考停止になるのか?
多くの場合、私たちは「これまでうまくいったやり方」や「慣れた思考パターン」に頼って物事を進めています。
たしかに、いつものパターンが通用する場面では、それで問題ありません。
けれど、状況が変化していることに気づかず、同じやり方を繰り返していると、
うまくいかない場面にぶつかったとき、頭は混乱し、「どうしたらいいのか分からない」と立ち止まってしまうのです。
これが、行動分析学の観点から見た思考停止の正体です。
思考停止を解消するための第一歩

思考停止状態から抜け出すには、「今までのやり方」を繰り返すのではなく、あえて違う行動を挟むことが重要なカギになります。
たとえば、
- 「いったん立ち止まって、紙に書き出してみる」
- 「信頼できる誰かに話してみる」
- 「作業場所を変えてみる」
- 「タスクをびっくりするほど小さくしてみる」
こういった、ほんの小さな行動のスイッチが、新たな思考の流れを生み出すきっかけになるのです。
「止まった自分」を責めずに、行動から再起動しよう
止まってしまった自分を責める必要はありません。
むしろ、「今は、これまでのやり方では進めないタイミングなんだ」と受け止めて、行動を変えることで、思考を再起動する。
これが思考停止への新しいアプローチです。
キャパオーバーな脳内を俯瞰する

前の章でもお伝えしたように、「いつもと違う行動」をひとつ挟むだけで、止まっていた思考が動き出すことがあります。その中でも特に効果的なのが、自分の思考や状況を「俯瞰」することです。
たとえば、仕事もプライベートも関係なく、「気になっていること」「やらなきゃと思っていること」「本当はやりたいと思っていること」これらをすべて、紙に書き出してみてください。
頭の中に詰め込んだままでは、優先順位を整理するのもひと苦労。
気づけば感情に流されて、本当に大切なことを見失いやすくなります。まるで、散らかった部屋の中で探し物をしているようなものです。
でも、書き出すという行為を通じて、頭の中のごちゃごちゃをいったん外に出してあげる。
すると、不思議と冷静になれて、「これは今やるべき?」「そもそも、自分がやる必要ある?」といった問いが自然と浮かんできます。
次に大切なのは、「やらなくてもいいこと」をはっきりさせること。
中には、今やらなくてもいいこと。誰かにお願いした方がいいこと。実は自分が抱え込む必要のないこともあります。
「今はやらない」と決めてしまうことで、毎回の判断に使っていたエネルギーを節約できます。これだけでも、脳内に少しずつ“余白”が生まれてくるのです。
そして最後にやるべきは、タスクの引き算です。
やらなければ、という気持ちが強いと、つい自分のキャパシティ以上に背負ってしまいがちです。
でも、本当に大切なのは、すべてをこなすことではなく、「今の自分に無理なくできること」に集中すること。
タスクを絞り込むことで、思考はクリアになり、行動にも自然とエネルギーが戻ってきます。
この「俯瞰→手放す→整える」という流れこそが、思考停止から脱し、行動を再起動するための確かな一歩になるのです。
思考を整理する方法について、より具体的に解説している記事はこちらです。
第三者の視点を取り入れて思考停止を解消する
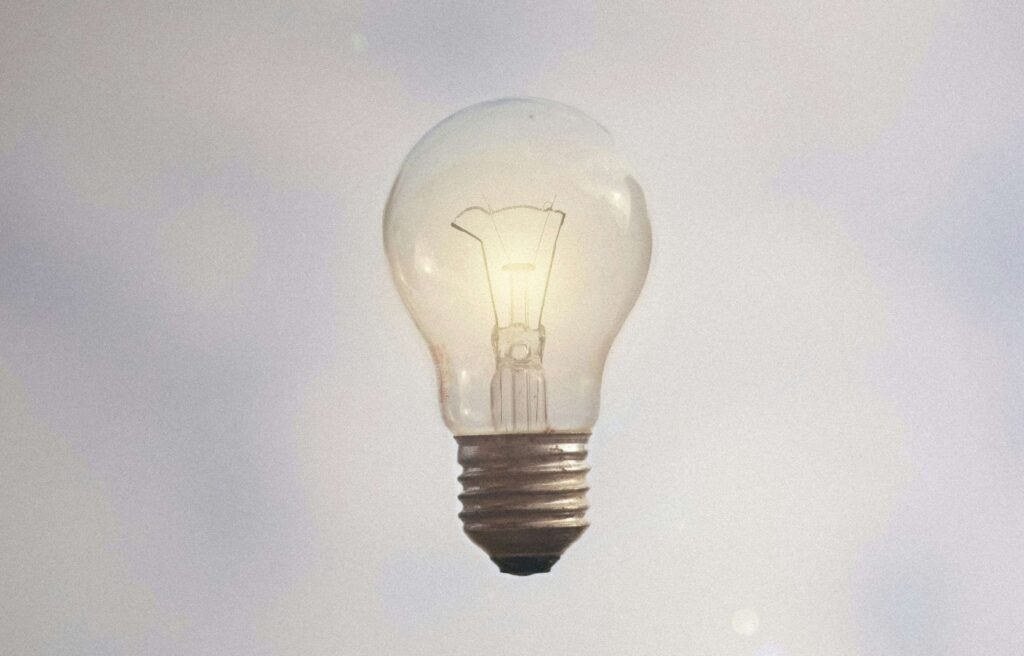
「なんとか自分ひとりで整理しなきゃ」
そんなふうに思って頑張りすぎていませんか?
実はその気持ちが、いつのまにか視野を狭めてしまっていることがあります。
たしかに、自分の頭で考えて、紙に書き出して、俯瞰するのはとても大事なプロセスです。
でも、それだけでは行き詰まってしまうときもあるんです。
そんなときに力をくれるのが、第三者の視点。
誰かに話すことで、自分では見えていなかった考え方に気づけたり、「そんなふうに捉えてよかったのか」と新しい視点を得られたりします。
上司や同僚、信頼できる友人、そしてときには専門家のフィードバックが、止まっていた思考をそっと動かしてくれることもあります。
とくに…
・問題が複雑すぎるとき
・感情が強く絡んでいるとき
そんな状況では、自分ひとりで考え続けるよりも、外からの視点によって、現状を客観的に整理できるようになります。
当社では、専門家があなたと一緒に状況を俯瞰し、行動分析学を活用してタスクの優先順位や見直しをサポートするサービスをご用意しています。
これまで7万回以上、「人の行動を変える」ことにサポートをしてきました。
私にご依頼くださると、あなたを思考停止状態から抜け出させ、さらにやるべきことが明確になり、あなたが望む結果にどんどん近づいていくことを実感できるようになります。
私のセッションで他と大きく違うのは、あなたがなぜ思考停止状態になっているのかその原因を探るため、再発が起きないようにサポートできる点です。
「もう頭の中がいっぱいで、何から手をつけていいか分からない」そんなふうに感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
サービスの詳細はこちらです。
まとめ|キャパオーバー・思考停止から抜け出すために大切なこと

タスクに追われて、頭も心も止まってしまったように感じるとき。そんなときこそ「いつもと違う行動パターン」を取り入れることが大切です。
行動が変われば、環境が変わります。そして、環境が変われば、思考も自然と動き出します。
キャパオーバーや思考停止は、あなたの意志の弱さが原因ではありません。それは、「今までのやり方では、もう進めない」というサインです。
だからこそ、この記事を読み終えた「今」が、仕事をリセットし、再構築する回復のはじまり”になるのです。
次の一歩|今日からできる“思考停止”回避アクションリスト
「思考停止を防ぐには具体的にどうすればいいの?」そんなあなたに、今日から始められる小さな行動をご紹介します。
✅ 1日5分の書き出し習慣
頭の中の「気になること」「やらなきゃと思っていること」「やりたいこと」を、毎日たった5分だけ紙に書き出す。思考を外に出すだけで、整理の一歩が始まります。
✅ 「やらなくていいこと」を1つ手放す
今日は何をやらないと決めますか?保留・削除・人に任せるのも立派な選択です。
✅ 場所を変えて、タスクに向き合ってみる
環境の変化は、思考の流れを変えるきっかけになります。カフェ、自習室、別の部屋など、ほんの少しの移動でもOK。
✅ 週1回、専門家に話して状況を俯瞰する
信頼できる相手に話すことで、ひとりでは見えなかった視点に気づけます。当社でもサポートを提供しています。必要な方はいつでもご相談ください。サービスの詳細はこちらです。
✅ 「小さく動く」ことを毎日のタスクにする
行動は思考の再起動スイッチ。いきなり全部やろうとせず、1つでも動けば十分です。
少しずつで大丈夫。今日の「ひとつのアクション」が、明日のあなたの思考を救ってくれます。